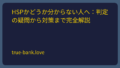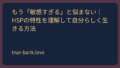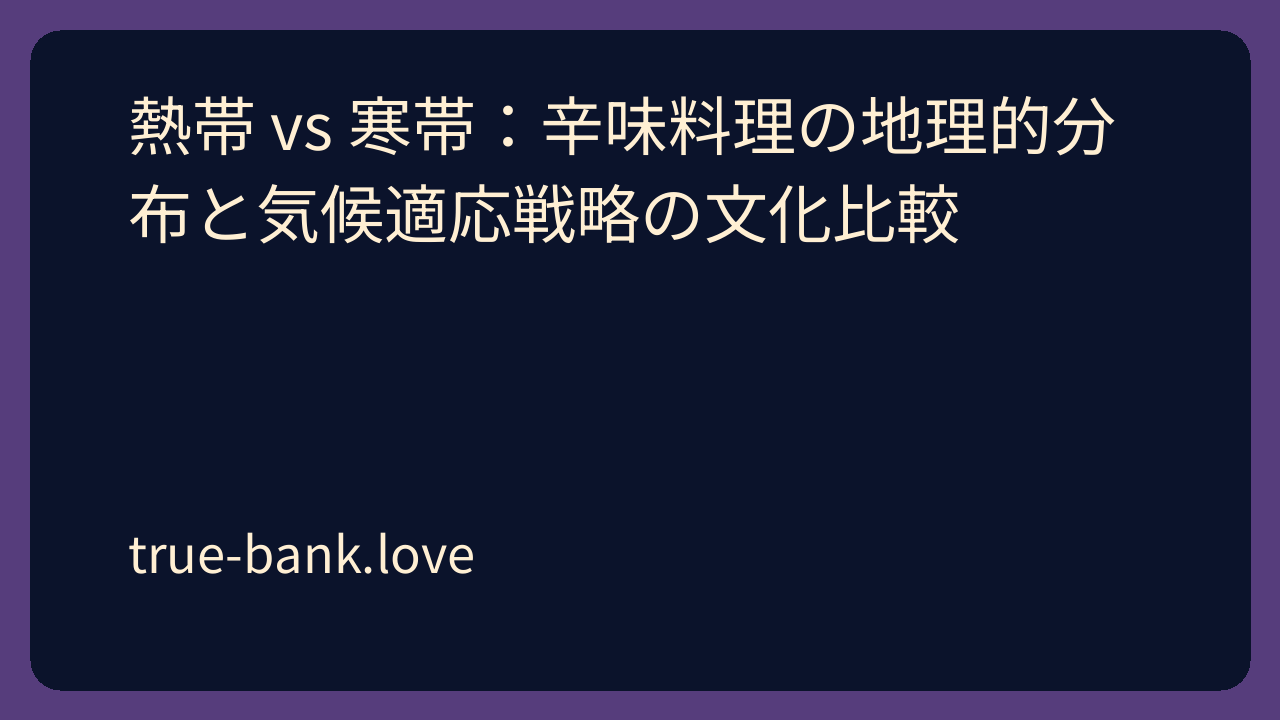第4部:進化と文明の交点 – 唐辛子の文化生態学
4.1 地理的拡散と文化融合:コロンブス交換と世界の食文化革命
唐辛子(Capsicum属)の原産地は南米アンデス地域と考えられているが、その世界的な拡散は人類の食文化史における最も劇的な転換の一つである。「コロンブス交換」として知られる生物学的・文化的交流の中で、唐辛子は驚異的なスピードで世界中に広がった。
← [前の記事]
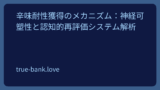
[次の記事] →
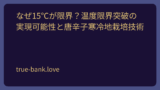
唐辛子の原産地と初期家畜化
考古学的証拠によれば、唐辛子の家畜化は少なくとも6,000年前頃(紀元前4000年頃)に現在のメキシコで始まったと考えられる:
初期栽培種: 最古の家畜化証拠はTehuacán渓谷(メキシコ)で発見されたが、当初の推定年代は約9,000-7,000年前とされていた。しかし、より精密なAMS(加速器質量分析)による直接年代測定により、より保守的な年代が示されている。
多中心的家畜化: 複数の独立した家畜化イベントが南米の異なる地域(アンデス東部、アマゾン流域など)で発生した可能性が高い。
品種多様化: 先コロンブス期のメソアメリカとアンデス文明において、既に用途別に多様な品種が栽培されていた。
DNA分析と考古学的証拠を統合した研究により、少なくとも5種のCapsicum(C. annuum, C. baccatum, C. chinense, C. frutescens, C. pubescens)が独立して家畜化されたと考えられている。この多様性が、後の世界的拡散の基盤となった。
コロンブス交換と初期拡散パターン
1492年のコロンブスの航海に続く「新世界」探検により、唐辛子は旧世界へと急速に拡散した:
ヨーロッパへの導入: コロンブスが最初に唐辛子の標本をスペインに持ち帰ったが、当初は観賞植物として扱われた。
アジアへの早期伝搬: ポルトガル商人により、1500年代初頭にインドへ、そして東南アジアと中国へと急速に広がった。
アフリカへの伝播: ポルトガルとアラブの交易ネットワークを通じて、西アフリカと東アフリカ沿岸に導入された。
興味深いことに、唐辛子の拡散は他の新世界作物(トウモロコシ、ジャガイモなど)と比較して著しく迅速だった。これは、種子の小ささ(容易な運搬)、栽培の単純さ、そして何よりも風味への即時的なインパクトによると考えられる。
在来料理体系への統合
唐辛子が最も深く根づいたのは、既に辛味香辛料(黒胡椒、生姜、山椒など)を使用していた食文化圏である:
インド亜大陸: 辛味を重視するインド料理は唐辛子を急速に採用し、今日では世界最大の唐辛子生産地となっている。
中国四川・湖南地方: 花椒(山椒)の辛味を既に好んでいた地域で、「麻辣」(痺れと辛さの組み合わせ)という独特の風味複合体が発展した。
東南アジア: 生姜やガランガルなどの刺激的香辛料が既に普及していた東南アジアでは、唐辛子が在来料理に深く統合された。
ハンガリー: ヨーロッパでは例外的に唐辛子(パプリカ)を広く採用し、国民的料理の中核成分とした。
これらの文化的採用パターンは、単なる味覚的選好を超えた「風味的互換性」と「文化的受容性」の相互作用を示している。既存の辛味香辛料を使用していた文化は、唐辛子の辛味を認知的に「馴染み深い異質性」として解釈し、より容易に採用したと考えられる。
文化的変容と新たな辛味の意味論
唐辛子の採用は単なる調味料の追加ではなく、多くの文化において料理と味覚の概念的再構成をもたらした:
韓国のキムチ文化: 唐辛子導入前のキムチは赤くなく、現在の辛味も持たなかった。唐辛子がキムチの中核的アイデンティティとなったのは17-18世紀の現象である。
メキシコのモレソース: 先住民のチリソースとスペインの調理技術が融合し、チョコレートと唐辛子を組み合わせた複雑なモレソースが誕生した。
イタリア南部のペペロンチーノ: シンプルな料理に唐辛子を取り入れ、地域料理のアイデンティティ形成に寄与した。
アフリカのハリッサとベルベルソース: 北アフリカでは現地の香辛料と唐辛子の融合により、独自の辛味調味料文化が発展した。
これらの事例は、唐辛子がもたらした「文化的翻訳」の過程を示している。興味深いことに、多くの文化で唐辛子は「外来」と認識されることなく、まるで「常にそこにあった」かのように文化的記憶に統合された。
4.2 辛味嗜好の進化心理学:なぜ人間は「痛み」を好むのか
人間が辛い食品を好む傾向は、進化生物学的な観点からは一見逆説的である。辛味は本質的に痛みの信号であり、有害物質の存在を警告する機能を持つ。しかし、世界中の多くの文化で人々は積極的にこの「警告信号」を求め、享受している。この逆説は、複数の進化心理学的枠組みから説明が試みられている。
調味毒物学と感覚的ホルメシス
辛味嗜好の最も基本的な説明は「調味毒物学(culinary toxicology)」の枠組みに基づく:
低用量ホルメシス: カプサイシンは低用量では有益な生理的応答(代謝促進、抗菌作用など)を引き起こす。これは「ホルメシス」(低用量ストレスによる適応的利益)の一例と見なせる。
リスク-報酬評価: 人間の味覚システムは、潜在的リスク(苦味・辛味)と潜在的報酬(栄養価・風味)のバランスを評価するよう進化した。唐辛子の場合、適度なリスク信号が特別な風味体験と結びついている。
解毒酵素誘導: 辛味物質への曝露は解毒酵素系を活性化し、環境毒素への耐性を高める可能性がある。これが長期的な適応価を持つ可能性がある。
この視点は、辛味嗜好が「適応的な薬理学的自己調整」の一形態である可能性を示唆している。つまり、人間は潜在的に有益な植物化学物質を適度な量で摂取するよう進化的に動機づけられているというものだ。
環境適応としての辛味消費
辛味嗜好の分布には地理的・気候的パターンが見られ、これが環境適応説を支持する:
熱帯地域での高頻度: 辛味食品消費は一般に熱帯・亜熱帯地域で最も顕著である。
食品保存効果: 高温多湿環境では、唐辛子の抗菌・抗真菌特性が食品保存に寄与する。
温熱調節互恵性: 唐辛子摂取による発汗促進が、高温環境での体温調節を助ける可能性がある。
Sherman & Billing (1998)の分析によれば、植物性抗菌物質(カプサイシノイドを含む)の利用は、微生物汚染リスクの高い地域で特に顕著である。ただし、近年の研究(Bromham et al., 2021)では、地理的・系統的非独立性を統計的に調整すると、この相関関係の有意性が減弱することが指摘されている。
社会シグナリングと集団識別
辛味嗜好には重要な社会的次元があり、これが現代社会でも持続する主要な推進力かもしれない:
勇気/強靭さの誇示: 辛い食品の摂取は「痛みへの耐性」の社会的誇示として機能し、間接的に強靭さや勇気を信号する。
集団帰属の標識: 特定の辛味レベルや様式の好みが、文化的・社会的アイデンティティのマーカーとなる。
共有感覚体験: 共に辛い食品を消費することで生じる独特の感覚体験が、社会的結合を強化する。
人類学的研究によれば、多くの文化で辛味耐性は「通過儀礼」や「男性性の証明」などの社会的文脈と結びついている。現代社会でも、「チリチャレンジ」などの形で、この社会シグナリング機能が維持されている。
感覚追求と快感誘導
神経科学的観点からは、辛味嗜好は「感覚追求」と「快感誘導」の文脈で理解できる:
感覚的新奇性: 辛味は通常の食事体験にない強烈な感覚刺激を提供し、感覚的単調さを破る。
内因性オピオイド放出: 研究により、カプサイシン投与が脳内でPOMC(プロオピオメラノコルチン)mRNAレベルを有意に増加させ、β-エンドルフィン産生を促進することが確認されている。この内因性オピオイド系の活性化が「自然な高揚感」をもたらす。
感覚的コントラスト: 辛味とそれに続く緩和(例:甘味、脂肪)のコントラストが強化された快感をもたらす。
これらの要因は、個人の「感覚追求傾向」と辛味嗜好の相関を説明する。実際、感覚追求スケール(SSS)の高スコアは、辛い食品への選好と有意に相関することが複数の研究で示されている(Terasaki & Imada, 1988; Byrnes & Hayes, 2015)。
革新的視点:辛味の認知的再定義
辛味嗜好の最も興味深い側面の一つは、「痛み」という通常否定的な感覚経験の認知的再定義である。この現象を説明する革新的視点として、「感覚的境界越え」理論を提案したい:
感覚的カテゴリー越境: 辛味体験は、本来的に否定的な感覚(痛み)を「楽しむべき体験」という通常相容れないカテゴリーに再分類する認知的柔軟性を必要とする。
メタ認知的フレーミング: 辛味愛好家は「これは痛みだが、危険ではない痛み」という認知的フレームを構築し、通常の感覚評価システムを一時的に迂回する。
認知的境界空間の拡張: 繰り返される辛味体験は、「快-不快」「安全-危険」という二項対立的感覚評価の境界を再構成し、より複雑な感覚評価空間を創出する。
この視点に立てば、辛味嗜好の発達は単なる「耐性獲得」ではなく、感覚体験の認知的カテゴリー化を根本的に再構成する過程と見なせる。この再構成能力は、おそらく人間特有の認知的柔軟性の現れであり、他の認知的境界越えの例(芸術における不協和音の享受、恐怖映画の娯楽性など)と並行して理解できる。
4.3 気候と食文化の相関:辛味料理の地理的分布パターン
辛味料理の世界的分布には、明確な地理的・気候的パターンが観察される。これらのパターンは単なる偶然ではなく、気候条件、食材利用可能性、微生物学的環境、そして文化的拡散経路の複雑な相互作用を反映している。
気候帯と辛味強度の相関:実証データと最近の批判
Sherman & Billing (1998, 1999)による包括的研究では、93冊の伝統料理本から4,578のレシピを分析し、36カ国のパターンを調査した:
実測データ:
- インド(平均気温26.9°C):平均9.3スパイス/レシピ
- ノルウェー(平均気温2.8°C):平均1.6スパイス/レシピ
- 一般傾向: 平均気温の上昇と共に、スパイス使用頻度、レシピあたりスパイス数、抗菌性の高いスパイスの使用頻度が全て増加した
抗菌効果: 実験室研究により、カプサイシンを含む唐辛子は約75%の細菌を阻害・殺菌する能力を持つことが確認されている。
批判的再評価: ただし、近年のBromham et al. (2021)の分析では、地理的近接性と文化的関連性を統計的に調整すると、気温と辛味使用の相関は有意性を失うことが示されている。この研究は、観察された相関が真の因果関係ではなく、関連する諸要因の結果である可能性を示唆している。
栄養生態学と辛味補完性
辛味料理は特定の食材との強い関連性を示す:
炭水化物主食との相関: 米、トウモロコシ、キャッサバなどの比較的淡白な主食が中心の食文化で、辛味調味料の使用が顕著である。
タンパク質摂取と辛味緩和: 肉類の利用可能性が高い食文化では、一般に辛味の使用が控えめになる傾向がある。
脂質との相乗効果: 中南米(アボカド)、インド(ギー)、東南アジア(ココナッツミルク)など、辛味料理は脂質と組み合わされることが多い。これはカプサイシンの脂溶性と、脂質による辛味緩和効果を反映している。
これらのパターンは、辛味が単なる味覚的嗜好ではなく、利用可能な食材の栄養価を最大化し、感覚的単調さを打破する機能を持つことを示唆している。
文化伝播と地理的障壁
辛味料理の分布は、文化伝播の経路と地理的障壁によっても大きく形作られている:
海洋交易ルート: ポルトガル交易網が唐辛子の世界的拡散の主要経路となり、インド洋沿岸諸国での早期採用をもたらした。
山脈と砂漠の障壁: ヒマラヤ山脈が北インド料理と中国料理の辛味パターンの相違に寄与し、サハラ砂漠が北アフリカと西アフリカの料理様式を分離した。
言語・文化境界: 言語系統と辛味嗜好の間には興味深い相関がみられる(例:タイ語族とラオ語族の辛味強度の類似性)。
これらの伝播パターンは、文化進化の重要な側面を示している。辛味嗜好は単なる個人的選好ではなく、文化的学習と社会的伝達を通じて伝播する「文化的形質」である。
気候変動と辛味文化の未来
気候変動は辛味料理の地理的分布に新たな変数をもたらしている:
栽培地域の北方シフト: 温暖化により、唐辛子栽培の北限が徐々に高緯度へとシフトしている。
新たな病害虫圧: 気候パターンの変化が唐辛子の病害虫パターンを変化させ、これが栽培品種と辛味レベルの選択に影響する可能性がある。
文化的適応: 気候変動に伴う食材利用可能性の変化が、辛味料理の再構成と適応を促す可能性がある。
特に注目すべきは、温暖化が進行する北方地域(ロシア、カナダ、北欧など)における唐辛子栽培の新たな可能性である。これらの地域では、伝統的に辛味料理が限定的だったが、栽培可能性の拡大と共に、新たな辛味料理伝統が発展する余地がある。
4.4 伝統医学システムにおける唐辛子:古代知識と現代科学の接点
世界各地の伝統医学システムは、唐辛子の薬理学的特性を経験的に認識し、様々な治療的応用を発展させてきた。これらの伝統的知識体系は、現代科学による再評価と検証の対象となっている。
伝統医学における多様な応用
主要な伝統医学システムにおける唐辛子の位置づけと応用:
アユルヴェーダ(インド): 「アグニ」(消化の火)を強化し、「カパ」(粘液)を減少させる物質として位置づけられる。消化促進、気管支炎、関節痛に用いられる。
中国伝統医学: 「熱性」で「血行促進」の性質を持つとされ、「気滞」と「寒証」の状態に適用される。循環促進、消化不良、関節痛に用いられる。
マヤ・アステカ医学: カタル、咳、歯痛などに対する重要な薬草として用いられた。また、出産後の回復促進にも使用された。
アフリカ伝統医学: 西アフリカでは発熱、リウマチ、皮膚感染症の治療に用いられ、特にシア油との混合剤が一般的。
これらの応用は、カプサイシンの生理活性に関する現代的理解と多くの点で一致している。例えば、「血行促進」効果は血管拡張作用に、「消化促進」効果は消化液分泌促進と胃粘膜保護作用に対応する。
民族薬理学的体系と使用形態
唐辛子の医療応用は、複数の投与経路と調製法を含む:
内服応用: 煎じ薬、チンキ剤、発酵調製物として消化器系疾患、循環器疾患、呼吸器疾患に使用。
局所応用: 軟膏、湿布、油浸出液として関節痛、筋肉痛、神経痛に適用。
混合処方: 他の薬草(ニンニク、生姜、クルクマなど)との相乗効果を活用した複合処方が一般的。
予防的利用: 日常的な食事への少量添加による慢性疾患予防と健康維持。
特に注目に値するのは、異なる文化が独立して類似の医療的応用を発見した事実である。これは、カプサイシンの生理効果が十分に顕著で一貫性があり、経験的観察を通じて複数の文化で検出可能だったことを示唆している。
伝統的知恵の科学的再評価
現代科学は、これらの伝統的応用の多くに科学的根拠を提供している:
鎮痛効果: TRPV1受容体の脱感作による慢性痛緩和は、関節炎や神経痛に対する伝統的使用を裏付ける。研究により、カプサイシンがカルシウム依存的メカニズムによりTRPV1の脱感作を引き起こすことが確認されている。
消化促進作用: 胃酸分泌と粘液産生の促進は、消化不良に対する伝統的使用と一致する。
抗菌・抗真菌効果: 感染症に対する伝統的応用を説明する。実験的研究により、カプサイシンは濃度依存的に様々なグラム陽性・陰性細菌に対して静菌的または殺菌的効果を示すことが確認されている。
代謝促進効果: 「身体を温める」という伝統的概念は、熱産生増加と代謝率上昇という科学的事実に対応する。
現代医薬品開発への貢献
伝統医学における唐辛子の用途は、現代薬理学研究と医薬品開発に影響を与えてきた:
局所鎮痛剤: **8%カプサイシンパッチ(Qutenza®)**は、2009年にFDAが帯状疱疹後神経痛に、2020年に糖尿病性末梢神経障害に承認した現代医薬品である。30分の施術で最大3ヶ月の鎮痛効果を提供し、伝統的な痛み管理法に科学的洗練を加えたものと見なせる。
機能性消化管障害治療: 過敏性腸症候群に対するカプサイシン含有処方は、伝統的消化器治療の現代版と言える。
代謝促進補助剤: ダイエットサプリメントにおけるカプサイシン利用は、伝統的な「代謝活性化」概念の商業的応用である。
このように、伝統医学は現代薬理学研究の「先見的仮説生成装置」として機能し、研究方向の特定と優先順位付けに貢献している。
薬食同源と統合医療アプローチ
東アジアの「薬食同源」(医食同源)の概念は、唐辛子のような物質の二重の役割—調味料であり同時に医薬品である—を捉える上で特に有用である:
予防医学の枠組み: 日常的な唐辛子摂取が慢性疾患予防に寄与するという考えは、「食事を通じた健康維持」という予防医学的視点と一致する。
個別化適用: 体質や症状に応じた唐辛子の適用量調整は、現代の精密医療・個別化医療のパラダイムと共鳴する。
全体論的視点: 単一の化合物ではなく、唐辛子全体(複数のカプサイシノイドと他の生理活性物質の複合体)に価値を置く伝統的アプローチは、現代の「多成分相乗効果」研究と連携する。
これらの原則は、唐辛子を含む統合医療アプローチの基盤となり、伝統的知恵と現代科学の対話を促進する。
革新的視点:異時性知識体系としての伝統医学
伝統医学と現代科学の関係を理解するための革新的枠組みとして、「異時性知識体系」という概念を提案したい:
異なる時間性を持つ知識: 伝統医学は「長期的・累積的観察」に基づく知識であり、現代科学は「短期的・集約的実験」に基づく知識である。両者は本質的に異なる時間スケールで知識を生成する。
相補的認識論: 科学的還元主義が「どのように作用するか」という機序を解明する一方、伝統医学の現象論的アプローチは「どのような文脈で効果があるか」という状況的知識を提供する。
知識翻訳の非対称性: 伝統医学の概念を現代科学の言語に翻訳することも、逆も、完全には不可能である。これは概念的枠組みの非互換性を反映している。
この視点は、伝統医学を「未熟な科学」あるいは「迷信的残滓」としてではなく、「異なる時間性と方法論に基づく知識体系」として再評価することを促す。唐辛子の伝統的応用は、この異時性知識体系の好例であり、両方の知識伝統の強みを組み合わせることで、より包括的な理解と応用が可能になる。
4.5 革新的視点:生物文化的共進化としての辛味
唐辛子と人間の関係を最も包括的に理解するには、「生物文化的共進化」という枠組みが必要である。この視点では、唐辛子の生物学的特性と人間の文化的実践が相互に形作り合う動的プロセスとして捉えられる。
相互形成的進化の軌跡
唐辛子と人間の関係は、一方向的な「使用」ではなく双方向的な「共進化」として理解できる:
人間による選択圧: 人間の味覚選好と栽培実践が唐辛子の遺伝的多様性を形作った。特定の辛味レベル、風味プロファイル、形態的特徴を持つ品種が選択的に繁殖された。
唐辛子による文化形成: 唐辛子の生物学的特性(特にカプサイシンの感覚効果)が、人間の食文化、医療実践、そして社会的儀礼を形作った。
共進化的適応: 唐辛子の進化と人間文化の発展は、相互にフィードバックを与え合いながら進行してきた。
この視点から見ると、現在の多様な唐辛子品種(300以上の栽培品種が存在)は、人間の選好と栽培実践の物質的具現化と言える。同様に、世界各地の辛味料理伝統は、唐辛子の生物学的特性への文化的応答として理解できる。
ニッチ構築としての辛味文化
人間と唐辛子の関係は「ニッチ構築」の優れた例でもある:
生態学的ニッチ拡大: 人間は唐辛子の原生地を超えて、適応的に不可能だった気候帯にまで栽培範囲を拡大した。
文化的ニッチ創造: 唐辛子を中心とした料理体系、医療実践、社会的儀礼という「文化的ニッチ」が構築された。
感覚的ニッチ形成: 辛味耐性と嗜好の発達を通じて、人間は通常は回避される感覚刺激(痛み)を享受する独自の「感覚的ニッチ」を創造した。
このニッチ構築過程は累積的であり、世代を超えて強化されてきた。現代社会では、このプロセスがさらに加速し、辛味文化の急速なグローバル拡散と辛味強度の「軍拡競争」(超辛唐辛子品種の開発)として現れている。
文化的情報伝達と辛味の記号学
辛味は単なる感覚刺激を超え、複雑な文化的記号体系の一部となっている:
アイデンティティ標識: 特定の辛味パターンが地域的・民族的アイデンティティの重要なマーカーとなる(例:韓国の「매운맛」、メキシコの「picante」、タイの「pet」)。
社会的階層化: 辛味耐性と嗜好が社会的区分(性別、年齢、階級など)に関連付けられる場合がある。
情動象徴: 辛さが「情熱」「強さ」「生命力」などの抽象的概念の象徴として機能する。
この記号学的次元は、辛味の文化的持続性と伝播を理解する上で不可欠である。辛味は単なる味覚的選好ではなく、意味が込められた文化的実践である。これにより、例えば移民集団が不利な条件下でも辛味料理伝統を維持する強い動機が説明される。
感覚進化としての辛味嗜好
辛味嗜好の発達は、人間の感覚能力の文化的進化の一例と見なせる:
感覚的可塑性: 辛味耐性の獲得は、神経系の可塑性と感覚評価システムの再構成能力を示す。
感覚的報酬再構築: 本来逃避的な刺激(痛み)が接近的刺激(快楽)へと転換される特殊な例。
意図的感覚修飾: 人間が意図的に特定の感覚体験を求め、改変する能力の例証。
この感覚進化の能力は、音楽鑑賞、芸術的感性、美食文化など、他の「高次感覚活動」と並行して理解できる。これらはすべて、基本的な感覚入力を文化的実践を通じてより複雑な体験へと変容させる人間特有の能力を示している。
未来の辛味共進化:可能性の領域
人間と唐辛子の共進化関係は、新たな方向に進化し続ける可能性がある:
温度限界の突破: 寒冷耐性品種の開発は、唐辛子のエコロジカルニッチを拡大し、新たな文化的ニッチの創造につながる可能性がある。
感覚設計の進化: 特定の感覚プロファイルを持つ唐辛子品種の精密設計(例:辛味の時間的展開、副次的風味特性など)が進行する可能性がある。
機能性辛味の発展: 特定の健康効果に最適化された辛味プロファイルの開発(例:代謝活性化特化型、鎮痛特化型など)。
新たな文化的文脈: グローバル化とローカル文化の相互作用を通じた、辛味の新たな文化的意味と実践の創発。
これらの可能性は、人間と唐辛子の共進化的関係が静的な「終着点」ではなく、継続的に展開するプロセスであることを示唆している。
結論:辛味の文化生態学
本章では、唐辛子の地理的拡散と文化統合、辛味嗜好の進化心理学、気候と食文化の相関、そして伝統医学における応用を探究してきた。これらの視点を統合すると、辛味は単なる感覚刺激ではなく、生物学的特性と文化的実践が複雑に絡み合う「生物文化的現象」として理解できる。
特に注目すべきは、辛味をめぐる「逆説の解消」である。なぜ人間が痛みシグナルを好むのか、なぜ特定の地域で辛味料理が発達したのか、なぜ伝統医学が唐辛子の薬理作用を認識できたのか—これらの逆説的現象は、生物文化的共進化の枠組みで包括的に説明される。
ただし、科学的厳密性を保つため、以下の点に注意が必要である:
- 気候-辛味相関の再評価: 従来の気候決定論的説明は、近年の系統・地理統計分析により疑問視されている
- 伝統的知識の限界: 伝統医学の知見は貴重だが、現代的な検証と再解釈が必要
- 進化的説明の注意: 適応主義的説明は慎重に評価し、代替仮説も考慮すべき
辛味は、人間の文化的創造性と生物学的適応性の交差点に位置する特権的な研究対象である。それは感覚的体験、社会的実践、生態学的関係、そして医療的知識が一つの複合的現象に統合された例であり、人間と植物の関係の複雑性と深さを示す証拠である。
次章では、この理解を踏まえ、唐辛子研究と応用の未来展望、特に寒冷地栽培の可能性から精密辛味医療まで、革新的アプローチと新たなパラダイムについて考察する。
← [前の記事]
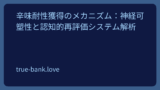
[次の記事] →
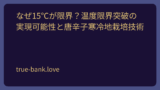
参考文献
考古学・地理学分野
- Kraft, K. H., Brown, C. H., Nabhan, G. P., Luedeling, E., Luna Ruiz, J. D. J., Coppens d’Eeckenbrugge, G., … & Gepts, P. (2014). Multiple lines of evidence for the origin of domesticated chili pepper, Capsicum annuum, in Mexico. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(17), 6165-6170.
- Perry, L., & Flannery, K. V. (2007). Precolumbian use of chili peppers in the Valley of Oaxaca, Mexico. Proceedings of the National Academy of Sciences, 104(29), 11905-11909.
香辛料使用と気候相関
- Billing, J., & Sherman, P. W. (1998). Antimicrobial functions of spices: why some like it hot. The Quarterly Review of Biology, 73(1), 3-49.
- Sherman, P. W., & Billing, J. (1999). Darwinian gastronomy: why we use spices: spices taste good because they are good for us. BioScience, 49(6), 453-463.
- Bromham, L., Skeels, A., Schneemann, H., Dinnage, R., & Hua, X. (2021). There is little evidence that spicy food in hot countries is an adaptation to reducing infection risk. Nature Human Behaviour, 5(7), 878-891.
神経科学・薬理学分野
- Smutzer, G. (2016). Integrating TRPV1 receptor function with capsaicin psychophysics. Advances in Pharmacological and Pharmaceutical Sciences, 2016, 1512457.
- Mou, J., Paillard, F., Turnbull, B., Trudeau, J., Stoker, M., & Katz, N. P. (2013). Efficacy of Qutenza® (capsaicin) 8% patch for neuropathic pain: a meta-analysis of the Qutenza Clinical Trials Database. Pain, 154(9), 1632-1639.
感覚追求と食品嗜好
- Terasaki, M., & Imada, S. (1988). Sensation seeking and food preferences. Personality and Individual Differences, 9(1), 87-93.
- Byrnes, N. K., & Hayes, J. E. (2015). Behavioral measures of risk tasking, sensation seeking, and sensitivity to reward may reflect different motivations for spicy food liking and consumption. Appetite, 103, 411-422.
内因性オピオイド研究
- Yoon, S. S., Kwon, Y. K., Kim, M. R., Shim, I., Kim, K. J., & Lee, Y. S. (2012). Acute effects of capsaicin on proopioimelanocortin mRNA levels in the arcuate nucleus of Sprague-Dawley rats. Psychiatry Investigation, 9(2), 187-190.
抗菌特性研究
- Cichewicz, R. H., & Thorpe, P. A. (1996). The antimicrobial properties of chile peppers (Capsicum species) and their uses in Mayan medicine. Journal of Ethnopharmacology, 52(2), 61-70.
- Liu, Q., Meng, X., Li, Y., Zhao, C. N., Tang, G. Y., & Li, H. B. (2017). Antibacterial and antifungal activities of spices. International Journal of Molecular Sciences, 18(6), 1283.