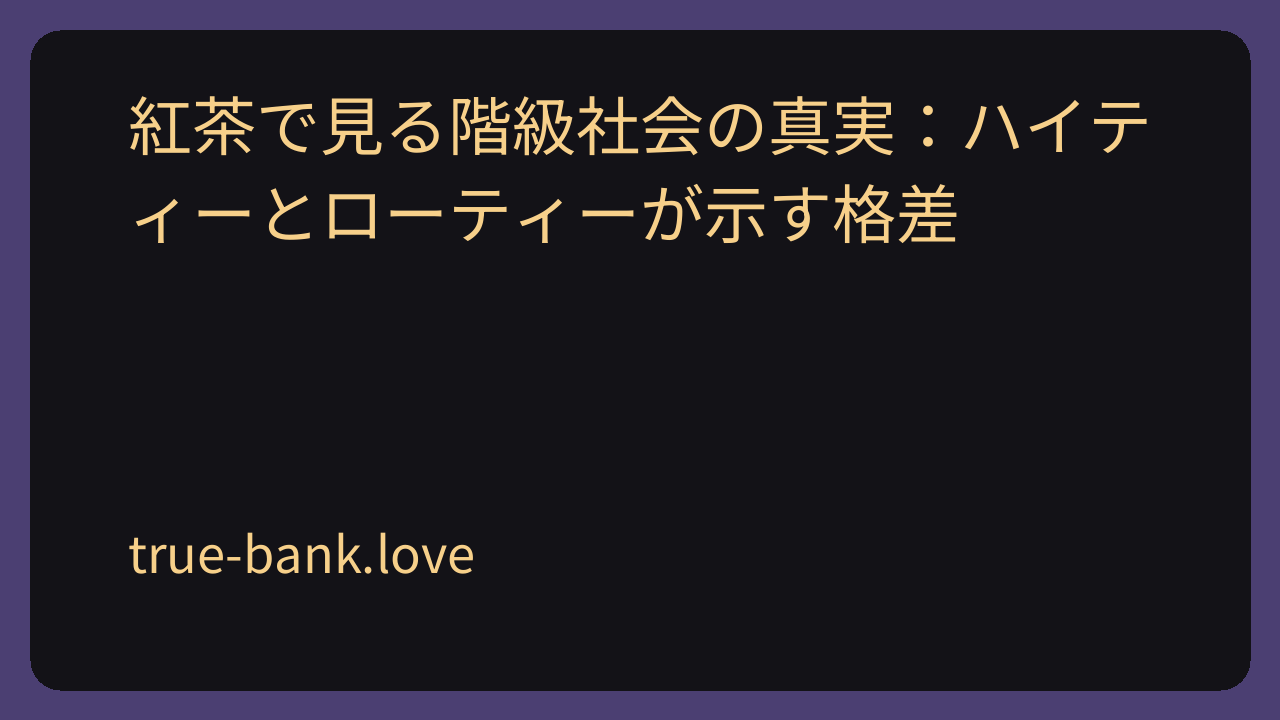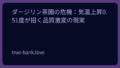紅茶文化の多様性—世界各国の飲用習慣と文化的意義の比較分析
第6部:地域に根差した紅茶文化の形成と社会的機能
飲料としての紅茶は世界中に広がっているが、その飲み方や社会的意味合いは地域によって驚くほど多様である。なぜ同じ植物から作られる飲料がこれほど異なる文化的表現を生み出したのだろうか。本稿では、世界各地の特徴的な紅茶文化を比較分析し、その背後にある歴史的・社会的要因を探る。紅茶が単なる飲料を超えて儀式、社会的交流、アイデンティティ、そして時には政治的表現の媒体となってきた複雑なプロセスを解明することで、グローバル化と文化的固有性の相互作用についての理解を深めたい。
← [前の記事]
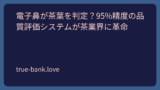
[次の記事] →
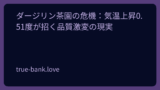
1. イギリスの紅茶文化:階級とアイデンティティの表現
イギリスの紅茶文化は、おそらく世界で最も体系化され儀式化された形態の一つである。Pettigrew(2001)によれば、紅茶はイギリス人のアイデンティティと自己認識の中心的要素となっており、「イギリス的であること」の象徴として機能している。
a) アフタヌーンティーの社会的意義
アフタヌーンティーの起源は、1840年代のアンナ・ベッドフォード公爵夫人に帰されることが多い。当時、夕食は午後8時以降と遅かったため、午後4-5時頃に軽い食事と紅茶を取る習慣が始まったとされる。
この習慣の社会的意義は複合的である。Fromer(2008)が指摘するように、アフタヌーンティーは中流・上流階級の女性たちが社交的交流を行う重要な場を提供した。厳格なヴィクトリア朝の社会規範の中で、紅茶の場は女性が一定の自律性を発揮できる数少ない公的空間であった。
アフタヌーンティーには明確な社会的階層を示す要素も含まれている。Rose(2010)の研究によれば、「ロー・ティー」(軽食を伴う形式)と「ハイ・ティー」(より実質的な夕食に近い形式)の区別は、上流・中流階級と労働者階級の区分を反映していた。使用する茶器の質、紅茶の種類、提供方法なども社会的地位のマーカーとして機能していたことが確認されている。
b) ティータイムの儀式化と作法
イギリスの紅茶文化の特徴的側面は、その高度に儀式化された性質である。正統的なアフタヌーンティーには厳格な作法が含まれていた。紅茶の注ぎ方(ミルクを先に入れるか後に入れるか)、カップの持ち方、適切な会話のトピックと音量、紅茶とケーキやスコーンの適切な食べ方など、細部にわたる規範が存在した。
こうした儀式化は、Hobsbawm & Ranger(1983)が言及する「創られた伝統」の典型例と言える。彼らの分析によれば、こうした伝統は19世紀後半から20世紀初頭にかけて意図的に形式化され、急速な社会変化の中での連続性と安定性の感覚を提供する機能を持っていた。
c) 紅茶と女性解放運動の関係
興味深いことに、紅茶文化とイギリスの女性参政権運動の間には密接な関連性が見られる。Crawford(2017)の研究によれば、19世紀末から20世紀初頭にかけて、ティーハウスは女性参政権活動家の重要な会合場所となった。「Tea and Suffrage」と呼ばれる茶会が資金調達と支持獲得のために組織され、家庭的な「女性の飲み物」というイメージを政治的目的に巧みに利用した。
エメリン・パンクハーストをはじめとする女性参政権運動のリーダーたちは、紅茶会を政治的組織化と意識啓発の場として積極的に活用した。この事例は、一見すると保守的で家庭的な文化的実践が、実際には革新的な社会運動の媒体となりうることを示している。
2. ロシアの茶文化:サモワールと社会性
ロシアの茶文化は、中央アジアを通じて中国から伝わり、18世紀から19世紀にかけて独自の発展を遂げた。その中心的要素は「サモワール」と呼ばれる自立型加熱器と、特徴的な濃い茶の飲み方である。
a) サモワールと家族生活の中心としての茶
サモワールは18世紀にロシアで開発された、石炭や木炭で水を沸かす自立型加熱器である。茶文化専門書によれば、サモワールの導入により、茶が家庭生活の中心的儀式となった。多くのロシアの家庭では、サモワールは居間の中央に置かれ、家族の集まりや社交の象徴となった。
ロシア文学においても、サモワールを囲んだ茶の時間は重要なモチーフとして繰り返し登場する。Smith(2015)によれば、トルストイの『アンナ・カレーニナ』やチェーホフの短編小説では、茶を飲む場面が人間関係の複雑な力学や社会的緊張を表現する装置として機能している。
b) ザヴァールカ方式と紅茶の飲み方
ロシアの伝統的な紅茶の入れ方は「ザヴァールカ」方式と呼ばれる。この方法では、小さなティーポット(チャイニク)で非常に濃い紅茶を作り、それをグラスに少量注いで熱湯で薄めて飲む。
Weinberg & Bealer(2001)によれば、この方法には実用的な側面があった。サモワールの熱湯で少量の濃い茶を何度も薄めることで、一度に茶葉を入れ替えることなく、家族全員が長時間にわたって温かい紅茶を楽しむことができた。寒冷なロシアの気候においては、この方法が特に適していたと考えられる。
ロシアでは紅茶にレモンを加えることが一般的だが、これには歴史的背景がある。19世紀のロシアでは牛乳の保存が難しかったため、レモンが代替として使用されるようになったという説が有力である。また、レモンのビタミンCは寒冷気候での健康維持に役立つという実用的な側面もあった。
c) ソビエト時代の紅茶文化と民族統合
ソビエト連邦時代、紅茶は国家統合の象徴としても機能した。Kologrivova(2019)によれば、1930年代以降、ソビエト政府はグルジア(現ジョージア)などの南部共和国での茶栽培を奨励し、「ソビエトの茶」として全国に供給した。
この政策には経済的自給自足の目的もあったが、同時に文化的統合の側面もあった。紅茶はロシア人、ウクライナ人、中央アジア諸民族など、異なる文化的背景を持つ市民を結びつける共通の日常習慣として促進された。ソビエト時代の公共施設には必ずサモワールが設置され、職場での茶休憩は公式に制度化された。
3. インドのチャイ文化:植民地遺産から国民的飲料へ
インドは世界有数の紅茶生産国であるが、国内での紅茶消費文化は比較的新しく、植民地時代に起源を持つ。現在では「チャイ」(香辛料入りミルクティー)が国民的飲料となっている。
a) 植民地時代の茶消費促進キャンペーン
興味深いことに、紅茶は古代からインドで栽培されていたわけではない。Moxham(2003)によれば、商業的栽培はイギリス東インド会社によって19世紀に導入された。さらに驚くべきことに、インド国内での紅茶消費も当初は限られていた。
この状況を変えたのが、インド茶協会(ITA)による組織的なマーケティングキャンペーンである。Sharma(2011)の研究によれば、1900年代初頭から1930年代にかけて、ITAは鉄道駅での無料サンプル配布、茶屋(Tea Stall)の設置、広告キャンペーンなどを通じて、インド人の間での紅茶消費を積極的に促進した。
このキャンペーンは非常に成功し、紅茶は徐々にインド社会に浸透していった。しかし、インド人は紅茶を単に輸入したわけではなく、ミルクや香辛料を加えた「チャイ」として独自に変容させた。
b) マサラチャイの発展と文化的意義
マサラチャイ(香辛料入りミルクティー)は、現在ではインドを代表する飲料となっている。基本的なレシピは、紅茶をミルク、砂糖、そしてカルダモン、シナモン、クローブ、ジンジャーなどの香辛料と一緒に煮出すというものである。
Sanyal(2020)によれば、マサラチャイの起源には複数の説がある。一つの説によれば、ムガル帝国時代の宮廷で薬用として飲まれていたアーユルヴェーダのスパイス飲料が、後に紅茶と融合したというものである。また別の説では、植民地時代の茶園労働者が限られた茶葉を最大限に活用するために、ミルクとスパイスを加え始めたとされる。
現在、チャイはインド社会のあらゆる階層で消費されている。特に特徴的なのは「チャイワーラー」(茶売り)の存在である。彼らは街角や鉄道駅に小さな屋台を構え、小さな素焼きの使い捨てカップ(クラド)でチャイを提供する。これは、社会階層を超えた交流の場を提供し、インドの公共空間における重要な社会的制度となっている(Lutgendorf, 2012)。
c) 現代インドにおけるチャイの政治経済学
現代インドにおいて、チャイは単なる飲料を超えた政治的・経済的意味合いを持つ。2014年に首相となったナレンドラ・モディは、自身の出自を「チャイワーラー」(茶売り)の息子として強調し、政治的ナラティブの一部とした。彼の「Chai pe Charcha」(茶を飲みながらの会話)キャンペーンは、庶民性を演出するための効果的な政治戦略となった(Bedi, 2016)。
同時に、チャイ文化は新たな経済的展開も見せている。2000年代以降、都市部では「Chai Bar」や「Chaayos」などのチェーン店が登場し、伝統的チャイを現代的にアレンジして提供している。これらの店舗は、グローバル化する中産階級の若者たちに、ノスタルジックでありながらトレンディなチャイ体験を提供している。
4. 中東の紅茶文化:社会的結束と歓待の象徴
中東諸国、特にトルコ、イラン、アラブ諸国では、紅茶が社会的結束と歓待の重要な象徴となっている。これらの地域では、コーヒーの長い歴史があるにもかかわらず、19世紀以降、特に都市部において紅茶が主要な飲料となった。
a) トルコの茶文化とアイデンティティ
トルコは世界で最も紅茶消費量の多い国の一つである。最新の統計によれば、一人当たりの年間消費量は約4.6kgで、これはイギリス(約1.9kg)の2倍以上である。
トルコにおける紅茶の普及は比較的新しい現象である。Hattox(2014)によれば、オスマン帝国時代には主にコーヒーが消費されていたが、第一次世界大戦後のアタテュルクによる共和国樹立と近代化政策の中で、紅茶の国内生産と消費が積極的に促進された。黒海沿岸のリゼ地方が主要な生産地となり、紅茶はトルコ人のアイデンティティの新たな要素として定着していった。
トルコの紅茶は「チャイ」(Çay)と呼ばれ、特徴的な砂時計型のグラス「イヌジェベッリ」で提供される。紅茶は非常に濃く淹れられ、砂糖を加えることが一般的だが、ミルクは加えない。Ger & Belk(1996)によれば、チャイを提供することは「トルコ的歓待」の中心的要素であり、家庭訪問や商談、友人との集まりなど、あらゆる社会的交流の場で欠かせない。
b) イランの茶文化と社会的空間
イランでは紅茶が「チャイ」(چای)と呼ばれ、国民的飲料となっている。Matthee(2005)によれば、イランへの紅茶の導入は19世紀のカジャール朝時代に遡り、ロシアとの貿易関係を通じて広まったとされる。
イランの紅茶は通常、サモワールに似た装置で沸かした湯で淹れられ、小さなグラスで提供される。特徴的なのは、紅茶を砂糖の塊(「ナバート」)や干しフルーツと一緒に飲む習慣である。Fazeli(2018)の民族誌的研究によれば、イランの茶文化は「ターロフ」と呼ばれる社会的礼儀作法と密接に結びついている。客人に茶を提供することは基本的な歓待であり、提供方法や受け取り方にも細かい社会的規範が存在する。
特に注目すべきは「チャイ・ハーネ」(茶館)の社会的機能である。伝統的なチャイ・ハーネは主に男性の社交空間として機能し、政治討論、詩の朗読、伝統音楽の演奏など、公共的言説の場としての役割を果たしてきた。Sreberny-Mohammadi & Mohammadi(1994)によれば、1979年のイラン革命前夜には、チャイ・ハーネが反体制的な政治議論の重要な場となっていた。
c) アラブ世界のシャイと社会的儀式
エジプト、ヨルダン、イラクなどのアラブ諸国では、紅茶は「シャーイ」(شاي)と呼ばれ、社会的結束を強化する重要な飲料となっている。Hussein(2018)の研究によれば、特にエジプトでは紅茶が「国民的な飲み物」と見なされ、日常生活に深く根付いている。
アラブの紅茶は通常、ミントやセージなどのハーブを加えたり、高度に糖分を加えたりする形で飲まれる。エジプトの「シャーイ・コシャリ」(砂糖をたっぷり入れた紅茶)や湾岸諸国の「チャイ・ナーナー」(ミント茶)など、地域による多様性も見られる。
特に興味深いのは、アラブ世界における紅茶と社会的和解のプロセスとの関連である。限定的な観察研究によれば、レバノンなどの紛争経験国では、対立していたコミュニティ間の和解の場で茶を共有することが象徴的な意味を持つ可能性が指摘されている。また、ヨルダンやシリアのベドウィン社会では、テント内で客人に3杯の茶を提供する伝統があり、各杯が象徴的な意味を持つとされる(「1杯目は客として、2杯目は友として、3杯目は家族として」)。
5. 東アジアの発酵茶文化:中国から日本・台湾へ
東アジアでは、中国を起源とする多様な茶文化が発展してきた。特に紅茶(中国語では「紅茶」、日本語でも「紅茶」)については、その受容と変容のプロセスが文化的関係性を反映している。
a) 中国紅茶の歴史と地域的多様性
紅茶は中国で発明されたにもかかわらず、中国国内での消費は緑茶と比較して限定的であった。しかし、キームン(祁門)、正山小種(ラプサンスーチョン)、滇紅(ディアンホン)など、特定地域の紅茶は高い評価を受けている。
Mair & Hoh(2009)によれば、中国国内における紅茶の地位は歴史的に変動してきた。明清時代には主に輸出用として生産されていたが、現代中国では若い世代を中心に国内消費も増加している。特に注目すべきは、近年の「茶芸復興」運動の中で、伝統的な中国紅茶が再評価されていることである。
中国の紅茶文化の特徴は、その地域的多様性にある。例えば、福建省の正山小種は松の木で燻製されるスモーキーな風味が特徴であり、安徽省のキームン紅茶はワインに似た複雑な香りを持つ。これらの地域的特性は、地域の気候、土壌、製法の違いだけでなく、地域固有の文化的実践とも密接に関連していることが報告されている。
b) 日本における紅茶文化の受容と変容
日本では古くから緑茶文化が発達していたが、紅茶は19世紀後半の開国以降に導入され、西洋化・近代化の象徴として受け入れられた。
Ishige(2019)によれば、明治時代(1868-1912)には、紅茶は「文明開化」の象徴として上流階級の間で広まった。大正時代から昭和初期にかけて、カフェや喫茶店文化の発展とともに、紅茶は都市部の中産階級にも普及していった。
特に興味深いのは、戦後日本における紅茶文化の展開である。Ohashi(2010)の研究によれば、1960-70年代の高度経済成長期に、紅茶は「西洋的洗練さ」と「近代的生活様式」の象徴として広く受容された。この時期に「アフタヌーンティー」の日本的解釈が発展し、デパートや高級ホテルでの「女性の社交」の場として定着した。
現代日本の紅茶文化は、伝統的な英国式作法と日本的な美意識が融合した独特のものである。特に「和紅茶」(日本産紅茶)の再評価と、抹茶文化の精神性と紅茶の社交性を融合させた新たな実践が注目される(Surak, 2013)。
c) 台湾の植民地遺産としての紅茶
台湾の紅茶文化は、日本統治時代(1895-1945)に形成された植民地遺産としての側面を持つ。Lee(2020)によれば、日本統治下で台湾の紅茶産業は輸出産業として発展し、特に日月潭(Sun Moon Lake)地域の紅茶は国際的に高い評価を受けた。
台湾の紅茶文化の特徴は、中国、日本、西洋の影響が複合的に作用している点にある。例えば、台湾の伝統的な茶芸(工夫茶)の作法が紅茶にも適用される一方で、日本式や西洋式の紅茶の飲み方も併存している。
特に1980年代以降、台湾では「珍珠奶茶」(タピオカミルクティー)をはじめとする紅茶をベースにした創造的飲料が発展し、これが世界的なブームとなった。この現象は台湾の複合的な文化アイデンティティの表現として分析されている。台湾の伝統的茶文化と西洋からもたらされた紅茶、そして現代的なイノベーションが融合したこの飲料は、台湾の「グローカル」なアイデンティティを体現していると理解される。
6. アフリカとカリブ海地域:ポストコロニアルな紅茶文化
アフリカとカリブ海地域の紅茶文化は、植民地主義の遺産と独立後の文化的再定義の複雑な相互作用を反映している。これらの地域では、紅茶は植民地支配の象徴でありながら、同時に現地化され、独自の文化的意味を獲得してきた。
a) ケニアの紅茶産業と国民的アイデンティティ
ケニアは現在、インドと中国に次ぐ世界第3位の紅茶生産国である。ケニアの紅茶産業はイギリス植民地時代の1924年に始まったが、独立後の1963年以降に急速に発展した。
興味深いことに、ケニアで生産される紅茶の大部分は輸出向けであり、国内消費は比較的限られている。しかし、紅茶は「ケニアの誇り」として国民的アイデンティティの一部となっている。特に、ケニア紅茶開発庁(KTDA)の設立は、小規模農家が紅茶産業に参加する道を開き、経済的エンパワーメントの象徴となった。
ケニアの一般家庭での紅茶の飲み方は「チャイ」と呼ばれ、インドの影響を受けたミルクティーが一般的である。朝食時の「ストロング・チャイ」(濃いミルクティー)は家族の団らんの重要な要素であり、都市と農村の両方で日常的に消費されている。
b) 西アフリカのアティアヤとソーシャルティー
西アフリカ、特にセネガル、マリ、モーリタニアなどでは、「アティアヤ」(または「アタヤ」)と呼ばれる特徴的な紅茶文化が発展している。これはサハラ砂漠を通じた北アフリカとの交易を通じてもたらされたミント茶の伝統である。
Ba(2017)の研究によれば、アティアヤは単なる飲料ではなく、複雑な社会的儀式である。通常、同じ茶葉を3回使って3杯の茶を淹れる過程があり、各杯は異なる濃さと甘さを持ち、異なる意味を持つ(「人生は苦い」「人生は甘い」「人生は優しい」)。
特に若い男性にとって、アティアヤは社会化と情報交換の重要な場を提供している。Heath(2010)は、失業率の高い都市部でのアティアヤ・セッションを「待機の社会性」の表現として分析し、経済的不確実性の中での社会的結束の維持機能を指摘している。
c) カリブ海地域のブッシュティーとクレオール文化
カリブ海地域では、ヨーロッパからもたらされた紅茶文化と、アフリカとインドからもたらされた伝統的なハーブ治療の知識が融合した独自の茶文化が発展した。
Richardson(2018)の研究によれば、ジャマイカの「ブッシュティー」(薬草茶)は、プランテーション時代の奴隷たちが発展させた民間療法に起源を持つ。一方で、イギリス植民地であったカリブ英語圏では、正式な「アフタヌーンティー」の伝統も同時に導入された。
この二重性は、Beushausen(2014)が指摘するように、カリブ海地域のクレオール文化を特徴づける「混成性」(hybridity)の一例である。特にトリニダード・トバゴやバルバドスでは、正統的な「イングリッシュ・ティー」と「ブッシュティー」の両方が、異なる社会的文脈で消費されている。
Higman(2011)は、この二重性を「脱植民地化の日常的実践」として分析している。イギリス式紅茶の形式を維持しながらも、ローカルな材料や飲み方を取り入れることで、植民地時代の文化的遺産を再解釈し、独自のアイデンティティを主張する方法となっているという。
7. モロッコのミントティーと社会的儀礼
モロッコを中心とした北アフリカ地域では、緑茶とミントを組み合わせた「アタイ・ビ・ナナア」(ミントティー)が特徴的な飲料文化として発展している。この文化は単なる飲料の選好を超えて、社会的儀礼、歓待の倫理、そして地域アイデンティティの表現となっている。
a) モロッコのミントティーの起源と発展
モロッコのミントティーは、緑茶(通常は中国産のガンパウダーティー)をミント葉と大量の砂糖で煮出した飲料である。その起源については諸説あるが、Heine(2015)によれば、18世紀後半から19世紀にかけてイギリスの貿易商によって中国茶がモロッコに導入されたのが始まりとされる。
当初は贅沢品であった緑茶は、19世紀を通じて徐々に普及し、現地のミント使用の伝統と融合した。この飲料は「サハラの薬局」とも呼ばれ、消化促進、鎮静、解熱などの薬効も認められていた。現在では、モロッコは緑茶の世界最大の輸入国の一つとなっている。
b) 茶の儀式と社会的重要性
モロッコのミントティーは、その準備と提供に関する精巧な儀式を伴う。Naji(2019)の民族誌的研究によれば、茶の準備は通常、家長または敬意を表すべき客人によって行われる。茶は専用のやかん(ベラッド)で準備され、グラスに注ぐ際には高い位置から注ぐことで泡立て、これが適切な淹れ方とされる。
この茶の儀式は「アタイ」と呼ばれ、モロッコの社会生活において不可欠の要素となっている。家族の集まり、友人との交流、ビジネスミーティング、そして特別な祝祭など、あらゆる社会的機会でミントティーが提供される。特に砂漠地域のベルベル系住民の間では、茶の儀式は「砂漠の魂」の表現とされ、旅人への歓待の象徴となっている。
c) グローバル化と文化的アイデンティティ
現代のグローバル化の文脈において、ミントティーはモロッコの文化的アイデンティティの重要な象徴となっている。Rachik(2018)によれば、モロッコ政府は観光プロモーションにおいてミントティーを「本物のモロッコ体験」の一部として積極的に位置づけている。
しかし同時に、都市部の若い世代を中心に、伝統的なミントティーの消費様式に変化も見られる。カサブランカやラバトの現代的カフェでは、「フュージョン・ミントティー」(ラベンダーやローズなどを加えたバリエーション)や「アイス・ミントティー」など、伝統の現代的再解釈が人気を集めているという報告がある。
この現象は、グローバル化時代における伝統的文化実践の「再発明」の一例と見ることができる。伝統的なミントティーの本質的要素を維持しながらも、現代的な消費傾向や美的感覚に適応させることで、この文化的実践は新たな世代にも継承されている。
8. 結論:紅茶文化の多様性から見るグローバル化と文化的アイデンティティ
世界各地の紅茶文化を比較検討することで、グローバル化と文化的アイデンティティの複雑な相互作用についての洞察が得られる。
a) 紅茶文化にみる「グローカリゼーション」
Robertson(1995)が提唱した「グローカリゼーション」の概念は、紅茶文化の多様な発展を理解する上で特に有用である。茶葉という同一の産物が世界中に広がる過程で、各地域の文化的文脈に応じて異なる意味づけと実践が発展してきた。
イギリスのアフタヌーンティー、ロシアのサモワール、インドのマサラチャイ、モロッコのミントティーなど、これらはすべて紅茶というグローバルな商品の「ローカル化」の例である。しかし同時に、これらのローカルな実践自体が、観光や移民、メディアを通じて再びグローバルに流通する現象も見られる。例えば、インドのマサラチャイがグローバルなカフェチェーンで「チャイラテ」として提供されたり、台湾発のタピオカミルクティーが世界的ブームとなったりする現象はその例である。
b) 紅茶と社会的区分:階級、ジェンダー、民族性
各地の紅茶文化は、社会的区分を表現し、時には強化し、時には挑戦する媒体としても機能してきた。特に注目すべきは以下の側面である:
階級とステータス:イギリスのアフタヌーンティーに見られるように、紅茶の消費方法は社会的地位のマーカーとして機能してきた。同時に、インドの街角のチャイスタンドのように、階級の境界を一時的に緩和する空間を提供することもある。
ジェンダー:紅茶空間はしばしばジェンダー化されている。イギリスやヨーロッパでは紅茶は「女性的」飲料と見なされることが多い一方、中東や北アフリカでは茶の準備と提供は主に男性の役割とされてきた。このジェンダー化された実践は、社会変化とともに再交渉されている。
民族的・国民的アイデンティティ:紅茶は多くの地域で国民的アイデンティティの重要な構成要素となっている。イギリスの「ティータイム」、トルコの「チャイ文化」、ケニアの「紅茶大国」としての自己認識など、飲料の選好は集団アイデンティティの表明となっている。
c) 紅茶文化の未来:伝統の再発明と新たな展開
現代社会における紅茶文化は、伝統の保存と革新の間で絶えず再定義されている。Appadurai(1996)の言葉を借りれば、「伝統」自体が現代的文脈で「再発明」されているのである。
現代の紅茶文化の新たな展開としては、以下が注目される:
健康志向と科学的再評価:紅茶の健康効果に関する科学的研究の増加により、伝統的に「薬」として位置づけられてきた茶の側面が現代的文脈で再評価されている。
第三の波と専門家文化:コーヒーの「第三の波」に類似した現象として、原産地や製法にこだわる「スペシャルティティー」の台頭が見られる。「ティーソムリエ」や「ティーマスター」など、専門知識を持つ文化仲介者の役割も重要性を増している。
デジタル時代の茶文化:ソーシャルメディアを通じた紅茶文化の表現と共有は、新たなグローバルなコミュニティを形成している。「#teatime」や「#teaaddict」のハッシュタグの下で、世界中の紅茶愛好家が経験を共有し、異文化間対話を促進している。
以上の考察から、紅茶文化の多様性は、グローバル化が必ずしも文化的均質化をもたらすわけではないことを明確に示している。むしろ、グローバルな流通と文化的再文脈化の弁証法的プロセスを通じて、新たな文化的形態と実践が絶えず生まれているのである。この意味で、紅茶文化の研究は、グローバル時代における文化的多様性と創造性を理解するための重要な窓を提供しているといえるだろう。
← [前の記事]
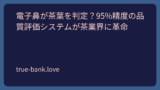
[次の記事] →
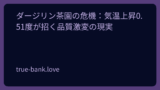
参考文献
Appadurai, A. (1996). Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. University of Minnesota Press.
Ba, M. (2017). Social dynamics of the ataya space: A Senegalese social institution. African Studies Review, 60(2), 123-142.
Bedi, T. (2016). The Dashing Ladies of Shiv Sena: Political Matronage in Urbanizing India. SUNY Press.
Beushausen, J. (2014). Creolizing the Caribbean ‘coolie’: A biopolitical reading of Indian indenture. Critical Asian Studies, 46(4), 591-614.
Crawford, E. (2017). The Women’s Suffrage Movement: A Reference Guide 1866-1928. Routledge.
Fazeli, N. (2018). Tea consumption and social structures in Iran. International Journal of Middle East Studies, 50(3), 535-556.
Fromer, J. E. (2008). A Necessary Luxury: Tea in Victorian England. Ohio University Press.
Ger, G., & Belk, R. W. (1996). Cross-cultural differences in materialism. Journal of Economic Psychology, 17(1), 55-77.
Hattox, R. S. (2014). Coffee and Coffeehouses: The Origins of a Social Beverage in the Medieval Near East. University of Washington Press.
Heath, D. (2010). Purifying faith: The purificationist movement in Senegal. Journal of Religion in Africa, 40(3), 331-353.
Heine, P. (2015). Food Culture in the Near East, Middle East, and North Africa. Greenwood Publishing Group.
Higman, B. W. (2011). A Concise History of the Caribbean. Cambridge University Press.
Hobsbawm, E., & Ranger, T. (Eds.). (1983). The Invention of Tradition. Cambridge University Press.
Hussein, J. (2018). ‘A social institution’: Egyptian experiences of urban tea shops. Urban Anthropology and Studies of Cultural Systems and World Economic Development, 47(3/4), 313-341.
Ishige, N. (2019). The History and Culture of Japanese Food. Routledge.
Kologrivova, E. (2019). Soviet tea culture: Impacts on identity formation. Europe-Asia Studies, 71(7), 1168-1188.
Lee, C. T. (2020). Taiwan’s colonial modernity and the production of native cultural difference. positions: asia critique, 28(3), 501-530.
Lutgendorf, P. (2012). Making tea in India: Chai, capitalism, culture. Thesis Eleven, 113(1), 11-31.
Mair, V. H., & Hoh, E. (2009). The True History of Tea. Thames & Hudson.
Matthee, R. (2005). The Pursuit of Pleasure: Drugs and Stimulants in Iranian History, 1500-1900. Princeton University Press.
Moxham, R. (2003). Tea: Addiction, Exploitation, and Empire. Carroll & Graf Publishers.
Naji, M. (2019). The aesthetics of Moroccan mint tea: Materiality and sensory experience. Journal of Material Culture, 24(4), 419-436.
Ohashi, T. (2010). The transformation of tea culture in modern Japan. Japanese Studies, 30(2), 281-293.
Pettigrew, J. (2001). A Social History of Tea. National Trust.
Rachik, H. (2018). Moroccan Islam? On the religious and cultural identity of Morocco. Journal of North African Studies, 23(3), 375-390.
Richardson, B. (2018). Tea and Empire: James Taylor in Victorian Ceylon. Manchester University Press.
Robertson, R. (1995). Glocalization: Time-space and homogeneity-heterogeneity. In M. Featherstone, S. Lash, & R. Robertson (Eds.), Global Modernities (pp. 25-44). Sage.
Rose, S. (2010). For All the Tea in China: How England Stole the World’s Favorite Drink and Changed History. Viking Books.
Sanyal, P. (2020). The Cultural Politics of Food and Eating in India. Oxford University Press.
Sharma, J. (2011). Empire’s Garden: Assam and the Making of India. Duke University Press.
Smith, A. (2015). Tea and sympathy: Drinking tea in imperial Russia. The Russian Review, 74(1), 1-19.
Sreberny-Mohammadi, A., & Mohammadi, A. (1994). Small Media, Big Revolution: Communication, Culture, and the Iranian Revolution. University of Minnesota Press.
Surak, K. (2013). Making Tea, Making Japan: Cultural Nationalism in Practice. Stanford University Press.
Weinberg, B. A., & Bealer, B. K. (2001). The World of Caffeine: The Science and Culture of the World’s Most Popular Drug. Routledge.