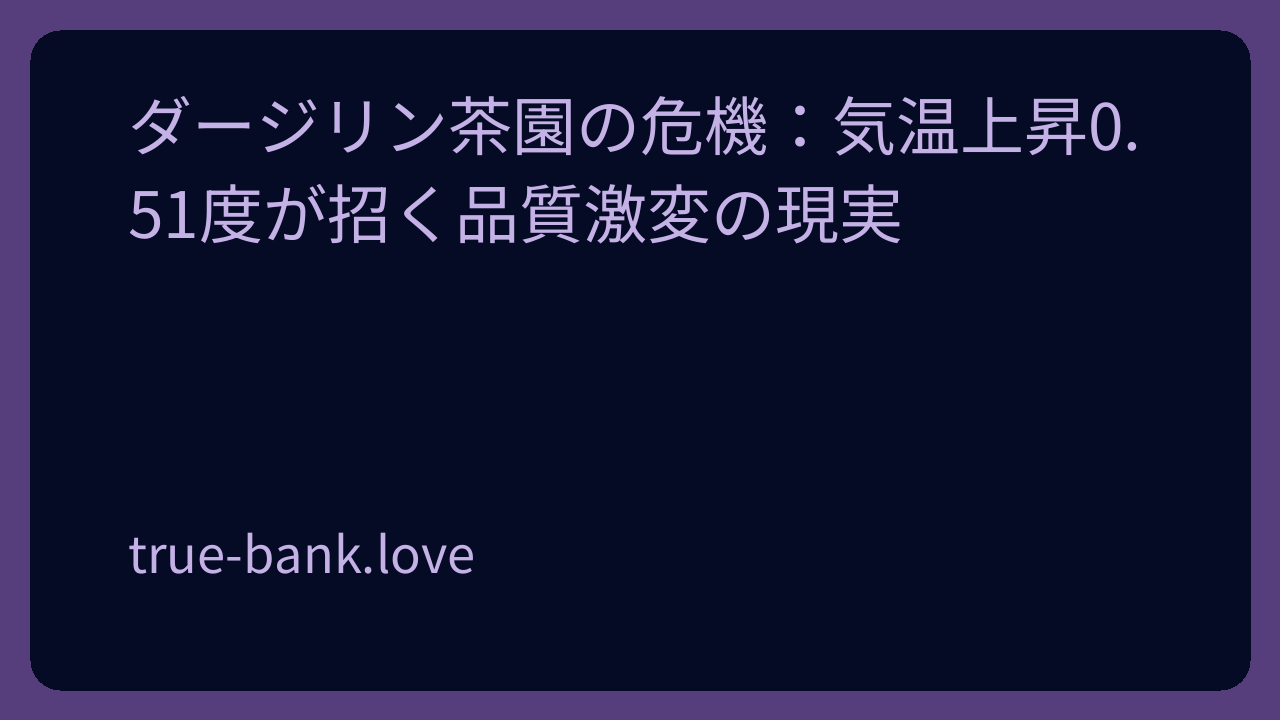紅茶の未来—持続可能性と新たな展開の総合展望
第7部:気候変動時代における紅茶産業の課題と可能性
紅茶は数世紀にわたり世界中で愛飲されてきた飲料だが、その未来は気候変動、市場のグローバル化、消費者嗜好の変化など、様々な課題に直面している。同時に、持続可能な農業技術、デジタル革命、新たな消費形態など、紅茶産業に変革をもたらす革新的な動きも活発化している。本稿では、紅茶の未来を形作る主要な課題と機会を多角的に分析し、この古くからある飲料が21世紀にどのように適応・進化していくのかを展望する。
← [前の記事]
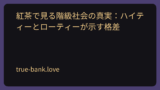
[次の記事] →
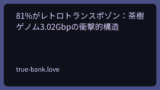
1. 気候変動と紅茶生産の将来
気候変動は、世界の主要な紅茶産地に深刻な影響を及ぼしつつある。気温の上昇、降雨パターンの変化、極端気象の増加などにより、茶樹の生育環境が大きく変化している。
a) 茶樹栽培地域の変動
茶樹(Camellia sinensis)は特定の気候条件下でのみ最適に生育する。Ahmed et al. (2019) の系統的レビューによれば、環境要因が茶の二次代謝物に大きく影響し、気候変動関連の環境変化が茶の品質に複雑な影響を与える可能性が明らかになっている。
特に注目すべきは、標高による栽培適地の移動である。現地の報告によると、インドのダージリン地方では気候変動の影響により、従来の栽培地域での生産が困難になりつつある状況が観察されている。ダージリンでは過去20年間で最高気温が0.51度上昇し、年間降雨量が56mm減少、相対湿度が16.07%低下するなど、茶栽培に適した環境条件が変化している。
一方で、現在は茶樹栽培に適さない地域が新たな生産地として浮上する可能性もある。例えば、日本の北部地域や中国北部では、気温上昇により茶樹栽培の可能性が拡大している。気候変動に伴う「栽培適地のシフト現象」として捉えると、これは産業構造の根本的な再編を意味する重要な変化である。
b) 気候変動の品質への影響
気候変動は茶葉の品質にも複雑な影響を及ぼす。「品質の気候感受性」という視点で分析すると、以下の影響が観察される:
温度と光の条件による品質変化: Wang et al. (2022) の研究では、温度と光の条件により、茶葉の品質関連代謝物が変化することが実証されている。複数の研究により、温度がカテキンの蓄積に重要な影響を与えることが確認されており、特に極端な温度条件がカテキン合成の調節において重要な役割を果たすことが判明している。ただし、その具体的な変化率は茶樹の品種や栽培条件により大きく異なる。
標高による代謝物プロファイルの変化: Kfoury et al. (2018) の研究では、標高の違いによる茶代謝物の顕著な変化が報告されており、高標高地域では特徴的な風味プロファイルが形成されることが明らかになっている。
病害虫の増加: 気温上昇により、特にブリスターブライト病やヘミレヤさび病などの病害の発生範囲が拡大しつつある。これは収量減少だけでなく、防除のための農薬使用増加にもつながる懸念がある。
c) 気候変動への適応戦略
茶産業は気候変動の影響に対応するため、様々な適応戦略を模索している。「レジリエント農業システム」という統合的アプローチの下で、以下のような革新的な取り組みが進められている:
耐性品種の開発: 伝統的な育種法に加え、CRISPR-Cas9などのゲノム編集技術を用いた新品種開発が進行中である。例えば、中国農業科学院茶葉研究所は、より高い温度環境でも安定した収量と品質を維持できる新品種の開発に成功している。
アグロフォレストリーの導入: 茶園に日陰樹を植栽するアグロフォレストリーシステムは、微気候の調整、土壌浸食の防止、生物多様性の向上に寄与し、極端な高温による影響が大幅に軽減されることが研究で確認されている。
精密灌漑技術の革新: 点滴灌漑や土壌水分センサーを活用した精密灌漑システムの導入により、水資源の効率的利用と干ばつ対策が進められている。これらの技術により水使用効率が大幅に向上している事例が報告されている。
地理的リスク分散: 主要茶企業は、気候変動リスクの分散戦略として、複数の地理的地域に生産拠点を展開し始めている。例えば、インドの主要茶企業の中には、アフリカや南米にも茶園を取得する動きが見られる。
2. 持続可能な紅茶生産への取り組み
紅茶産業の持続可能性は、環境的側面だけでなく、社会的・経済的側面も含む複合的な課題である。近年、業界全体でこれらの課題に対応するための取り組みが活発化している。
a) 認証制度の発展と消費者認識
持続可能な紅茶生産を促進する上で、第三者認証システムが重要な役割を果たしている。主要な認証制度としては、フェアトレード、レインフォレスト・アライアンス、UTZ認証、有機認証などがある。
これらの認証制度は以下のような側面で紅茶産業に影響を与えている:
生産者への経済的インセンティブ: 特にフェアトレード認証では、最低価格保証と社会的プレミアムの支払いにより、小規模生産者の経済的安定に寄与している。
環境基準の遵守促進: レインフォレスト・アライアンスやUTZ認証では、農薬使用の削減、森林保全、水資源管理などの環境基準の遵守が求められる。
消費者への情報提供: 認証ラベルは消費者に持続可能性に関する情報を提供し、購買決定に影響を与える。
Bermúdez et al. (2024) の市場分析によれば、持続可能性基準に準拠した茶の割合が着実に増加している。ただし、地域間で認証茶の普及状況には大きな差があり、先進国市場では関心が高い一方、新興市場では普及が限定的な状況が続いている。
b) 労働条件と社会的公正
紅茶産業は歴史的に労働集約的であり、労働条件や社会的公正は重要な課題である。紅茶プランテーションの労働者、特に女性労働者は、低賃金、不安定な雇用、健康リスクなどの問題に直面していることが多い。
これらの課題に対応するため、以下のような取り組みが進められている:
生活賃金イニシアチブ: 最低賃金ではなく、労働者とその家族が尊厳ある生活を送るために必要な「生活賃金」の支払いを促進する取り組み。Ethical Tea Partnership (ETP) などの業界団体が主導している。
女性のエンパワーメント: 紅茶産業では収穫作業者の大部分が女性であるにもかかわらず、管理職や意思決定者としての女性の割合は低いままである。この不均衡を是正するため、Women in Tea Alliance などのイニシアチブが始まっている。
労働者の健康と安全: 農薬曝露のリスク低減、労働環境の改善、医療アクセスの向上などの取り組みが進められている。これらの取り組みが労働者の健康改善と生産性向上の両方に寄与することが研究で示されている。
c) 環境保全と生物多様性
紅茶栽培における環境保全と生物多様性の維持も重要な課題である。従来の単一栽培方式の茶園では、生物多様性の低下、土壌侵食、水質汚染などの環境問題が発生しやすい。
これらの課題に対応するための革新的アプローチとしては:
生物多様性に配慮した茶園管理: 林間茶園や混植システムの導入により、生物多様性の維持と自然の害虫制御機能の向上が図られている。こうした多様性のある茶園システムでは、従来型と比較して昆虫多様性が大幅に向上することが研究で確認されている。
有機肥料と生物的防除の導入: 化学合成農薬や化学肥料の使用を削減し、堆肥や緑肥、天敵昆虫などの生物的手法を活用する取り組みが広がっている。有機栽培に移行した茶園では土壌微生物多様性が大幅に向上することが報告されている。
水資源管理の改善: 雨水収集システム、点滴灌漑、廃水リサイクルなどの技術導入により、水資源の効率的利用と汚染防止が図られている。これらの技術導入により水使用量が大幅に削減された事例が報告されている。
3. 市場動向と消費者嗜好の変化
紅茶市場は消費者嗜好の変化、健康志向の高まり、新興市場の成長などにより、大きな変化を遂げつつある。これらの変化は紅茶産業の未来を形作る重要な要因となっている。
a) スペシャルティーティー市場の成長
コーヒー業界における「スペシャルティコーヒー」の成功に続き、紅茶業界でも「スペシャルティティー」市場が急速に成長している。「茶のテロワール概念」として理解すると、この現象は単なる商品の高付加価値化を超えた、文化的・体験的価値の創出を意味している。
スペシャルティティー市場の特徴としては:
原産地の重視: 特定の茶園や地域の特性を強調した「シングルエステート」「シングルオリジン」茶葉の人気上昇。
限定生産品の価値向上: 特定の季節や収穫期(ファーストフラッシュダージリンなど)に限定された茶葉の希少価値が高まっている。
職人技の再評価: 手摘み茶葉や伝統的製法による茶葉がpremium segmentで高い評価を得ている。
直接取引モデルの拡大: 生産者と小売業者・消費者を直接結びつける「ダイレクトトレード」モデルの普及により、生産者の利益向上と消費者への情報提供が促進されている。
b) 健康志向と機能性紅茶
健康意識の高まりにより、紅茶の健康効果への関心も高まっている。特に、アジア太平洋地域を中心とした文化的伝統に加え、北米・欧州でも健康志向の消費者層を中心に、ウェルネス重視の茶の需要が拡大している。
この傾向を反映した市場展開としては:
機能性強化紅茶: 特定の健康効果を強化した紅茶製品の開発。例えば、プロバイオティクス添加紅茶、抗酸化成分強化紅茶、リラックス効果を強調したL-テアニン強化紅茶などがある。
ウェルネスブレンド: 紅茶にハーブやスパイスを組み合わせた健康志向のブレンド茶の人気上昇。例えば、紅茶にターメリック、ジンジャー、シナモンなどを組み合わせた「イミュニティブレンド」などがある。
デカフェイネーション技術の進化: 健康志向の消費者向けに、より自然な方法でカフェインを低減した紅茶の開発が進んでいる。特に、超臨界CO₂抽出法など、風味を保持しながらカフェインを除去する技術の改良が進んでいる。
c) ミレニアル世代とZ世代の嗜好変化
若い世代の消費者は、紅茶に対して従来とは異なるアプローチを示している。「体験消費パラダイム」という文脈で捉えると、彼らの嗜好は単なる飲料消費を超えた、ライフスタイル表現の手段としての茶文化を求めている。
特徴的な消費パターンとしては:
体験重視の消費: 茶葉の品質だけでなく、提供方法や消費体験の質を重視する傾向。特に「インスタ映え」するプレゼンテーションや独特の飲用体験を求める傾向が強い。
ストーリーテリングへの関心: 茶葉の背景にあるストーリー、生産者の情報、文化的文脈などに強い関心を持つ。
クラフトティーバーの人気: 専門知識を持つバリスタが提供する高級紅茶体験を提供する「ティーバー」の人気上昇。
フュージョン飲料の台頭: 紅茶をベースにした創造的な飲料(チーズティー、バブルティー、ティーカクテルなど)への関心の高まり。
これらの傾向は、伝統的な紅茶ブランドにとって課題であると同時に、革新的な企業にとっては新たな市場機会を提供している。
4. デジタル時代の紅茶産業
デジタル技術の発展は、紅茶のサプライチェーン管理から消費者体験まで、産業全体に変革をもたらしている。
a) ブロックチェーン技術とトレーサビリティ
ブロックチェーン技術の発展により、紅茶のサプライチェーン全体の透明性とトレーサビリティの向上が期待されている。「信頼のデジタル化」という観点から分析すると、この技術は以下のような利点をもたらす:
生産情報の透明性: 栽培方法、収穫日、加工方法などの情報を改ざん不可能な形で記録し、消費者に提供することが可能になる。
品質保証と偽造防止: 高級紅茶の偽造防止や品質証明のためのデジタル認証システムの構築。
公正な価値分配: 生産者から小売業者までの各段階での価格形成の透明化により、より公正な価値分配が可能になる。
実際の応用例としては、一部の先進的な茶企業において、消費者がQRコードをスキャンすることで、購入した紅茶の産地、製造日、品質検査結果などの情報にアクセスできるシステムが導入され始めている。
b) IoTと精密農業
IoT(モノのインターネット)技術の発展により、紅茶栽培における精密農業(Precision Agriculture)の実践が可能になりつつある。「データ駆動型栽培システム」として捉えると、以下のような応用例が見られる:
センサーネットワーク: 茶園に設置された土壌水分センサー、気象センサー、葉面湿度センサーなどからリアルタイムデータを収集し、最適な栽培管理を支援するシステム。
ドローン技術: 多分光カメラを搭載したドローンによる茶園の定期的なモニタリングにより、病害虫の早期発見や栄養状態の評価が可能になっている。
AI予測モデル: 蓄積されたデータと機械学習を組み合わせた収量予測モデルや品質予測モデルの開発。
これらの技術導入により、資源利用効率の向上、労働生産性の向上、品質の安定化などの効果が報告されている。
c) オンライン販売とD2C(Direct to Consumer)モデル
デジタル技術の発展により、紅茶の流通・販売モデルも変化している。特に注目されるのは、生産者から消費者への直接販売(D2C)モデルの台頭である。
「流通革命」という視点で理解すると、2020年以降、オンラインチャネルを通じた紅茶販売は大幅な成長を示しており、特に以下のような特徴が見られる:
サブスクリプションモデル: 定期的に厳選された茶葉を届けるサブスクリプションサービスの人気上昇。
パーソナライゼーション: 消費者の好みや習慣に合わせてカスタマイズされた紅茶ブレンドを提供するサービス。
コミュニティ構築: オンラインコミュニティを通じた茶愛好家同士の交流や情報共有の活性化。
バーチャル茶会: パンデミック期間中に始まり、現在も継続している「バーチャル茶会」や「オンライン茶道体験」などの新しい消費形態。
これらの新しい販売モデルは、特に小規模・専門的な生産者にとって、従来の流通チャネルを迂回して消費者に直接アクセスする機会を提供している。
5. 紅茶関連製品の多様化と革新
紅茶産業の未来は、従来の飲料としての用途を超えた多様な製品開発と用途拡大にも見られる。
a) テア・フード:紅茶の食品応用
紅茶の風味や機能性成分を活用した食品開発が活発化している。「茶の多元的利用」という統合的アプローチにより、以下のような応用例が注目されている:
紅茶ポリフェノールの食品添加物としての利用: 天然酸化防止剤、天然着色料、風味増強剤としての応用。
紅茶発酵技術の応用: コンブチャ(紅茶キノコ)などの発酵飲料の人気上昇。特に2019年以降、プロバイオティクス飲料市場の拡大とともに注目を集めている。
紅茶フレーバーの食品応用: 紅茶フレーバーのアイスクリーム、チョコレート、ベーカリー製品など、紅茶の風味を活かした食品の多様化。
紅茶抽出物の機能性食品素材としての利用: 抗酸化作用、抗菌作用などを活かした機能性食品素材としての応用研究が進んでいる。
これらの応用は、紅茶産業に新たな付加価値創出の機会を提供するとともに、消費者に多様な紅茶体験の選択肢を提供している。
b) 非飲料用途の拡大
紅茶の成分や副産物の非飲料分野への応用も拡大している。「循環型価値創造システム」として理解すると、以下のような新たな応用分野が開発されている:
化粧品・スキンケア製品: 紅茶ポリフェノールの抗酸化作用や抗炎症作用を活かしたスキンケア製品の開発。特に、紅茶カテキンを配合した抗加齢化粧品や日焼け防止製品が注目されている。
医薬品・サプリメント: 紅茶ポリフェノールの抗菌作用、抗ウイルス作用、抗炎症作用を活用した健康補助食品や医薬部外品の開発。
バイオマテリアル: 茶葉の廃棄物からのセルロースナノファイバー抽出や、紅茶タンニンを活用した天然接着剤の開発など、環境配慮型材料への応用研究。
農業用途: 茶葉残渣からの有機肥料生産や、茶ポリフェノールの天然農薬としての応用研究。
これらの非飲料用途の開発は、紅茶産業の副産物や廃棄物の有効活用にもつながり、循環型経済の構築に貢献する可能性を持っている。
c) イノベーティブな紅茶飲料
伝統的な紅茶の飲み方に加え、革新的な紅茶ベースの飲料も急速に発展している。「飲料カテゴリーの境界溶解現象」として捉えると、特に以下のようなカテゴリーが成長している:
クラフトティーカクテル: アルコール飲料と紅茶を組み合わせた創造的なカクテルの開発。特に、ジン、ウォッカ、ラム酒などと紅茶の組み合わせが人気を集めている。
スパークリングティー: 炭酸水と紅茶を組み合わせた低カロリー飲料の開発。特に、砂糖を使用しない自然な甘さを持つ製品が注目されている。
ティーラテの進化: 従来のミルクティーを超えた、植物性ミルク(オーツミルク、アーモンドミルクなど)と紅茶の組み合わせや、風味付けの多様化(スパイス、フルーツフレーバーなど)。
RTD(Ready-to-Drink)紅茶の高級化: 缶やペットボトル入り紅茶の高級化・プレミアム化。特に、有機認証、フェアトレード認証、単一原産地などを前面に出した製品が増加している。
これらの革新的な紅茶飲料は、特に若年層の消費者や健康志向の消費者を中心に新たな需要を創出している。
6. 紅茶産業の社会経済的変革
紅茶産業は、グローバル経済の変化や社会的価値観の変化に応じて、構造的な変革も進行している。
a) 小規模生産者の役割変化とエンパワーメント
伝統的に大規模プランテーションが主導してきた紅茶産業だが、近年は小規模生産者の役割が拡大している。「産業民主化プロセス」として理解すると、以下のような変化が見られる:
小規模生産者協同組合の台頭: 特にインド、ケニア、スリランカなどでは、小規模生産者が協同組合を形成し、加工施設の共同利用や共同マーケティングを行うモデルが発展している。
特産品としての差別化: 小規模生産者が地域特性や伝統的製法を強調した高付加価値製品の開発に成功する事例が増加している。
デジタルプラットフォームの活用: オンラインマーケットプレイスや直接取引プラットフォームを通じて、小規模生産者が国際市場にアクセスする機会が拡大している。
これらの変化は、従来の産業構造を多様化させ、より包摂的な価値創造と分配のモデルを促進する可能性を持っている。
b) 女性のエンパワーメントと社会的包摂
紅茶産業における女性の役割強化と社会的包摂も重要な変化である。「ジェンダー平等の産業実践」という視点から見ると、以下のような取り組みが進んでいる:
女性生産者・経営者の増加: 特に小規模生産者や協同組合の中で、女性リーダーの台頭が見られる。
ジェンダーギャップ解消イニシアチブ: 賃金格差の是正、女性の土地所有権強化、意思決定への参加促進などの取り組み。
教育・トレーニングプログラム: 女性生産者向けの技術トレーニング、経営スキル開発プログラムなどの導入。
これらの取り組みは、紅茶産業の持続可能性向上と共に、農村コミュニティ全体の社会経済的発展にも貢献している。
c) デジタル金融の活用と価値捕捉の再構築
デジタル技術の発展は、紅茶産業の金融モデルにも変革をもたらしている。「金融包摂のデジタル化」として分析すると、以下のような革新が見られる:
モバイルペイメントの普及: 特にアフリカやアジアの茶生産地域では、モバイルマネーの普及により、小規模生産者への直接支払いや迅速な決済が可能になっている。
マイクロファイナンスとデジタル金融の融合: スマートフォンアプリを通じた小規模融資へのアクセス改善により、小規模生産者の設備投資や品質向上投資が促進されている。
クラウドファンディングの活用: 特に小規模生産者や若手起業家によるクラウドファンディングを通じた資金調達の成功事例が増加している。
これらの金融イノベーションは、従来の紅茶産業のバリューチェーンを再構築し、より公平な価値分配モデルを促進する可能性を持っている。
7. 紅茶の文化的価値と未来のアイデンティティ
紅茶は単なる飲料を超えて、文化的アイデンティティや社会的実践の重要な要素となっている。その文化的意義も時代とともに変化している。
a) 伝統の再解釈と現代的表現
伝統的な紅茶文化は、現代的文脈の中で再解釈されつつある。「文化的イノベーション」というレンズを通して観察すると、以下のような現象が見られる:
伝統的茶文化の現代的再解釈: 例えば、イギリスのアフタヌーンティーがラグジュアリーホテルでの特別体験として再定義されたり、日本での「和紅茶」文化の発展など。
デジタル空間における茶文化: SNS上での茶文化コミュニティの形成や、バーチャル茶会など、デジタル空間における新たな紅茶文化の表現。
クロスカルチャーな融合: 異なる茶文化の要素を融合させた新たな実践の出現。例えば、日本の茶道の精神性と西洋の紅茶文化を融合させた新しい茶の作法など。
これらの文化的再解釈は、紅茶の文化的価値を維持しながらも、現代社会の文脈に適応させる創造的プロセスとして理解できる。
b) 世代間の文化伝承と変容
紅茶文化の世代間伝承も重要な課題である。「文化継承のダイナミクス」という観点から分析すると、以下のような傾向が見られる:
若年層の紅茶離れと回帰: 多くの伝統的紅茶消費国では、一時期若年層の紅茶離れが進んだが、近年は健康志向や文化的アイデンティティの再評価により、若年層の紅茶回帰現象が見られる。
教育プログラムと文化伝承: 茶産地や消費地での茶文化教育プログラムの発展。例えば、学校での茶文化教育、茶博物館の設立、茶文化フェスティバルの開催など。
インフルエンサーの役割: SNS上の「ティーインフルエンサー」による新しい紅茶文化の発信と若年層への影響。
これらの取り組みは、伝統的な紅茶文化の価値を次世代に伝えつつも、現代的文脈での再解釈と革新を促進している。
c) グローバルな文化交流の媒体としての紅茶
グローバル化の進展に伴い、紅茶は異文化間の交流と対話の媒体としても機能している。「文化的ブリッジング」という視点で捉えると、以下のような現象が見られる:
国際的な茶文化フェスティバル: 世界各地で開催される茶文化フェスティバルを通じた異文化理解の促進。
ツーリズムとしての茶体験: 茶産地ツアー、茶道体験、茶工場見学など、観光産業における茶文化体験の重要性の増大。
ディアスポラコミュニティの文化的アイデンティティ: 移民コミュニティにおける紅茶習慣の維持と変容、およびホスト社会との文化的交流の媒体としての役割。
これらの現象は、紅茶が単なる飲料を超えて、グローバル化時代における文化的対話と交流の重要な媒体となっていることを示している。
8. 結論:紅茶の未来展望
紅茶産業は、気候変動、持続可能性への要求、デジタル革命、消費者嗜好の変化など、様々な課題と機会に直面している。これらの変化への対応が、紅茶の未来を形作ることになるだろう。
紅茶産業の未来に関する主要な展望としては、以下が挙げられる:
レジリエンスと適応: 気候変動に対応するための栽培地域の多様化、耐性品種の開発、精密農業技術の導入など、環境変化への適応能力の強化が重要となる。
持続可能性と倫理的実践: 環境的持続可能性だけでなく、社会的公正や経済的持続可能性も含めた総合的アプローチの重要性が増している。
デジタル技術の統合: サプライチェーン全体へのデジタル技術の統合により、透明性向上、効率化、価値創造の新たな機会が生まれている。
消費体験の多様化と個人化: 伝統的な紅茶消費に加え、新たな飲み方や用途の開発、パーソナライズされた体験の提供などが重要になっている。
文化的価値の再評価と革新: 伝統的な紅茶文化の価値を維持しつつ、現代的文脈での再解釈と革新を促進する動きが活発化している。
これらの展望は、紅茶産業が直面する課題と機会の複雑な相互作用を反映している。紅茶は単なる飲料を超えて、文化的アイデンティティ、社会的実践、環境的持続可能性、経済的発展など、多面的な価値を持つ複合的な現象として理解する必要がある。
紅茶の未来は、「適応的進化」という統合的概念で理解できる。気候変動や市場変化への適応能力を高めつつ、文化的伝統と革新のバランスを取り、環境的・社会的・経済的持続可能性を実現することが、紅茶産業の長期的繁栄の鍵となるだろう。
← [前の記事]
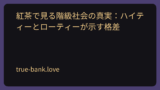
[次の記事] →
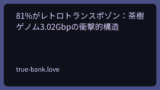
参考文献
Ahmed, S., Griffin, T. S., Kraner, D., Schaffner, M. K., Sharma, D., Hazel, M., Leitch, A. R., Orians, C. M., Han, W., Stepp, J. R., & Robbat, A. (2019). Environmental factors variably impact tea secondary metabolites in the context of climate change. Frontiers in Plant Science, 10, 939.
Ahmed, S., Stepp, J. R., Orians, C., Griffin, T., Matyas, C., Robbat, A., Cash, S., Xue, D., Long, C., Unachukwu, U., Buckley, S., Small, D., & Kennelly, E. (2014). Effects of extreme climate events on tea (Camellia sinensis) functional quality validate indigenous farmer knowledge and sensory preferences in tropical China. PLOS ONE, 9(10), e109126.
Bermúdez, S., Voora, V., Larrea, C., & Luna, E. (2024). Global market report: Tea prices and sustainability. International Institute for Sustainable Development.
Jayasinghe, S., & Kumar, L. (2019). Modeling the climate suitability of tea cultivation in Sri Lanka under climate change scenarios. Agricultural and Forest Meteorology, 272-273, 102-117.
Kfoury, N., Morimoto, J., Kern, A., Scott, E. R., Orians, C. M., Ahmed, S., Griffin, T., Cash, S. B., Stepp, J. R., Xue, D., Long, C., & Robbat, A. (2018). Striking changes in tea metabolites due to elevational effects. Food Chemistry, 264, 334-341.
Wang, M., Yang, J., Li, J., Zhou, X., Xiao, Y., Liao, Y., Tang, N., Deng, W. W., Zhang, L., Peng, Q., Li, Y., Zhang, C., Li, Y., Zi, S., Zhou, J., Wu, L., Wang, P., & Wan, X. (2022). Effects of temperature and light on quality-related metabolites in tea [Camellia sinensis (L.) Kuntze] leaves. Food Research International, 161, 111882.
Wang, X., Zhu, W., Cheng, X., Lu, Z., Liu, X., Wan, X., Zhang, L., Lin, C., & Chen, Z. (2021). The effects of circadian rhythm on catechin accumulation in tea leaves. Beverage Plant Research, 1, 8.