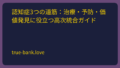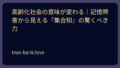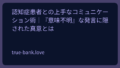第5部:発話生成の複雑性と自動化プロセス:スピーキングの認知科学
「なぜ私は言いたいことがあるのに、それをうまく表現できないのだろう?」この問いは、多くの第二言語学習者が日常的に直面する挑戦である。前章では音声言語の理解(リスニング)における認知的ボトルネックを検討したが、発話生成(スピーキング)はさらに複雑な認知的挑戦をもたらす。それは受容的処理から生産的処理への質的転換を要求するからである。リスニングが「認識」を中心とするならば、スピーキングは「創造」を中心とする。本稿では、発話生成の認知的複雑性と自動化プロセスに焦点を当て、特に流暢なスピーキングを妨げる認知的要因とその克服法を探究する。この理解は、CEFR B2からC1・C2レベルへの移行を目指す学習者のスピーキング能力開発に不可欠な科学的基盤を提供するものである。
I. 発話生成の認知プロセス:理論モデルと第二言語への応用
発話生成はどのような認知プロセスから構成されるのだろうか。この問いに対する最も影響力のある理論的枠組みがLevelt(1989, 1999)の発話生成モデルである。このモデルによれば、発話生成は次の三つの主要段階で構成される:
- 概念化(conceptualization):伝達内容の計画、メッセージの生成
- 形式化(formulation):語彙選択、統語構造構築、音韻符号化
- 調音(articulation):音声波形の発生、物理的発話の実現
これらの処理段階は部分的に並列処理されるが、基本的には階層的な依存関係を持つ。Levelのモデルの特筆すべき特徴は、各処理段階の出力が「内部モニタリングシステム」によって監視され、必要に応じて修正されるという点である。この内部モニタリングは「自己中心的言語理解システム」を通じて行われる。つまり、スピーカーは自身の発話を潜在的に聞き手として処理し、評価するのである。
第二言語(L2)の発話生成は、この基本モデルにどのような修正を必要とするだろうか。Kormos(2006)は、母語(L1)発話生成との主要な相違点として以下を挙げている:
- 概念化段階でのL1概念への依存
- 宣言的知識とプロシージャル知識の並行使用
- 形式的正確さへの注意配分の必要性
- 限定的な運用可能語彙と定型表現の在庫
特に興味深いのは、De Bot(2004)が提案する「二重アクセスモデル」(dual access model)である。このモデルによれば、L2話者の概念化段階はL1と共有されるのに対し、形式化・調音段階は言語特異的に機能する。このような処理構造は、概念形成と言語形式化の間に特有のインターフェース問題を生じさせる。例えば、日本語母語話者が英語で発話する場合、しばしば日本語の概念構造を直接英語形式に変換しようとする「転移」現象が生じる。これは文化特異的概念や構文的非対応箇所で特に顕著である。
Hubert & Bonzo(2019)は、様々な第二言語発話生成モデルを比較検討し、特にこの「概念-形式インターフェース」における処理の非効率性がL2発話生成の主要なボトルネックになると結論づけている。彼らの実験では、L2話者(CEFR B2レベル)が等価の複雑さを持つ表現を生成する際、L1と比較して平均1.8倍の反応時間を要することが示された。さらに注目すべきは、この反応時間差が形式化段階に集中しており、概念化段階での差は比較的小さいという事実である。
Skehan(2014)の「限定的注意容量理論」(Limited Attentional Capacity Theory)によれば、L2話者はリアルタイムの形式化過程において、「内容」(表現したい意味)と「形式」(言語的正確さ)の間で注意資源を競合的に配分する必要がある。このモデルは、後述する「正確さと流暢性のトレードオフ」現象の理論的基盤となる。Skehanのモデルをさらに発展させたはTaguchi(2007)の実験研究である。彼女は、第二言語話者の発話生成において「概念化→形式化→調音」の三段階モデルが明確に観察できることを示しつつも、熟達度が高まるにつれて各処理段階の境界が曖昧になり、並列処理の割合が増加することを実証した。これは、後述する「自動化プロセス」の認知的基盤を示唆するものである。
発話生成モデルの理論研究では、対立する見解も存在する。例えば、MacWhinney(2005)の「競合モデル」(Competition Model)は、Levelのような階層的段階モデルではなく、多層的な「制約の同時的調整」として言語生成を捉える。この視点では、統語、語用、音韻などの各種情報が並列的に活性化し、最終的な発話形式は複数の制約条件の相互作用によって決定される。このモデルの強みは言語間転移現象の自然な説明にあり、例えば日本語母語話者が英語で主語を省略する傾向などを、制約優先順位の転移として説明できる。
第二言語の発話生成における最も困難な側面の一つが「即時性」の要求である。書き言葉と異なり、話し言葉は「オンライン」で生成されなければならない。この即時性要求が、Christiansen & Chater(2016)が「Now-or-Never bottleneck」(今か無かのボトルネック)と呼ぶ時間的制約を生み出す。彼らの計算モデル研究によれば、言語情報は「使うか失うか」の原則に従い、各処理段階での迅速な情報統合が求められる。この「時間的圧力」が、第二言語発話における主要な認知的ボトルネックの一つとなる。
II. 認知的流暢性と発話の流暢性:多層的現象としての流暢さ
「流暢さ」とは何か。この一見単純な問いに対する回答は、意外に複雑である。Segalowitz(2010)の先駆的研究は、「流暢性」の概念を三つの異なる次元で捉えることを提案している:
- 認知的流暢性(cognitive fluency):言語処理の効率性、速度、自動化の程度
- 発話の流暢性(utterance fluency):発話産出の客観的測定可能な特性
- 知覚される流暢性(perceived fluency):聞き手が感じる主観的流暢さ
この区分は、流暢性の本質理解において極めて重要である。特に注目すべきは、「認知的流暢性」が他の二つの基盤となることだ。すなわち、発話者の内的な言語処理の効率性が、観察可能な発話特性や聞き手の印象を根本的に規定するのである。
Segalowitz & Freed(2004)の縦断研究は、この多層的流暢性の相互関係を実証的に検証している。彼らの研究では、大学生の留学前後での発話流暢性変化を測定し、認知流暢性(語彙アクセス速度など)の向上が発話流暢性(発話速度、非流暢性要素の減少など)の予測因子となることを示した。特に興味深いのは、認知流暢性の向上が発話流暢性の向上に先行する傾向があり、両者の間に時間的ラグが存在することである。
発話の流暢性は、どのように客観的に測定できるだろうか。De Jong et al.(2013)は、L2発話の流暢性測定において以下の三つの次元を区別することを提案している:
- スピード流暢性(speed fluency):発話速度、調音速度
- ブレイク流暢性(breakdown fluency):無音ポーズ、充填ポーズ(umやerなど)の頻度と分布
- 修復流暢性(repair fluency):言い直し、修正、繰り返しの頻度
彼らの研究によれば、これらの指標は部分的に独立しており、異なる認知的基盤を持つ可能性がある。特に注目すべきは、ブレイク流暢性(特に句間ポーズの分布)が概念化段階の処理効率性を、修復流暢性が内部モニタリングの機能を反映する傾向があることである。
Götz(2013)の研究は、上級L2話者(CEFR C1レベル)の発話特性を母語話者と詳細に比較している。興味深いことに、上級L2話者の全体的発話速度は母語話者の約80-85%に達するが、ポーズパターンには質的差異が残存する。具体的には、L2話者はクローズクラス語(前置詞、冠詞など)の前でポーズを入れる頻度が有意に高い。この現象は、語彙-統語インターフェースにおける残存する処理負荷を示唆している。
流暢性の発達パターンについては、Towell et al.(1996)の縦断研究が重要な知見を提供している。彼らは、一年間の海外留学前後でのフランス語学習者の発話流暢性変化を詳細に分析し、「平均発話長」(mean length of runs:ポーズ間の音節数)が最も顕著に向上することを発見した。この結果は、流暢性向上が単純な「速く話す」能力ではなく、より大きな処理単位(言語チャンク)を利用できるようになることと密接に関連することを示唆している。
最近の研究では、Préfontaine & Kormos(2016)が発話流暢性の個人差に焦点を当て、学習者の認知スタイルとの関連を探っている。彼らの研究によれば、「場依存型」(field dependent)認知スタイルの学習者はブレイク流暢性(ポーズパターン)に優れる一方、「場独立型」(field independent)学習者はスピード流暢性と修復流暢性に優れる傾向がある。この結果は、流暢性発達の個別化アプローチの必要性を示唆している。
Skehan et al.(2016)は、発話流暢性における「混合効果モデル」(mixed effects model)分析を用いた大規模研究を行い、流暢性発達が線形ではなく「段階的」であることを示した。特に注目すべきは、B1からB2への移行期とB2からC1への移行期に観察される「流暢性の再構築」(fluency restructuring)現象である。これは、言語能力の質的転換点において一時的な流暢性低下が生じることを示唆している。この現象は、次節で検討する「正確さと流暢性のトレードオフ」とも関連する。
発話の流暢性を理解する上で重要なのが、「定型表現」(formulaic expressions)の役割である。Wood(2006, 2010)の一連の研究によれば、熟達したL2話者は発話の約30-40%を定型表現で構成しており、これが流暢性に大きく貢献している。定型表現の使用は「全体的処理」(holistic processing)を可能にし、個別の語彙項目や統語規則の「組み立て処理」よりも認知的効率が高い。特に興味深いのは、Wood(2010)の縦断研究で観察された「定型表現の連鎖」(formulaic sequences)使用率と発話流暢性の相関関係である。
III. 正確さと流暢性のトレードオフ:限られた認知資源の配分
第二言語発話生成における典型的な現象の一つが、「正確さと流暢性のトレードオフ」である。これは、限られた認知資源の中で、言語的正確さ(文法、語彙、発音の正確性)と発話の流暢性(スムーズさ、自然なリズム)の両立が困難であるという現象を指す。この現象は、どのような認知的メカニズムによって生じるのだろうか。
Skehan(1998, 2009)の「タスク難易度理論」(Task Difficulty Theory)は、この現象を説明する主要な理論的枠組みの一つである。彼のモデルによれば、発話者は認知資源を「意味」(meaning)、「形式」(form)、「流暢性」(fluency)の三次元に配分する必要があり、タスクの複雑性や難易度によってこの配分パターンが変化する。特に、「新規性」「抽象性」「複雑性」の高いタスクでは、意味処理により多くの資源が配分されるため、形式的正確さや流暢性に利用できる資源が制限される。
このモデルに対し、Robinson(2003, 2011)の「認知仮説」(Cognition Hypothesis)は異なる視点を提供する。この仮説によれば、タスクの認知的複雑性の増加が必ずしも正確さと流暢性のトレードオフを引き起こすわけではない。彼は、タスク複雑性を「資源指向的」(resource-directing)次元と「資源分散的」(resource-dispersing)次元に区別し、前者は言語形式への注意を促進する一方、後者は注意を分散させると主張する。例えば、「理由説明を求めるタスク」(資源指向的複雑性)は因果関係を表す言語形式への注意を高め、結果として正確さを向上させる可能性がある。
この二つの理論的立場の対立は、Révész(2009)の実証研究によって部分的に検証されている。彼女の研究では、タスクの認知的複雑性と時間的圧力の交互作用が検討され、時間的圧力がない条件では複雑なタスクで正確さが向上する(Robinson仮説を支持)一方、時間的圧力がある条件では複雑なタスクで正確さと流暢性の両方が低下する(Skehan仮説を支持)ことが示された。これは、リアルタイムの処理制約が認知資源配分に決定的影響を与えることを示唆している。
Michel et al.(2007)の研究は、タスクの「対話性」(dialogic vs. monologic)が正確さと流暢性のバランスに与える影響を検証している。彼らの実験では、同一内容について対話形式とモノローグ形式で発話させた場合の違いを分析した。結果として、対話条件では正確さが向上し流暢性が低下する傾向が、モノローグ条件では逆のパターンが観察された。この結果は、対話における相互作用が「形式への注意」を促進することを示唆している。
正確さと流暢性のトレードオフに関して、学習者の熟達度による影響も重要である。Kormos & Dénes(2004)の研究によれば、このトレードオフ効果はCEFR B1-B2レベルで最も顕著であり、C1レベル以上では両者の統合的向上が可能になる傾向がある。これは、高度な熟達度では言語処理の自動化が進み、認知資源の制約が緩和されることを示唆している。
正確さと流暢性のバランスに影響を与える要因として、タスク自体の特性だけでなく、「タスク実施条件」も重要である。Ellis(2005, 2009)の一連の研究によれば、事前計画時間(pre-task planning)の有無が正確さと流暢性のバランスに大きく影響する。具体的には、計画時間があると流暢性と複雑性が向上する一方、正確さの向上は限定的である。これに対し、オンライン計画(online planning: 発話中の思考時間)を促進する条件では、正確さは向上するが流暢性は低下する傾向がある。
正確さと流暢性のトレードオフに関する興味深い事例研究として、Ahmadian(2012)の「繰り返しタスク」実験がある。彼の研究では、同一タスクを4週間にわたり週1回ずつ繰り返し実施した際の発話特性変化を追跡した。初回では流暢性優先、2回目では正確さ向上・流暢性低下、3-4回目では両者の統合的向上というパターンが観察された。この結果は、タスク内容の馴染みが増すことによる認知的負荷の軽減と、それに伴う資源再配分のダイナミクスを示唆している。
正確さと流暢性のバランスを取るための教授法として、Gatbonton & Segalowitz(2005)は「コミュニカティブな自動化」(communicative automatization)アプローチを提案している。このアプローチでは、コミュニケーション活動の中で特定の言語形式を反復使用する機会を設計することで、形式的正確さと会話の流暢性を同時に促進することを目指す。具体的には、情報交換や問題解決などの有意味なタスクの中に、目標言語形式が自然に多数回出現するよう設計するのである。
IV. オンライン処理の複雑性:認知的負荷と発話企画
自発的な会話において、発話者は「何を言うか」と「どのように言うか」を同時に処理しなければならない。この「オンライン処理」(online processing)の複雑性は、第二言語発話の主要な挑戦の一つである。オンライン処理において、どのような認知的負荷が生じ、それはどのように管理されるのだろうか。
Levelt(1989)のモデルをL2発話に適用したJordens(1996)の研究によれば、オンライン処理の主要な挑戦は「時間的圧力」(temporal pressure)にある。自然会話では平均して約500-1000ミリ秒のギャップで話者交代が行われるが、これは完全な発話計画には不十分な時間である。そのため、発話者は「段階的計画」(incremental planning)に依存し、発話の一部を生成しながら次の部分を計画するという並列処理を行う。
この並列処理の効率性は熟達度によって大きく異なる。Kormos(2006)の研究によれば、CEFR B1レベルの学習者は発話単位(clause)ごとに計画する傾向があるのに対し、B2-C1レベルでは複数の発話単位にわたる計画が可能になり、母語話者や上級学習者(C2)では談話レベルの計画が可能になる。この計画範囲の拡大が、発話の構造的一貫性と流暢性に大きく貢献する。
オンライン処理の認知的負荷に関して、Sweller(2011)の認知負荷理論(Cognitive Load Theory)を適用した研究も重要である。Yunusova et al.(2022)は、認知負荷の三要素—内在的負荷(intrinsic load)、外在的負荷(extraneous load)、妥当な負荷(germane load)—がL2発話生成にどのように影響するかを検証している。彼らの実験では、内在的負荷(タスクの本質的複雑性)が高い条件では、特に形式化段階(語彙選択と統語構築)でのエラー率が上昇することが示された。
オンライン発話計画の特性として、Baralt(2015)は「予測的処理」(predictive processing)の役割を強調している。自然会話では、話者は相手の発話や文脈から次に必要となる内容や形式を予測し、発話計画を前倒しで行うことができる。この予測能力は、母語話者では自動的に機能するが、L2話者では制限的である。Baraltの実験によれば、予測可能性の高い対話コンテキストでは、L2話者(CEFR B2レベル)の応答潜時(response latency)が約30%短縮されることが示された。
オンライン処理において特に挑戦的なのが、談話レベルの一貫性維持である。Segalowitz et al.(2016)の研究によれば、B2レベルの学習者は個別の発話単位では適切な生成が可能でも、談話全体の構造維持には困難を示すことが多い。彼らは、この現象を「局所的処理優位性」(local processing dominance)と呼び、認知資源の制約からより大きな談話単位の処理が犠牲になる傾向を指摘している。
Lim & Godfroid(2015)の眼球運動追跡研究は、オンライン発話生成中の注意配分パターンを検証している。彼らの実験では、絵描写タスク中の視線パターンを分析し、熟達度の違いによる注意配分の質的差異を明らかにした。具体的には、中級学習者は個別オブジェクトに注視する「局所的注視」パターンを示すのに対し、上級学習者は場面全体を俯瞰する「全体的注視」パターンを示す傾向があった。この結果は、熟達度による概念化処理の質的差異を示唆している。
オンライン処理の興味深い側面として、Segalowitz & Frenkiel-Fishman(2005)は「切り替えコスト」(switching cost)の影響を検証している。自然会話では、トピック、レジスター、対話者など様々な要素が動的に変化するが、これらの切り替えは認知的コストを伴う。彼らの実験では、言語内切り替え(同一言語内での異なるレジスター間の移行)と言語間切り替え(L1-L2間の移行)のコストを測定し、B2レベルの学習者では言語内切り替えでも有意なコストが生じることを示した。
オンライン発話生成の効率化戦略として、Bygate(2001, 2018)は「言語ルーチン」(language routines)の活用を提案している。言語ルーチンとは、特定の社会的機能を持つ定型的発話パターンであり、これを活用することで認知的負荷を軽減できる。例えば、会話開始、話題転換、意見表明、反論などの機能に対応するルーチン表現を習得することで、これらの談話機能に関連する認知的負荷を軽減し、内容面への注意資源配分を増やすことができる。
オンライン処理の効率化において重要な役割を果たすのが「プロソディ計画」(prosodic planning)である。Koreman et al.(2010)の研究によれば、プロソディ(韻律)は単なる「仕上げ」ではなく、発話計画の中核的要素である。彼らの実験では、韻律的に自然なプロソディを持つ発話は、形態統語的エラーが少なく、より長い発話単位の生成が可能であることが示された。これは、適切なプロソディ計画が統語処理と語彙アクセスを促進する可能性を示唆している。
V. 発話の自動化と手続き化:熟達への認知的道筋
発話の流暢性向上において中心的役割を果たすのが「自動化」(automatization)のプロセスである。第二言語発話における自動化はどのようなメカニズムで進行し、どのような段階を経るのだろうか。
DeKeyser(2007, 2015)の「技能習得理論」(Skill Acquisition Theory)は、言語生成の自動化プロセスを理解する上で重要な理論的枠組みを提供する。この理論によれば、言語技能の発達は以下の三段階を経る:
- 宣言的段階(declarative stage):明示的規則知識の使用、遅い処理、高い注意要求
- 手続き化段階(proceduralization stage):宣言的知識の手続き的知識への変換
- 自動化段階(automatization stage):処理の高速化、低い注意要求、並列処理能力
特に重要なのが、宣言的知識から手続き的知識への移行プロセスである。Loewen(2015)によれば、この移行には「コンパイル」(compilation)と呼ばれる認知的プロセスが関与し、もともと複数の明示的ステップで実行されていた操作が単一の処理単位に統合される。例えば、初級段階では「主語+動詞+目的語」という明示的構造意識に基づいて発話構築をするが、手続き化が進むとこの統語パターンが一つの処理単位として機能するようになる。
DeKeyserのモデルをL2発話に適用した実証研究として、Tavakoli & Hunter(2018)の縦断的観察研究が挙げられる。彼らは16週間にわたる集中英語プログラムに参加する学習者の発話特性変化を追跡し、自動化の進行パターンを分析した。興味深いことに、自動化は言語要素によって異なる速度で進行した。具体的には、高頻度語彙や単純な統語構造の自動化が比較的速く進行する一方、複雑な統語構造や低頻度語彙の自動化はより緩やかに進行した。
自動化の神経生理学的基盤については、Paradis(2009)の「手続き的/宣言的モデル」(procedural/declarative model)が重要な知見を提供している。彼のモデルによれば、宣言的記憶(明示的言語知識)と手続き的記憶(暗示的言語知識)は異なる神経回路に支えられている。具体的には、宣言的記憶は側頭葉内側部と海馬に依存する一方、手続き的記憶は基底核と小脳に依存する。言語の自動化は、処理の主導権が前者から後者へと移行するプロセスとして理解できる。
Ullman(2020)の最新研究は、この二重システムモデルをさらに発展させ、L2習得における両システムの動的相互作用を強調している。彼の「DP-P model」(declarative/procedural-proceduralization model)によれば、L2学習の初期段階では宣言的システムが優位だが、十分な練習を通じて手続き的システムが徐々に活性化される。特に興味深いのは、この移行過程で「競合」(competition)が生じることである。すなわち、ある言語項目の処理において、宣言的システムと手続き的システムが同時に活性化し、処理の主導権を競い合う段階が存在する。この競合段階では、しばしば一時的な処理効率の低下(「U字型発達」)が観察される。
自動化のレベルは、どのように測定できるだろうか。Segalowitz(2010)は、自動化の測定において「処理の可変性」(processing variability)の重要性を強調している。彼の研究によれば、処理時間の絶対値よりも、その変動係数(coefficient of variation: 標準偏差を平均で割った値)が自動化の信頼性の高い指標となる。つまり、反応時間が短いことよりも、反応時間が一貫していることの方が、高度な自動化を示す証拠となるのである。Segalowitz & Husltijn(2005)の実験では、CEFR C1レベルの学習者と母語話者の語彙アクセス時間を比較した結果、平均時間の差(約30%)よりも変動係数の差(約70%)の方が顕著であることが示された。
自動化の過程では、「注意シフト」(attention shift)と呼ばれる現象も重要である。Kormos(2006)の研究によれば、言語処理の自動化が進むにつれて、注意の焦点が「形式」(言語形式の正確さ)から「意味」(伝達内容)へ、さらに「効果」(聞き手への影響)へと移行する傾向がある。これは、言語生成における「自己中心的段階」(egocentric stage)から「聞き手中心的段階」(listener-oriented stage)への発達的移行とも解釈できる。
自動化を促進する要因として、Anderson(2015)は「チャンキング」(chunking)の役割を強調している。チャンキングとは、もともと個別に処理されていた複数の要素が単一の処理単位に統合されるプロセスである。例えば、”I don’t know”という表現が、個別の語彙項目の連なりではなく、[aɪdənoʊ]という一つの音韻的・意味的単位として処理されるようになる現象である。Andersonの「ACT-R」認知アーキテクチャに基づく模擬実験によれば、チャンキングの進行は「べき法則」(power law)に従い、練習の初期段階で急速に進み、その後緩やかになる傾向がある。
自動化を促進する練習法として、Gatbonton & Segalowitz(2005)は「機能に基づく繰り返し」(function-based repetition)アプローチを提案している。このアプローチの特徴は、単純な反復ドリルではなく、同一の言語機能(依頼、提案、反論など)を様々な文脈で繰り返し実行する活動を設計する点にある。これにより、特定の機能に関連する言語形式の「機能的チャンキング」が促進される。例えば、「提案」機能に関連する様々な表現形式(”Why don’t we…”, “How about…”, “We could…” など)を多様な文脈で使用することで、「提案」という機能と表現形式の結びつきが強化される。
自動化に関連する興味深い現象として、Boers et al.(2006)は「偽流暢性」(pseudo-fluency)の問題を指摘している。これは、特定の言語形式や定型表現が表面的には流暢に生成できるものの、その使用文脈や語用論的適切さに問題がある状態を指す。彼らの調査によれば、CEFR B2レベルの学習者の約35%がこの現象を示し、特に慣用表現や談話標識の使用において顕著である。これは、形式的側面の自動化が必ずしも機能的側面の習得を保証しないことを示唆している。
自動化の個人差要因については、Li(2017)の包括的研究が重要な知見を提供している。彼のメタ分析によれば、自動化の進行速度には少なくとも以下の四つの要因が影響する:
- 言語的距離(L1-L2の構造的類似性)
- 言語学習適性(特に音韻的作業記憶容量)
- 練習の量と質(分散練習と集中練習のバランス)
- 明示的知識の質(概念的明確さと構造化の程度)
特に興味深いのは、これらの要因の相対的影響力が学習段階によって変化することである。初期段階では言語的距離と明示的知識の質の影響が大きい一方、中・上級段階では練習の量と質の影響が増大する傾向にある。
VI. 発話能力の段階的向上:教育的応用
ここまでの理論的考察をふまえ、発話能力の段階的向上のための具体的アプローチを検討する。特にB2からC1・C2レベルへの移行を支援するために、どのような指導法や練習法が効果的だろうか。
Nation & Newton(2008)は、発話流暢性向上のためのシステマティックアプローチとして「4/3/2テクニック」を提案している。これは同一内容のスピーチを、最初は4分、次に3分、最後に2分で行うという活動である。時間短縮により、言い直しや修正が減少し、より効率的な発話生成が促進される。さらに、この活動の認知的価値として「反復による処理深化」がある。Arevart & Nation(1991)の実験によれば、この活動後の発話では、語彙密度(内容語の割合)の増加、発話速度の向上(約25%)、非流暢性要素の減少(約40%)が観察された。
Gatbonton & Segalowitz(2005)の「自動化促進タスク」(automatization-promoting tasks)も効果的なアプローチである。この方法は次の三つの原則に基づく:
- 機能的反復(同一言語機能の多様な文脈での使用)
- 心理的真正性(意味のある文脈での言語使用)
- 形式への付随的注意(主な注意は内容にありながら形式への気づきも促進)
彼らの追跡研究によれば、この方法による12週間の訓練後、参加者の発話における非流暢性要素(ポーズ、言い直しなど)が約32%減少し、未練習の新規タスクへの般化効果も観察された。
McCarthy(2010)の「談話マーカー訓練」(discourse marker training)は、特に上級レベルへの移行に効果的なアプローチである。談話マーカー(”you know”, “I mean”, “actually”, “by the way”など)は、単なる「埋め草」ではなく、談話の構造化や対人関係管理において重要な機能を持つ。McCarthy & Carter(2006)の英語母語話者会話コーパス分析によれば、自然会話では平均して約7語に1つの割合で何らかの談話マーカーが使用されている。彼らの教授法研究によれば、コーパスベースの意識高揚活動と模倣練習の組み合わせが、学習者の談話マーカー使用を質的・量的に向上させる効果がある。
より総合的なアプローチとして、Derwing & Rossiter(2003)の「流暢性重視指導」(fluency-focused instruction)が挙げられる。この方法は以下の要素で構成される:
- プロソディ訓練(リズム、イントネーション、強勢の意識的制御)
- 計画ストラテジー(発話計画のための効果的方法)
- コミュニケーション方略(難点を乗り越えるための方略的能力)
- 即興性訓練(予期せぬ状況での発話能力)
彼らの10週間にわたる介入研究では、この方法による訓練を受けた実験群が伝統的文法・語彙中心の指導を受けた統制群と比較して、流暢性測定(発話速度、ポーズ分布、発話長など)で有意に高い向上を示した。特に注目すべきは、この効果が訓練終了3ヶ月後のフォローアップテストでも維持されていたことである。
Rossiter et al.(2010)は、上級レベルへの移行を支援するための「タスク複雑化」(task complexity manipulation)アプローチを提案している。これは、同種のタスクを徐々に複雑化することで、処理能力の段階的拡張を図る方法である。彼らが提案する複雑化の次元には以下がある:
- 認知的複雑性(抽象性、因果関係の複雑さなど)
- 言語的複雑性(必要となる語彙・文法の複雑さ)
- 会話的複雑性(会話管理の複雑さ)
- 状況的複雑性(場面や対人関係の複雑さ)
彼らの漸進的タスク設計に基づく訓練プログラムでは、8週間の介入後、複雑で予測不可能な状況での発話能力(特に対応の柔軟性と適切性)が有意に向上したことが報告されている。
De Jong & Perfetti(2011)の研究は、「スピーキングフルエンシー訓練」(speaking fluency training)の長期的効果を検証している。彼らの設計した訓練法は、以下の三つの要素で構成される:
- 時間的圧力(徐々に短縮される時間制限)
- 内容反復(同一内容の複数回発話)
- 観察と自己評価(録音を用いた振り返り)
彼らの6週間の介入実験では、この訓練を受けた学習者が各セッションでの短期的流暢性向上だけでなく、新しいトピックでの発話においても一般化された流暢性向上を示すことが明らかになった。特に、発話速度だけでなく「平均発話長」(ポーズ間の音節数)の増加が観察され、これは処理単位の拡大を示唆している。
文法的正確性と発話流暢性のバランスを取るアプローチとして、Trofimovich & Gatbonton(2006)は「焦点化された会話練習」(focused conversational practice)を提案している。この方法では、自然なコミュニケーション活動の中に特定の文法構造が高頻度で出現する機会を設計する。例えば、仮定法過去の練習であれば「理想の休暇」についての会話など、目標構造の自然な出現が期待できるトピックを選ぶ。彼らの実験では、この方法による練習が明示的文法指導と自由会話練習の「中間的アプローチ」として、両者の利点を統合できることが示されている。
特にC1・C2レベルを目指す学習者に有効なアプローチとして、McCarthy & O’Keeffe(2004)は「レジスター切り替え訓練」(register switching training)を提案している。これは、同一内容を異なるレジスター(フォーマル・インフォーマル)や異なるジャンル(説明的・説得的・物語的など)で表現する訓練である。彼らのコーパス研究によれば、母語話者と上級学習者の違いとして「レジスター感受性」(register sensitivity)が特に顕著であり、この能力の向上が「母語話者らしさ」に大きく貢献する。
発話能力向上のための自律学習アプローチとして、Wilkinson(2012)は「構造化発話日記」(structured speaking journal)を提案している。これは次の四つのステップで構成される自律的練習法である:
- 短い発話のモノローグ録音(1-2分)
- 書き起こしと自己評価(流暢性、正確性などの観点から)
- 改善点の特定と修正方法の検討
- 修正版の録音と比較
彼の18週間にわたる縦断研究によれば、この方法を定期的(週3-4回)に実践した学習者は、特に「自己修正能力」(self-repair competence)と「メタ言語的気づき」(metalinguistic awareness)の向上を示した。
発話能力向上の「個別化アプローチ」(individualized approach)として、Doughty & Long(2003)の「Focus on Form」(形式への焦点)が注目に値する。このアプローチでは、コミュニケーション活動中に学習者個人の「発達準備状態」(developmental readiness)に合致した言語形式に注意を向けさせる。彼らの主張によれば、特に上級レベルへの移行期においては、一般的なシラバスよりも学習者の「発達ゾーン」(zone of development)に基づく個別化指導が効果的である。
VII. 結論:発話生成の認知的理解と第二言語教育への示唆
本稿では、発話生成の認知的複雑性と自動化プロセスに焦点を当て、特に流暢なスピーキングを妨げる認知的要因とその克服法を探究してきた。Levelの発話生成モデルを出発点に、認知的流暢性と発話の流暢性の関係、正確さと流暢性のトレードオフ現象、オンライン処理の複雑性、そして発話の自動化プロセスについて多角的に検討した。これらの知見からは、第二言語教育、特にCEFR B2レベルからC1・C2レベルへの移行を支援するための重要な示唆が得られる。
発話生成研究からの主要な結論として、以下の点が特に重要である:
- 発話生成は単なる「言語知識の表出」ではなく、複雑な認知処理の連鎖として理解すべきである。特に「概念化」「形式化」「調音」の各段階における処理効率性と自動化度が発話の質を決定づける。
- 「流暢性」は多層的現象であり、認知的流暢性(内的処理の効率性)、発話の流暢性(観察可能な特性)、知覚される流暢性(聞き手の印象)という三つの次元で捉える必要がある。特に上級レベルへの移行においては、単純な「速さ」よりも処理単位の拡大と安定性が重要となる。
- 正確さと流暢性のトレードオフは認知資源の制約に起因するが、タスク設計や実施条件の工夫によって部分的に克服可能である。特に、タスクの認知的複雑性と時間的制約の適切な調整が両者のバランスに重要な役割を果たす。
- 発話の自動化は「宣言的知識→手続き的知識→自動化」という段階を経て進行し、このプロセスは神経生理学的には「宣言的記憶システム→手続き的記憶システム」への移行として理解できる。この移行過程では一時的な能力低下(U字型発達)が生じることがあり、これを教育的に考慮する必要がある。
これらの知見に基づく教育的示唆としては、以下の点が重要である:
- 発話指導は「形式」と「流暢性」を統合したアプローチが効果的である。特に、Gatbonton & Segalowitz(2005)の「コミュニカティブな自動化」や、Nation & Newton(2008)の「4/3/2テクニック」のような、形式的正確性と会話の流暢性を同時に促進する方法が推奨される。
- B2からC1・C2レベルへの移行においては、基本的言語形式の自動化に加え、談話構築能力の強化が重要である。McCarthy(2010)の「談話マーカー訓練」や、McCarthy & O’Keeffe(2004)の「レジスター切り替え訓練」が特に有効と考えられる。
- 発話能力の向上には個別化アプローチが重要である。特に上級レベルでは、学習者の「発達ゾーン」に合致した指導(Doughty & Long, 2003)や、Wilkinson(2012)の「構造化発話日記」のような自律学習支援が効果的である。
- タスク設計においては、複雑性の段階的操作(Rossiter et al., 2010)が重要である。同種のタスクを認知的・言語的・会話的・状況的側面で徐々に複雑化することで、処理能力の段階的拡張を図ることができる。
発話生成研究の今後の課題としては、以下の方向性が特に重要である:
- 個人差要因の解明:学習者の認知スタイル、作業記憶容量、処理速度などの個人特性がどのように発話能力の発達経路に影響するかをより詳細に調査する必要がある。
- テクノロジーの活用:自動音声認識、リアルタイムフィードバック、バーチャルリアリティなどの技術を活用した革新的発話訓練法の開発と検証が期待される。
- 多言語使用の影響:バイリンガルやマルチリンガルのコンテキストにおける発話生成の特性、特に複数言語間の相互作用と干渉の問題をより詳細に理解する必要がある。
- 言語的遠近の影響:学習者の母語と目標言語の言語的距離が発話生成プロセスにどのように影響するかについての比較研究が重要である。
最後に、発話生成の認知科学研究が示唆する最も重要な教育的視点は、「統合的アプローチ」の必要性であろう。発話は単一の技能ではなく、概念形成、言語生成、発声制御などの複合的能力の統合である。したがって、その教育も「形式vs.流暢性」「正確さvs.複雑性」といった二分法を超えた、認知的理解に基づく統合的アプローチによってこそ効果的に行われるのである。
次回の第6部では、多言語話者の脳と言語処理システムに焦点を移し、ポリグロットの脳がどのように複数言語を管理しているのか、また言語間干渉の抑制メカニズムなどについて検討を深める。
参考文献
Ahmadian, M. J. (2012). The effects of guided careful online planning on complexity, accuracy and fluency in intermediate EFL learners’ oral production. Language Teaching Research, 16(1), 129-149.
Anderson, J. R. (2015). Cognitive psychology and its implications (8th ed.). Worth Publishers.
Arevart, S., & Nation, P. (1991). Fluency improvement in a second language. RELC Journal, 22(1), 84-94.
Baralt, M. (2015). Working memory capacity, cognitive complexity and L2 recasts in online language teaching. In Z. Wen, M. B. Mota, & A. McNeill (Eds.), Working memory in second language acquisition and processing (pp. 248-269). Multilingual Matters.
Boers, F., Eyckmans, J., Kappel, J., Stengers, H., & Demecheleer, M. (2006). Formulaic sequences and perceived oral proficiency: Putting a lexical approach to the test. Language Teaching Research, 10(3), 245-261.
Bygate, M. (2001). Effects of task repetition on the structure and control of oral language. In M. Bygate, P. Skehan, & M. Swain (Eds.), Researching pedagogic tasks: Second language learning, teaching and testing (pp. 23-48). Longman.
Bygate, M. (2018). Learning language through task repetition. John Benjamins.
Christiansen, M. H., & Chater, N. (2016). The now-or-never bottleneck: A fundamental constraint on language. Behavioral and Brain Sciences, 39, e62.
De Bot, K. (2004). The multilingual lexicon: Modelling selection and control. International Journal of Multilingualism, 1(1), 17-32.
De Jong, N., & Perfetti, C. A. (2011). Fluency training in the ESL classroom: An experimental study of fluency development and proceduralization. Language Learning, 61(2), 533-568.
De Jong, N. H., Steinel, M. P., Florijn, A., Schoonen, R., & Hulstijn, J. H. (2013). Linguistic skills and speaking fluency in a second language. Applied Psycholinguistics, 34(5), 893-916.
DeKeyser, R. (2007). Skill acquisition theory. In B. VanPatten & J. Williams (Eds.), Theories in second language acquisition: An introduction (pp. 97-113). Lawrence Erlbaum.
DeKeyser, R. (2015). Skill acquisition theory. In B. VanPatten & J. Williams (Eds.), Theories in second language acquisition: An introduction (2nd ed., pp. 94-112). Routledge.
Derwing, T. M., & Rossiter, M. J. (2003). The effects of pronunciation instruction on the accuracy, fluency, and complexity of L2 accented speech. Applied Language Learning, 13(1), 1-17.
Doughty, C. J., & Long, M. H. (2003). Optimal psycholinguistic environments for distance foreign language learning. Language Learning & Technology, 7(3), 50-80.
Ellis, R. (2005). Planning and task-based performance: Theory and research. In R. Ellis (Ed.), Planning and task performance in a second language (pp. 3-34). John Benjamins.
Ellis, R. (2009). The differential effects of three types of task planning on the fluency, complexity, and accuracy in L2 oral production. Applied Linguistics, 30(4), 474-509.
Gatbonton, E., & Segalowitz, N. (2005). Rethinking communicative language teaching: A focus on access to fluency. The Canadian Modern Language Review, 61(3), 325-353.
Götz, S. (2013). Fluency in native and nonnative English speech. John Benjamins.
Hubert, M. D., & Bonzo, J. D. (2019). Theoretical foundations of task-based language teaching. In T. J. Stewart (Ed.), Handbook of research on foreign language education in the digital age (pp. 207-224). IGI Global.
Jordens, P. (1996). Input and instruction in second language acquisition. In P. Jordens & J. Lalleman (Eds.), Investigating second language acquisition (pp. 407-449). Mouton de Gruyter.
Koreman, J., Andreeva, B., & Barry, W. J. (2010). Prosodic characteristics of second language speech rhythm and stress-timing. In A. Botinis (Ed.), Proceedings of the 3rd International Conference on Experimental Linguistics (pp. 81-84). University of Athens.
Kormos, J. (2006). Speech production and second language acquisition. Lawrence Erlbaum.
Kormos, J., & Dénes, M. (2004). Exploring measures and perceptions of fluency in the speech of second language learners. System, 32(2), 145-164.
Levelt, W. J. M. (1989). Speaking: From intention to articulation. MIT Press.
Levelt, W. J. M. (1999). Producing spoken language: A blueprint of the speaker. In C. Brown & P. Hagoort (Eds.), The neurocognition of language (pp. 83-122). Oxford University Press.
Li, S. (2017). Cognitive differences and ISLA. In S. Loewen & M. Sato (Eds.), The Routledge handbook of instructed second language acquisition (pp. 396-417). Routledge.
Lim, H., & Godfroid, A. (2015). Automatization in second language sentence processing: A partial, conceptual replication of Hulstijn, Van Gelderen, and Schoonen’s 2009 study. Applied Psycholinguistics, 36(5), 1247-1282.
Loewen, S. (2015). Introduction to instructed second language acquisition. Routledge.
MacWhinney, B. (2005). A unified model of language acquisition. In J. F. Kroll & A. M. B. de Groot (Eds.), Handbook of bilingualism: Psycholinguistic approaches (pp. 49-67). Oxford University Press.
McCarthy, M. (2010). Spoken fluency revisited. English Profile Journal, 1(1), e4.
McCarthy, M., & Carter, R. (2006). This that and the other: Multi-word clusters in spoken English as visible patterns of interaction. In T. Odlin (Ed.), Perspectives on language and linguistic structure (pp. 91-116). John Benjamins.
McCarthy, M., & O’Keeffe, A. (2004). Research in the teaching of speaking. Annual Review of Applied Linguistics, 24, 26-43.
Michel, M. C., Kuiken, F., & Vedder, I. (2007). The influence of complexity in monologic versus dialogic tasks in Dutch L2. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 45(3), 241-259.
Nation, I. S. P., & Newton, J. (2008). Teaching ESL/EFL listening and speaking. Routledge.
Paradis, M. (2009). Declarative and procedural determinants of second languages. John Benjamins.
Préfontaine, Y., & Kormos, J. (2016). A qualitative analysis of perceptions of fluency in second language French. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 54(2), 151-169.
Révész, A. (2009). Task complexity, focus on form, and second language development. Studies in Second Language Acquisition, 31(3), 437-470.
Robinson, P. (2003). The cognition hypothesis, task design, and adult task-based language learning. Second Language Studies, 21(2), 45-105.
Robinson, P. (2011). Second language task complexity: Researching the cognition hypothesis of language learning and performance. John Benjamins.
Rossiter, M. J., Derwing, T. M., Manimtim, L. G., & Thomson, R. I. (2010). Oral fluency: The neglected component in the communicative language classroom. Canadian Modern Language Review, 66(4), 583-606.
Segalowitz, N. (2010). Cognitive bases of second language fluency. Routledge.
Segalowitz, N., & Freed, B. F. (2004). Context, contact, and cognition in oral fluency acquisition: Learning Spanish in at home and study abroad contexts. Studies in Second Language Acquisition, 26(2), 173-199.
Segalowitz, N., & Frenkiel-Fishman, S. (2005). Attention control and ability level in a complex cognitive skill: Attention shifting and second-language proficiency. Memory & Cognition, 33(4), 644-653.
Segalowitz, N., & Hulstijn, J. (2005). Automaticity in bilingualism and second language learning. In J. F. Kroll & A. M. B. De Groot (Eds.), Handbook of bilingualism: Psycholinguistic approaches (pp. 371-388). Oxford University Press.
Segalowitz, N., French, L., & Guay, J.-D. (2016). What features best characterize adult second language utterance fluency and what do they reveal about fluency gains in short-term immersion? Canadian Journal of Applied Linguistics, 20(1), 90-116.
Skehan, P. (1998). A cognitive approach to language learning. Oxford University Press.
Skehan, P. (2009). Modelling second language performance: Integrating complexity, accuracy, fluency, and lexis. Applied Linguistics, 30(4), 510-532.
Skehan, P. (2014). Limited attentional capacity, second language performance, and task-based pedagogy. In P. Skehan (Ed.), Processing perspectives on task performance (pp. 211-260). John Benjamins.
Skehan, P., Foster, P., & Shum, S. (2016). Ladders and snakes in second language fluency. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 54(2), 97-111.
Sweller, J. (2011). Cognitive load theory. Psychology of Learning and Motivation, 55, 37-76.
Taguchi, N. (2007). Chunk learning and the development of spoken discourse in a Japanese as a foreign language classroom. Language Teaching Research, 11(4), 433-457.
Tavakoli, P., & Hunter, A. M. (2018). Is fluency being ‘neglected’ in the classroom? Teacher understanding of fluency and related classroom practices. Language Teaching Research, 22(3), 330-349.
Towell, R., Hawkins, R., & Bazergui, N. (1996). The development of fluency in advanced learners of French. Applied Linguistics, 17(1), 84-119.
Trofimovich, P., & Gatbonton, E. (2006). Repetition and focus on form in processing L2 Spanish words: Implications for pronunciation instruction. The Modern Language Journal, 90(4), 519-535.
Ullman, M. T. (2020). The declarative/procedural model: A neurobiologically motivated theory of first and second language. In B. VanPatten, G. D. Keating, & S. Wulff (Eds.), Theories in second language acquisition: An introduction (3rd ed., pp. 128-161). Routledge.
Wilkinson, D. (2012). A data-driven approach to increasing student motivation in the language classroom. Language Education in Asia, 3(2), 252-262.
Wood, D. (2006). Uses and functions of formulaic sequences in second language speech: An exploration of the foundations of fluency. Canadian Modern Language Review, 63(1), 13-33.
Wood, D. (2010). Formulaic language and second language speech fluency: Background, evidence and classroom applications. Continuum.
Yunusova, A., Michel, M., & Révész, A. (2022). Investigating the development of L2 cognitive fluency, utterance fluency, and perceived fluency: The effects of L2 proficiency and task repetition. System, 108, 102850.