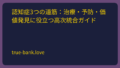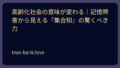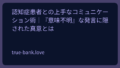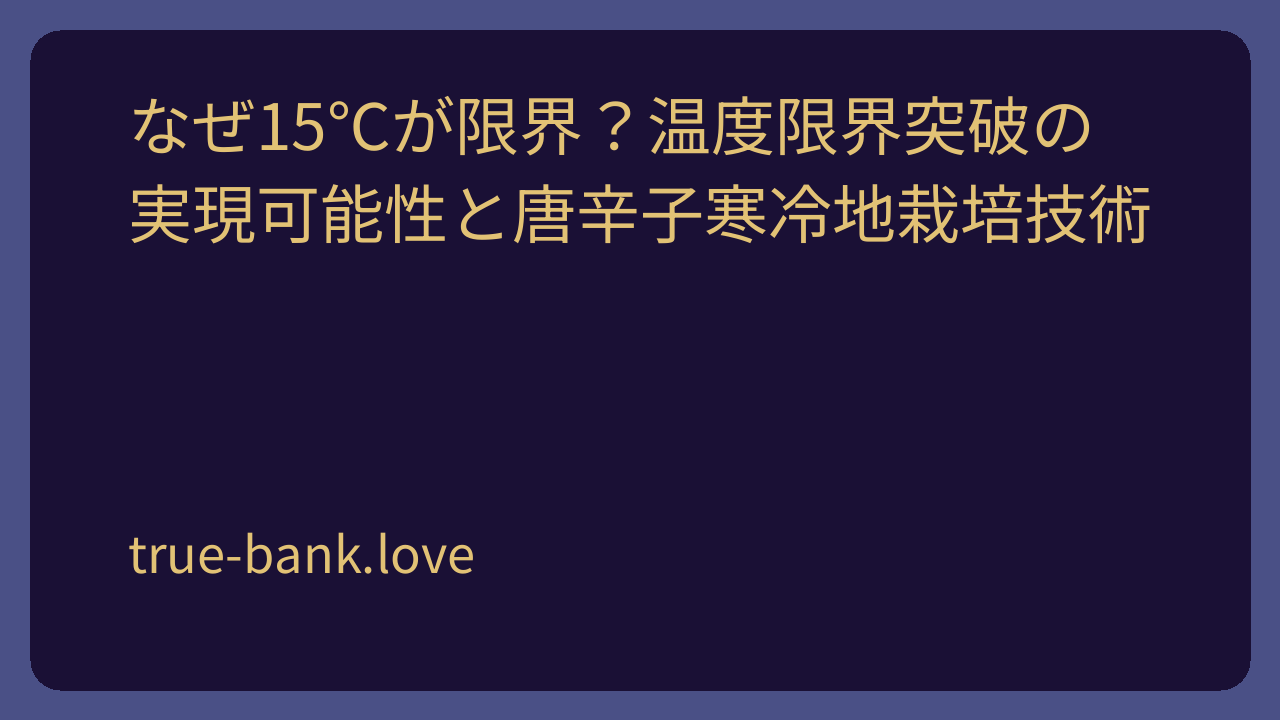第5部:未来展望 – 限界突破と新パラダイム
5.1 寒冷地栽培の可能性:温度限界の分子基盤と打破戦略
唐辛子(Capsicum属)の栽培は現在、その生物学的温度限界によって地理的に制約されている。唐辛子の発芽には最低でも15℃(60°F)の土壌温度が必要とされ、最適成長温度は21-29℃(70-85°F)の範囲である。これが北方地域での商業的栽培を制限する主要因となっている。しかし、この温度限界は固定的なものではなく、その分子基盤を理解し、革新的アプローチを適用することで突破できる可能性がある。
← [前の記事]
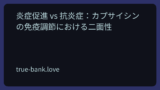
[次の記事] →
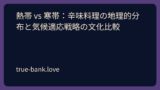
低温限界の分子機構
唐辛子の低温感受性の基盤となる分子機構は複数の要因から構成される:
膜脂質相転移: 約12℃以下では細胞膜脂質が液晶相からゲル相へと転移し、膜流動性が低下。これにより膜タンパク質の機能が阻害され、物質輸送と信号伝達が障害される。
酵素キネティクスの温度依存性: 主要代謝酵素(特に脂肪酸不飽和化酵素、抗酸化酵素など)のキネティクスパラメータが低温で不利になる。
光合成-呼吸バランスの崩壊: 低温では光合成速度が呼吸速度より急速に低下し、負のエネルギー収支が生じる。
水輸送の制限: 根系における水吸収と蒸散のバランスが低温で崩れ、生理的乾燥状態が発生する。
細胞骨格の安定性低下: 低温によるチューブリンとアクチンフィラメントの脱重合が細胞分裂と伸長を阻害する。
これらの制約は相互に関連し、複合的に作用する。唐辛子が進化的に熱帯原産であることから、その代謝システム全体が比較的高い温度範囲で最適化されている。
耐寒性品種開発の現状と戦略
低温耐性を向上させるための現行アプローチには以下がある:
伝統的育種法: 既存の遺伝的多様性からの選抜と交雑。C. annuumの一部系統(特に高地起源のもの)とC. pubescensが比較的高い低温耐性を示し、10℃と15℃の夜間温度条件下での生育比較研究が実施されている。
突然変異育種: エチルメタンスルホン酸(EMS)などの変異原処理による新規変異体の作出と選抜。
遺伝子工学: 低温応答遺伝子(CBF/DREB転写因子など)の過剰発現や、膜改変遺伝子(脂肪酸不飽和化酵素など)の導入。
ゲノム編集: CRISPR-Cas9システムを用いた低温応答経路の精密調整。
これらの方法により、従来の最適温度範囲を下回る条件での生育可能性が実験的に検討されているが、商業的に実用可能な超耐寒性品種の開発は現在も研究段階にある。
打破戦略としての統合的アプローチ
温度限界の実質的な打破には、複数戦略の統合が必要である:
多層的遺伝子改変: 単一遺伝子ではなく、膜安定性、代謝再プログラミング、抗酸化防御、シャペロン機能などに関わる複数の遺伝子群を同時に最適化。
環境-遺伝子相互作用の最適化: 遺伝的改良と栽培環境調整(光質・光量、CO₂濃度、栄養バランスなど)の組み合わせによる相乗効果の追求。
エピジェネティック改変: DNA脱メチル化剤処理などによるエピゲノム修飾を通じた低温応答能の向上可能性。
共生微生物の活用: 耐寒性を促進する根圏・内生微生物との共生関係の最適化。
特に注目すべきは「代謝リプログラミング」アプローチという視点である。これは特定の代謝経路(脂質代謝、炭水化物分配、アミノ酸生合成など)を低温に最適化するよう再設計する方法で、従来の単一遺伝子アプローチより包括的な耐寒性向上が期待できる。
寒冷地栽培の技術的イノベーション
遺伝的アプローチに加え、栽培技術の革新も寒冷地唐辛子生産の可能性を広げる:
マイクロクライメート最適化: 畝立て、被覆資材、風障壁などを用いた局所的環境改善。
地中熱利用システム: 地下水や地熱を利用した根域加温システムによる最低温度保証。
光環境最適化: LED補光による光合成効率向上と日長調整。
栽培系の工学的革新: 半地下栽培、高断熱ハウス、自動環境制御システムの統合。
これらの技術は、遺伝的限界を環境調整によって部分的に補償し、現行品種でも寒冷地での栽培を可能にする。特に北欧や日本では、地熱や工場廃熱を利用した唐辛子栽培システムの実験的導入が始まっている。
革新的視点:状態遷移としての温度応答
ここで、唐辛子の温度限界に関する新しい理解の枠組みとして、「固定的限界」ではなく「状態遷移条件」として捉える視点を提案したい:
二元論的限界からの脱却: 「生育可能/不可能」という二分法的理解から、「異なる生理的状態間の遷移確率」という連続的理解への移行。
確率論的状態空間: 生育温度を、植物が特定の生理的状態(成長状態、維持状態、休眠状態、死滅状態など)に存在する確率を決定するパラメータとして捉える概念。
状態遷移の可塑性: 遺伝的背景、発達段階、栄養状態、前歴などの要因によって、状態遷移の閾値と確率が可塑的に変化するという仮説。
この視点では、「15℃の発芽限界」は絶対的障壁ではなく、「成長状態から維持状態への遷移が急激に生じる温度領域」として再定義される。この再定義は単なる意味論的変更ではなく、限界突破へのアプローチを根本的に変える可能性を持つと考えられる。
5.2 精密辛味医療:遺伝子多型に基づく個別化アプローチ
カプサイシン応答性には顕著な個人差が存在し、この変動の主要な源泉は遺伝的多型である。遺伝子検査技術の進歩と個別化医療の発展により、個人の遺伝的プロファイルに基づいたカプサイシン利用の最適化が現実的可能性となってきた。
カプサイシン応答の遺伝的変異
カプサイシン応答に影響を与える主要な遺伝的多型として、TRPV1遺伝子のI585V(rs8065080)多型が複数の研究で確認されている。しかし、この多型の効果は複雑で、日本人を対象とした研究では、I585Vのホモ接合体(Val-Val型)でカプサイシン感受性が高いことが示された一方、別の研究では、この変異がカプサイシン感受性を低下させるという結果も報告されている。
その他の重要な遺伝的因子:
複数SNPsの統合効果: 健康な被験者におけるカプサイシン咳感受性の研究では、I315M、I585V、T469I、P91Sの4つのSNPsの組み合わせが主要な貢献をすることが示されている。
ナトリウムチャネル遺伝子(SCN9A/10A): これらの変異はカプサイシン誘発痛の強度と持続時間に影響を与える可能性がある。
代謝酵素多型: カプサイシン代謝に関与するCYP450ファミリー酵素の多型が、カプサイシン効果の持続時間と強度を修飾する可能性がある。
内因性オピオイド系遺伝子: OPRM1(μオピオイド受容体遺伝子)の多型が、カプサイシン誘発痛後の内因性鎮痛効果の強度に関連する可能性がある。
これらの遺伝的要因は複合的に作用し、カプサイシンへの応答の「個人的特性」を形成する。特に重要なのは、これらの多型が単一の応答要素ではなく、カプサイシン体験の異なる側面(閾値、強度、質的特性、持続時間、二次的効果など)に選択的に影響することである。
個別化カプサイシン療法の現状
現行の個別化アプローチとその臨床的応用は、まだ研究段階にある:
神経障害性疼痛管理: SDZ-249665のような改良されたカプサイシン類似体は、従来のカプサイシンの刺激作用を軽減しつつ鎮痛効果を維持する可能性を示している。TRPV1およびSCN9A遺伝子型に基づく治療最適化は、将来的な応用可能性として研究されている。
代謝促進介入: アドレナリン受容体(ADRB2/3)とUCP1遺伝子多型に基づく、代謝促進目的のカプサイシン摂取量と頻度の調整は、理論的枠組みとして提案されている。
消化管炎症性疾患: 炎症関連遺伝子(IL-1β、TNF-α、IL-6など)の多型プロファイルに基づく、消化管機能調整のためのカプサイシン用量決定は、予備的研究段階にある。
心血管リスク層別化: 血管収縮・拡張関連遺伝子(ACE、eNOS、ADRA1など)の多型に基づく、循環器系へのカプサイシン効果予測は、将来的研究課題として位置づけられる。
統合的バイオマーカー戦略
遺伝的多型単独ではなく、複数のバイオマーカーを統合したアプローチが最適であると考えられる:
遺伝的マルチマーカーパネル: 単一SNPではなく、関連遺伝子群の多型パターン全体を評価する包括的アプローチ。
エピジェネティックマーカー: DNA修飾やヒストン修飾パターンは、環境要因や前歴の影響を反映する重要な指標として期待される。
メタボロミクスプロファイル: 代謝産物パターンにより、カプサイシン応答性のフェノタイプをより直接的に評価可能と考えられる。
機能的感受性テスト: 局所的少量適用に対する応答を評価し、遺伝的予測を補完・検証する手法。
この多層的バイオマーカー戦略により、単一遺伝子解析よりも高い精度でカプサイシン応答性を予測し、治療戦略を最適化できる可能性がある。
精密辛味設計と次世代治療
遺伝子型に基づいた精密辛味設計の次世代アプローチとして、以下のような方向性が考えられる:
構造最適化カプサイシノイド: 個人の遺伝的背景に合わせた構造修飾カプサイシノイド(特定のTRPV1変異に最適化された類縁体など)の開発。
デリバリーシステム最適化: 吸収・代謝プロファイルに基づいた送達技術(ナノカプセル化、リポソーム封入、経皮送達システムなど)の個別化。
時間-用量プロファイル調整: 遺伝的要因に基づいた薬物動態・薬力学のモデリングによる最適投与スケジュールの設計。
複合処方: 特定の遺伝的背景に対して、カプサイシンと他の活性成分(アロエベラ、メントール、クルクミンなど)の最適組み合わせを設計する試み。
これらの精密アプローチは、カプサイシンの効果を最大化しつつ副作用を最小化する可能性を持つ。特に慢性疼痛や代謝疾患といった、現在の治療法に限界がある領域で大きな貢献が期待される。
革新的視点:シグナル共鳴としての辛味効果
カプサイシン応答の個人差を理解するための概念的枠組みとして、「シグナル共鳴」という視点を提案したい:
共鳴条件としての遺伝子型: 特定の遺伝的背景は、カプサイシンというシグナルと生体系の「共鳴条件」を決定するという仮説。最適な共鳴状態では、小さな入力信号(低用量カプサイシン)が大きな系全体の応答を引き出す可能性がある。
周波数応答特性: 異なる遺伝子型を持つ個人は、カプサイシン刺激に対して異なる「周波数応答特性」を示すという概念。一部の遺伝的背景では単回投与に対する高応答性を示し、他では反復投与への漸進的応答を示すかもしれない。
共鳴閾値の個別化: 各個人は特有の「共鳴閾値」を持ち、これを超えると系の状態が質的に変化する(例:鎮痛効果の発現、代謝活性化など)という仮説的モデル。
この枠組みでは、遺伝子型の役割は単なる「応答強度の修飾」ではなく、「系全体のシグナル処理特性の決定」という、より根本的なものとして捉えられる。これにより、カプサイシン応答の複雑で非線形的な特性をより正確にモデル化し、真に個別化された介入戦略を設計できる可能性がある。
5.3 カプサイシノイド工学:分子設計による新機能創出
カプサイシンの基本構造(ヴァニリルアミド骨格と脂肪酸側鎖)に基づいた化学的修飾により、新しい機能特性を持つ誘導体の設計が可能である。これらの「設計カプサイシノイド」は、特定の臨床的・機能的ニーズに対応した特性プロファイルを持つ可能性がある。
構造-活性相関と修飾戦略
カプサイシン分子の各部位は特定の機能を担っており、vanillyl頭部グループとamide結合部が主要な相互作用部位として機能することが分子レベルの研究で明らかになっている。修飾による効果:
ヴァニリル環修飾: 水酸基とメトキシ基の位置・数の変更により、TRPV1結合特性と活性化パターンを修飾できる。
アミド結合修飾: アミド結合の置換(エステル、ケトン、エーテルなど)により、代謝安定性と受容体選択性が変化する。
脂肪酸鎖修飾: 鎖長、不飽和度、分岐パターンの変更が親油性と組織分布に影響し、C-8からC-10の範囲で最適な辛味活性が得られることが示されている。
極性基導入: 水溶性向上や標的指向性のための極性官能基(ヒドロキシル、カルボキシル、アミノ基など)の導入。
これらの修飾戦略を組み合わせることで、天然カプサイシノイドの限界を超えた特性を持つ化合物の設計が可能になる。
機能特化型カプサイシノイド
目的別に設計された特殊カプサイシノイド誘導体:
鎮痛特化型: SDZ-249665は、初期刺激(灼熱感)を最小化しつつ、長期的脱感作効果を最大化した誘導体として開発され、カプサイシンと同等の鎮痛効果を示しながら刺激作用を大幅に軽減することが動物実験で確認されている。
代謝活性化特化型: TRPV1活性化と同時にAMPKシグナル経路を選択的に増強する誘導体(例:ノナノイルヴァニリルアミド誘導体は抗炎症特性と代謝促進効果を併せ持つことが報告されている)。
抗炎症特化型: NF-κB阻害活性を増強した誘導体の理論的可能性。
組織選択的誘導体: 特定組織(脂肪組織、筋肉など)への選択的送達を可能にする化学的修飾の研究。
これらの設計カプサイシノイドの一部はすでに前臨床研究段階にあり、天然カプサイシンと比較して改善された特性(例:治療域の拡大、副作用の低減)を示している。
投与技術と薬物送達革新
カプサイシノイドの効果を最適化するための送達技術:
時間放出制御: ポリマーマトリクス、リポソーム、マイクロエマルジョンなどを用いた放出動態の精密制御。
標的指向性送達: 特定組織・細胞を標的とするリガンド結合型カプサイシンナノキャリア。
経皮送達最適化: イオン導入法、マイクロニードルアレイ、超音波促進浸透などの先進技術による皮膚透過性向上。
環境応答型放出: pH、温度、酵素活性などの環境因子に応答して活性型カプサイシノイドを放出するプロドラッグシステム。
これらの送達技術は、カプサイシノイドの薬理効果を空間的・時間的に精密制御し、効果-副作用プロファイルを最適化する可能性を持つ。
多機能性ハイブリッド分子
カプサイシン骨格と他の生理活性構造を組み合わせたハイブリッド分子の可能性:
カプサイシン-NSAIDハイブリッド: 抗炎症作用と鎮痛作用を統合した二重機能性化合物の理論的設計。
カプサイシン-抗酸化物質結合体: 代謝促進効果と酸化ストレス保護を組み合わせた複合分子の可能性。
カプサイシン-脂肪酸ハイブリッド: オメガ3脂肪酸などと結合させ、心血管保護と代謝調節を統合する試み。
カプサイシン-ペプチド結合体: 特定受容体を標的とするペプチドと結合させた標的指向性分子の概念。
これらのハイブリッド戦略は、単一分子で複数の治療標的に同時アプローチすることを可能にし、相乗的治療効果と投与の簡略化を実現する可能性がある。
革新的視点:分子対話設計としてのカプサイシノイド工学
カプサイシノイド工学の本質をより深く理解するための概念的枠組みとして、「分子対話設計」という視点を提案したい:
情報伝達分子としてのカプサイシン: カプサイシンを単なる「化合物」ではなく、生体系との「対話」を開始する情報伝達分子として捉える視点。
分子文法の設計: 修飾はランダムではなく、生体系の「解読規則」に基づいた体系的な「分子文法」に従って設計されるという概念。
対話の時間的次元: 分子構造だけでなく、その時間的展開(効果の開始、持続、終結パターン)も設計対象となるという視点。
文脈依存的意味: 同一分子でも、異なる細胞・組織環境(「文脈」)で異なる「意味」(生理的応答)を持つように設計可能という仮説。
この視点は、カプサイシノイド修飾を単なる構造-活性相関の応用を超えた、生体-分子間の「コミュニケーションデザイン」として再概念化する。これにより、より洗練された分子設計戦略と、生体応答の予測モデルの開発が可能になると考えられる。
5.4 システム生物学的視点:統合的理解への道筋
唐辛子研究の将来的発展を考察するにあたり、従来の還元主義的アプローチの限界と、それを補完するシステム生物学的視点について考察したい。
複雑系としての生命システム
現代科学、特に生命科学における還元主義的アプローチの限界として、以下が挙げられる:
線形因果関係の限界: 生命システムは本質的に非線形的かつ複雑であり、単純な因果連鎖モデルでは捉えきれない現象が多数存在する。
静的記述の不十分性: 生命現象は本質的に動的過程であり、静的な「状態」の記述では不十分である場合が多い。
階層間相互作用の複雑性: 分子、細胞、組織、個体など異なる階層間の相互作用は、単一階層の理解を超えた創発的特性を生み出す。
文脈依存性と履歴効果: 同一の刺激が、システムの文脈と履歴によって全く異なる応答を引き起こす現象は、単純モデルでは説明困難である。
これらの限界は、唐辛子の温度限界や薬理効果を完全に理解し操作する上での制約となっている。しかし、これらの限界は科学的挑戦の終着点ではなく、新たなパラダイムの出発点となりうる。
状態遷移モデルの基本概念
「状態遷移パラダイム」という概念的枠組みは、生命システムを固定的構造ではなく動的過程として捉え直す試みである:
状態空間と軌跡: システムは多次元状態空間内の軌跡として理解される。各点は特定の生理的・分子的状態を表すという数理的アプローチ。
確率的遷移: ある状態から別の状態への移行は決定論的ではなく確率的であり、この確率分布が系の根本的特性を定義するという視点。
アトラクターとレジリエンス: 状態空間内には安定領域(アトラクター)が存在し、システムはこれらの領域に引き寄せられる傾向を持つ。レジリエンスはこの引力の強さとして定量化できるという概念。
閾値と分岐点: 特定のパラメータ値において、系の挙動が質的に変化する「分岐点」が存在する。これらの点の同定と操作が介入戦略の鍵となるという仮説。
この枠組みでは、唐辛子の温度限界は「固定的境界」ではなく「状態遷移確率の急激な変化域」として再概念化される。同様に、カプサイシンの薬理効果も「単一経路の活性化」ではなく「システム状態の軌跡修正」として理解される。
創発的制御と介入戦略
状態遷移パラダイムに基づく新たな介入戦略の可能性として、以下が考えられる:
状態遷移確率の操作: 系の基本的状態ではなく、状態間遷移確率を選択的に修飾する介入(例:特定の温度依存性シグナル経路の閾値調整)。
分岐点の同定と標的化: 系の挙動が質的に変化する分岐点を特定し、最小介入で最大効果を得るための戦略。
アトラクター地形の再構成: 系の安定状態パターン全体を再構成することで、根本的な機能変化を誘導する可能性。
ノイズ誘導秩序: 確率的共鳴などの非線形現象を利用し、適切なランダム変動を導入することで秩序ある応答を促進する戦略。
これらのアプローチは、従来の「単一標的・単一効果」パラダイムを超え、複雑系としての生体の特性を活用した介入を可能にする可能性がある。
実証可能性と方法論的課題
この概念的枠組みは思考実験に留まらず、実証可能な予測と介入戦略を提供しうる:
計測技術の革新: 単一細胞レベルでの状態遷移の実時間観察を可能にする高解像度イメージング技術とバイオセンサー開発。
数理モデリングの進化: 非線形動力学、確率過程論、複雑系科学の統合による生体系の数理的記述の精緻化。
シミュレーション能力の向上: 高度な計算モデル化を可能にする技術の発展により、複雑な生体系のシミュレーションが現実的になりつつある。
介入技術の精密化: 光遺伝学、化学遺伝学、ナノ材料工学など、時空間的に精密な介入を可能にする技術の発展。
これらの進歩により、状態遷移パラダイムは単なる概念的枠組みから、検証可能かつ実用的な科学的アプローチへと発展しうる。
唐辛子研究から広がる知的地平
一見すると、唐辛子という特定の植物の研究から、このような大胆な理論的考察が派生することは意外に思えるかもしれない。しかし、特定の具体的システムの深い探究こそが、より普遍的な原理への洞察をもたらすことは、科学史において繰り返し示されてきた。
唐辛子とカプサイシンの研究は、その多層的な複雑性—分子構造から生理効果、生態学的役割から文化的意義まで—により、還元主義的アプローチの限界と、より統合的パラダイムの必要性を特に鮮明に示す。この意味で、唐辛子研究は単なる専門的ニッチではなく、生命現象と人間文化の理解に関する根本的問いへの入り口となりうる。
結論:統合的視野と未来への展望
本シリーズでは、唐辛子とカプサイシンを分子レベルから文明的スケールまで多層的に探究してきた。第1部では分子言語としてのカプサイシノイドの構造と機能を、第2部では生体調節システムとしての辛味の多面的影響を、第3部では神経系との複雑な対話と感覚変換を、第4部では文化と進化の交点としての辛味の位置づけを分析した。そして最終部となる本章では、未来の可能性と限界突破の戦略を考察した。
唐辛子研究の未来は、単なる技術的進歩を超えた概念的革新を必要としている。特に「状態遷移パラダイム」という視点は、温度限界や生理効果に関する従来の理解を拡張し、より統合的かつ動的な生命現象理解への道を開く可能性がある。
同時に、個別化医療アプローチの発展は、カプサイシンの治療的可能性を最大化し、個人の遺伝的背景に基づいた精密な応用を可能にするだろう。また、分子設計と送達技術の革新は、天然カプサイシンの限界を超えた新たな機能特性を持つ化合物の開発を促進するだろう。
最も重要なのは、これらの多様な方向性が分断されたまま発展するのではなく、互いに情報を交換し統合されることである。分子レベルの理解が文化的実践に、臨床的応用が農業技術に、理論的枠組みが実験的デザインに、それぞれ影響を与える相互連結的発展が望ましい。
唐辛子という一見単純な植物の探究は、実は生命と文化の複雑性へのユニークな窓を提供する。痛みと快楽の境界、植物と人間の共進化、分子信号と文化的意味の交差など、唐辛子研究から派生する問いは、科学と人文の境界を越えた知的冒険への誘いである。
この探究を通じて、私たちは単なる科学的知識を超え、人間と自然の関係、感覚と認識の本質、そして科学の可能性と限界についての深い洞察を得ることができる。唐辛子の辛味が複雑な感覚体験を提供するように、唐辛子研究もまた、複雑で刺激的な知的体験を提供するのである。
← [前の記事]
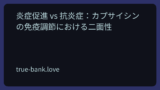
[次の記事] →
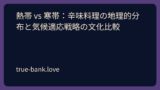
参考文献
Cao, E., Liao, M., Cheng, Y., Julius, D. (2013). TRPV1 structures in distinct conformations reveal activation mechanisms. Nature, 504(7478), 113-118.
Caterina, M.J., Schumacher, M.A., Tominaga, M., Rosen, T.A., Levine, J.D., Julius, D. (1997). The capsaicin receptor: a heat-activated ion channel in the pain pathway. Nature, 389(6653), 816-824.
Hanson, S.M., Newstead, S., Swartz, K.J., Sansom, M.S. (2015). Capsaicin interaction with TRPV1 channels in a lipid bilayer: molecular dynamics simulation. Biophysical Journal, 108(6), 1425-1434.
Kringel, D., Geisslinger, G., Resch, E., Oertel, B.G., Thrun, M.C., Heinemann, S., Lötsch, J. (2018). Machine-learned analysis of the association of next-generation sequencing-based human TRPV1 and TRPA1 genotypes with the sensitivity to heat stimuli and topically applied capsaicin. Pain, 159(7), 1366-1381.
Lee, J.H., Lee, Y., Ryu, H., Kang, D.W., Lee, S.M., Yoo, J., Park, C. (2020). Structural insights into transient receptor potential vanilloid type 1 (TRPV1) from homology modeling, flexible docking, and mutational studies. Journal of Computer-Aided Molecular Design, 34(5), 567-580.
Liviero, F., Campisi, M., Mason, P., Pavanello, S., Scapellato, M.L., Maestrelli, P. (2019). Multiple single nucleotide polymorphisms of the transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1) genes associate with cough sensitivity to capsaicin in healthy subjects. Respiratory Medicine, 154, 7-13.
Okamoto, N., Okumura, M., Tadokoro, O., Sogawa, N., Tomida, M., Kondo, E. (2018). Effect of single-nucleotide polymorphisms in TRPV1 on burning pain and capsaicin sensitivity in Japanese adults. Molecular Pain, 14, 1744806918804439.
Reilly, C.A., Johansen, M.E., Lanza, D.L., Lee, J., Lim, J.O., Yost, G.S. (2005). Calcium-dependent and independent mechanisms of capsaicin receptor (TRPV1) stimulation by 2-aminoethoxydiphenyl borate. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 313(1), 474-484.
Sandoz Pharmaceuticals. (2000). In vivo pharmacology of SDZ 249-665, a novel, non-pungent capsaicin analogue. European Journal of Pharmacology, 408(1), 49-55.
Sun, J., Chen, G., Jing, Y., He, X., Dong, J., Qiao, J., Li, D., Wang, J. (2013). The effect of night low temperature on agronomical traits of thirty-nine pepper accessions (Capsicum annuum L.). Agronomy, 11(10), 1986.
Walpole, C.S., Wrigglesworth, R., Bevan, S., Campbell, E.A., Dray, A., James, I.F., Perkins, M.N., Reid, D.J., Winter, J. (1993). Analogues of capsaicin with agonist activity as novel analgesic agents; structure-activity studies. 1. The aromatic “A-region”. Journal of Medicinal Chemistry, 36(18), 2362-2372.
Yang, F., Xiao, X., Cheng, W., Yang, W., Yu, P., Song, Z., Yarov-Yarovoy, V., Zheng, J. (2015). Structural mechanism underlying capsaicin binding and activation of the TRPV1 ion channel. Nature Chemical Biology, 11(7), 518-524.
Yang, F., Zheng, J. (2017). Understand spiciness: mechanism of TRPV1 channel activation by capsaicin. Protein & Cell, 8(3), 169-177.