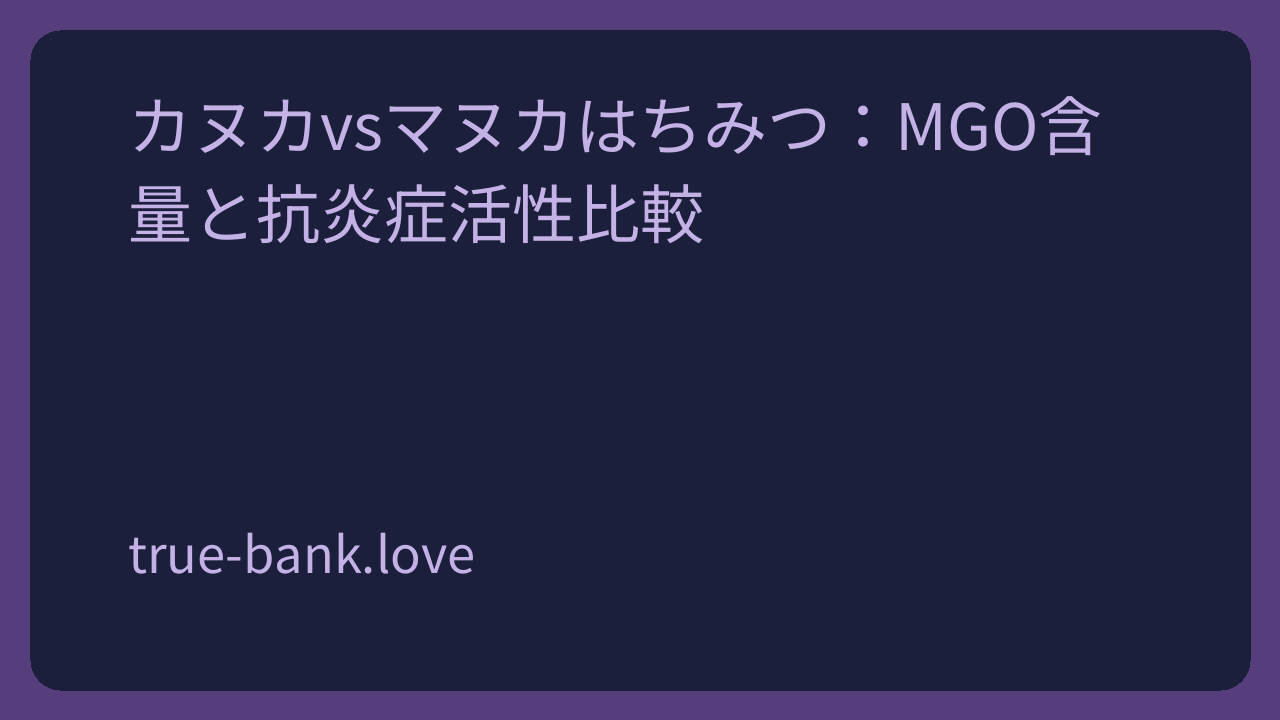第3部:カヌカはちみつ – マヌカの影に隠れた潜在力
序論:影の実力者への科学的視線
マヌカはちみつの国際的名声が高まる一方で、同じニュージーランド原産でありながら、その陰に隠れがちなカヌカはちみつ。両者は長い間混同されてきたが、実は全く異なる植物に由来し、化学組成や生理活性も大きく異なる。カヌカ(Kunzea ericoides、マートル科)は、マヌカ(Leptospermum scoparium)と形態的に類似していることから、「白いマヌカ」とも呼ばれてきたが、1983年の分類学的研究により別属として区分された経緯がある。
現在までの研究により、カヌカはちみつはマヌカほど高濃度のメチルグリオキサール(MGO)は含まないものの、独自のフラボノイド組成と抗酸化特性を持ち、特に炎症性疾患や皮膚病変に対する潜在的な有用性が示唆されている。本稿では、「マヌカの影」から浮かび上がりつつあるカヌカはちみつの科学的特性と医療応用の可能性、そして現状の研究課題に焦点を当てる。
1. カヌカ植物の生物学と生態学:過小評価された森の巨人
カヌカ(Kunzea ericoides)は、マヌカと同じマートル科に属するが、生態学的には大きく異なる特性を持つ。まず、その規模がマヌカ(通常3-4メートル)と比較して著しく大きく、樹高は最大18メートルに達し、寿命もマヌカの20-50年に対して相当に長い。
カヌカの分類学的歴史は複雑である。かつてはLeptospermum ericoidesとして分類されていたが、1983年にJoy Thompsonが形態的・化学的特性の違いに基づきKunzea属として再分類した。さらに、近年の分子系統学的研究により、ニュージーランド国内のカヌカはさらに複数の種に細分化されることが明らかになっている。現在、ニュージーランドにはK. ericoides、K. robusta、K. serotina、K. tenuicaulisなど10種以上のKunzea属植物が認識されている。
生態学的重要性という視点で捉えると、カヌカはニュージーランドの自然遷移において極めて重要な役割を果たしている。森林伐採後や火災後の荒廃地に先駆的に定着し、土壌条件を改善して次世代の森林植物の成長を促進する「看護樹種」としての機能を持つ。窒素固定能力が高く、自然修復生態学の観点からも注目されている。
カヌカの開花期は11月から1月で、マヌカより少し早く咲き始める傾向がある。花は小さく白色で、葉腋に単生または2-3個の集団で咲く。花蜜の分泌量はマヌカより多いとされ、ミツバチだけでなく、トゥイ(Prosthemadera novaeseelandiae)やベルバード(Anthornis melanura)などのニュージーランド固有の鳥類にとっても重要な蜜源となっている。
カヌカの精油は、古くからマオリの伝統医療で呼吸器系の問題や皮膚炎の治療に用いられてきた。その主要成分はα-ピネン、カラメネン、スパチュレノールなどのテルペン類で、抗菌・抗炎症作用を持つことが報告されている。興味深いことに、これらの成分の一部は花蜜にも含まれ、カヌカはちみつの生理活性に寄与していると考えられている。
2. カヌカとマヌカの識別:混同の歴史から科学的区別へ
カヌカとマヌカは外見上の類似性から、長年にわたって養蜂家や分類学者に混同されてきた。両者の確実な識別は、特に植物が開花していない時期には専門家でも困難な場合がある。しかし、科学的理解の進展により、現在では以下のような特徴から区別が可能となっている:
形態学的識別特徴:
- 樹皮の特性:カヌカの樹皮は灰色がかった茶色で縦に剥離する傾向があるのに対し、マヌカの樹皮は暗褐色でより硬く、不規則に剥離する
- 葉の形態:カヌカの葉は柔らかく、平滑で光沢があり、通常長さ6-12mmであるのに対し、マヌカの葉はより硬く、先端が鋭く、長さ7-20mmとやや大きい
- 花の特徴:両者とも白い花を咲かせるが、カヌカの花は雄しべが花弁より短く、花弁の縁がより滑らかであるのに対し、マヌカの花は雄しべが花弁と同程度かそれ以上の長さで、花弁の縁がわずかに波打つ傾向がある
- カプセル果の形状:カヌカの果実は円筒形で先端が平らなのに対し、マヌカの果実はより球形で先端が窪んでいる
化学的識別方法:
はちみつの区別に関しては、植物由来の花粉分析(メリソパリノロジー)が伝統的に用いられてきたが、両者の花粉は形態的に非常に類似しているため、この方法だけでは信頼性が低い。そこで、化学的指標による識別が重要となる。
『化学的識別アプローチとして』、特異的フェノール成分を指標とした識別法が提案されている。特に、3-フェニル乳酸(3-PLA)と4-メトキシフェニル乳酸(4-MPLA)の比率が、カヌカはちみつとマヌカはちみつで有意に異なることが報告されている。
また、最近では機器分析技術の発展により、より精密な識別が可能になっている。ヘッドスペース固相マイクロ抽出法とガスクロマトグラフィー質量分析法(HS-SPME-GC/MS)を用いて、カヌカとマヌカのはちみつの揮発性成分プロファイルを比較し、いくつかの特異的マーカー化合物が同定されている。特に、2-メトキシアセトフェノンがマヌカはちみつの特異的マーカーであるのに対し、アセチルアセトンがカヌカはちみつに特徴的に検出されることが報告されている。
さらに、近年のDNA分析技術の発展により、はちみつ中に含まれる花粉からのDNA抽出と分析が可能になり、カヌカとマヌカの区別がより確実になってきている。これらの科学的手法により、過去の混同を克服し、両者の特性を正確に評価する基盤が整いつつある。
3. カヌカはちみつの化学的特性:独自の成分プロファイル
カヌカはちみつの化学的特性は、マヌカはちみつとは明確に異なる。まず、基本的な物理化学的性質を見てみよう。カヌカはちみつは淡い琥珀色から中程度の琥珀色で、クリーミーな結晶化傾向を示し、マヌカより結晶粒が小さい。pH値は3.9-4.3程度で、マヌカのpH(3.5-4.0)よりもわずかに高い傾向がある。
糖組成に関しては、カヌカはちみつはフルクトース含有量(約38-40%)がマヌカ(約36-38%)よりやや高い傾向があり、これが結晶化特性の違いに影響していると考えられる。
しかし、最も注目すべきは生理活性成分の違いである。『化学組成の特異性という観点から理解すると』、カヌカはちみつとマヌカはちみつの主要なフェノール化合物のプロファイルには、以下のような特徴的な違いがある:
フラバノン誘導体:
カヌカはちみつはピノセンブリン、ピノバンクシンなどのフラバノン誘導体の含有量がマヌカよりも高い。特にピノセンブリンは強力な抗酸化作用と抗炎症作用を持つことが知られている。
メチルグリオキサール(MGO)含有量:
カヌカはちみつのMGO含有量は通常100 mg/kg以下であり、マヌカはちみつ(最高1500 mg/kg以上)と比較して著しく低い。これは、カヌカ花蜜中のジヒドロキシアセトン(DHA)含有量がマヌカより低いことに起因する。
トリケトン類:
マヌカが主にβ-トリケトン類(特にグランジフロロン)を含むのに対し、カヌカはα-トリケトン類の含有量が高い。これらのトリケトン類は、それぞれ異なる生理活性を示す。
芳香族カルボン酸:
カヌカはちみつでは没食子酸、プロトカテク酸、クロロゲン酸などのフェノール酸含有量がマヌカよりも高い傾向がある。
これらの成分プロファイルの違いは、カヌカはちみつがマヌカとは異なる生理活性を持つ可能性を示唆している。特に注目すべきは、総フェノール含量とそれに関連する抗酸化活性である。『抗酸化能力の比較という視点では』、カヌカはちみつの総フェノール含量がマヌカはちみつと同等かそれ以上である可能性が報告されている。
また、揮発性成分に関しても興味深い違いが見られる。カヌカはちみつの香気成分には、マヌカにはほとんど見られないリナロール、α-テルピネオール、1,8-シネオールなどのテルペンアルコールが特徴的に含まれる。これらの成分は、カヌカはちみつの官能特性(より柔らかく複雑な香り)に寄与しているだけでなく、抗微生物活性や抗炎症活性にも関与している可能性がある。
4. 官能特性と風味プロファイル:繊細さの科学
カヌカはちみつの官能特性は、マヌカとは明確に異なる独自のプロファイルを持つ。専門のはちみつ審査員による評価では、カヌカはちみつは以下のような特徴を示す:
視覚的特性:
カヌカはちみつは淡い琥珀色から中程度の琥珀色で、マヌカ(中〜濃い琥珀色)よりも明るい色調を示す。結晶化すると細かいクリーミーな結晶となり、マヌカよりも滑らかな質感を持つ。
香り:
カヌカはちみつの香りは繊細で複雑であり、軽いハーブ調の香りにわずかなスパイシーさと木質感が調和している。これに対し、マヌカはちみつはより強い薬草様の香りと独特の「湿った土」のような香気を持つ。
味わい:
カヌカはちみつは、カラメルのような甘さの中に微かなシトラス調の酸味とミネラル感が特徴的である。後味は比較的クリーンで持続時間が短い。一方、マヌカはちみつはより強い風味と長く持続する後味を持ち、時にわずかな苦味を伴う。
テクスチャー:
カヌカはちみつはマヌカよりも粘度がやや低く、口当たりが軽い傾向がある。結晶化した場合の粒子感もより細かく滑らかである。
『風味特性の科学的基盤として』、これらの官能特性の違いが化学的成分と関連づけられている。特に、カヌカはちみつに特徴的なフェノール化合物(特にピノセンブリンとピノバンクシン)とテルペンアルコール(リナロール、α-テルピネオール)が、その繊細な風味プロファイルに寄与していると考えられている。
風味の科学的評価方法としては、ガスクロマトグラフィー嗅ぎポート検出器(GC-O)が用いられ、香気活性値(Odor Activity Value, OAV)の測定により、個々の揮発性成分の風味への寄与度が評価されている。この分析により、カヌカはちみつの特徴的香気には、フェニルアセトアルデヒド(花のような香り)、リナロール(柑橘系の香り)、ノナナール(柑橘系・緑の香り)などが主要な寄与をしていることが明らかになっている。
官能評価の専門家は、カヌカはちみつの風味特性をしばしば「より洗練された」「より複雑な」と表現し、特に料理やドリンクのペアリングにおいては、マヌカより汎用性が高いとの評価もある。こうした繊細な風味特性が、カヌカはちみつの潜在的な付加価値となり得る可能性を示している。
5. 生物活性と潜在的医療応用:異なる作用機序
カヌカはちみつの生物活性は、マヌカと比較して異なるメカニズムによるものと考えられている。その主な特性と潜在的医療応用について検討してみよう。
5.1 抗菌活性:マヌカとは異なる機序
カヌカはちみつの抗菌活性は、マヌカほど強力ではないものの、決して無視できるものではない。初期の研究では、カヌカはちみつの非過酸化水素活性(フェノール当量)は平均で13.6%(マヌカの15.5%と比較)であった。その後の研究では、カヌカはちみつのMGO含有量が通常100 mg/kg以下であることが確認され、マヌカ特有の強力なMGO依存性抗菌活性は期待できないことが明らかになった。
しかし、『異なる抗菌メカニズムという視点で理解すると』、カヌカはちみつが異なるメカニズムで抗菌作用を示す可能性が示唆されている。カヌカはちみつに含まれるフラバノン誘導体(特にピノセンブリン)が細菌の細胞膜透過性を変化させ、他の抗菌成分の作用を増強する可能性が示されている。
特に注目すべきは、カヌカはちみつが示す選択的抗菌活性のメカニズムである。Lu et al. (2013)の研究では、カヌカはちみつが異なる細菌種に対して異なる増殖抑制パターンを示すことが報告されている。この効果は、カヌカはちみつに特異的に含まれる特定のフラボノイド類(特にピノセンブリン)が、細菌の細胞膜透過性や代謝酵素活性に影響を与えることに関連している可能性がある。
5.2 抗炎症作用:カヌカはちみつの強み
カヌカはちみつの最も注目すべき特性の一つは、その抗炎症作用である。研究により、カヌカはちみつがマクロファージ細胞における炎症性サイトカイン(IL-1β、TNF-α)の産生を有意に抑制することが示されている。この効果は、MGO含有量の低いカヌカはちみつでも観察されたことから、異なるメカニズムによるものと考えられる。
『抗炎症メカニズムの解析から』、カヌカはちみつ抽出物がCOX-2(シクロオキシゲナーゼ-2)酵素の活性を阻害することが示されている。COX-2は炎症反応における重要な酵素であり、その阻害はアスピリンなどの非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)と同様の効果をもたらす可能性がある。
これらの抗炎症作用のメカニズムとして、カヌカはちみつに含まれるピノセンブリン、ピノバンクシン、クリソン、ガランギンなどのフラボノイドが、NF-κBシグナル伝達経路を阻害することが示唆されている。NF-κBは炎症関連遺伝子の発現を制御する転写因子であり、その阻害は広範な抗炎症効果をもたらす。
5.3 抗酸化作用と組織保護
カヌカはちみつの抗酸化活性も注目に値する。研究では、カヌカはちみつの総フェノール含量と抗酸化活性(ORAC値)がマヌカと同等かそれ以上であることが示されている。
特に興味深いのは、動物実験による結果である。カヌカはちみつの摂取がラットの肝臓における抗酸化酵素(スーパーオキシドディスムターゼ、カタラーゼ、グルタチオンペルオキシダーゼ)の活性を有意に増加させることが示されている。これは、カヌカはちみつが生体内の抗酸化防御システムを強化する能力を持つことを示唆している。
これらの抗酸化効果が、カヌカはちみつに含まれる特定のフラボノイド(特にピノセンブリンとピノバンクシン)の直接的なラジカル捕捉作用と、Nrf2転写因子の活性化を介した内因性抗酸化システムの増強の両方によるものであると提案されている。
5.4 皮膚疾患への応用可能性
カヌカはちみつの抗炎症作用と抗酸化作用は、特に皮膚疾患治療への応用可能性を示唆している。カヌカはちみつ抽出物がアトピー性皮膚炎モデルマウスにおいて、症状スコアの改善と皮膚の炎症性サイトカインレベルの低下をもたらすことが示されている。
また、カヌカはちみつによる創傷治癒促進効果が報告されている。この効果は、直接的な抗菌作用よりも、線維芽細胞の増殖促進、血管新生の促進、そして炎症の緩和によるものと考えられている。
さらに、『皮膚マイクロバイオーム調整という新しい視点では』、カヌカはちみつが皮膚微生物バランスを調整する能力を持つことが示されている。特に注目すべきは、病原性細菌(黄色ブドウ球菌など)を抑制しつつ、有益な共生細菌(コリネバクテリウム属など)への影響が比較的少ないという選択性である。これは、皮膚のマイクロバイオーム調整を目的とした製品開発への応用可能性を示唆している。
6. 研究と開発の現状:未開拓の可能性
カヌカはちみつの研究と商業的開発は、マヌカと比較してまだ初期段階にある。しかし、その潜在的な価値が徐々に認識されつつあり、ここ数年で研究が活発化している。
6.1 学術研究の動向
カヌカはちみつの学術研究は、主にニュージーランドとオーストラリアの研究機関によって牽引されている。カヌカはちみつの特性解明に関する初期の研究以降、以下のような研究動向が見られる:
生理活性成分の同定と定量化:
カヌカはちみつの特徴的なフラボノイド成分が同定され、その含有量が定量化されている。これらの研究により、カヌカはちみつの化学的指紋が明確になりつつある。
機能性評価:
カヌカはちみつの抗炎症作用、抗酸化作用、創傷治癒促進効果などの機能性が評価されている。これらの研究により、カヌカはちみつの潜在的な医療応用の基盤が形成されている。
作用メカニズムの解明:
最近の研究では、分子レベルでの作用メカニズム解明に焦点が当てられている。カヌカはちみつが皮膚マイクロバイオームに与える影響を研究し、その選択的抗菌作用のメカニズムが探究されている。
臨床応用の可能性探索:
予備的臨床研究では、喘息患者におけるカヌカはちみつ吸入療法の安全性と忍容性が評価されている。結果は有望であったが、効果の確認にはより大規模な臨床試験が必要とされている。
6.2 商業的開発と市場動向
商業的側面では、カヌカはちみつは長らくマヌカはちみつの「不純物」または「混合物」として扱われ、独立した価値が認められていなかった。しかし、近年では、その独自の特性が評価され始め、専用ブランドも登場している。
ニュージーランドのいくつかの養蜂会社は、純粋なカヌカはちみつを「プレミアム」製品として販売し始めている。これらの製品は、マヌカのように標準化された活性指標はまだ確立されていないものの、総フェノール含量や抗酸化活性を強調している。
注:価格データについては市場変動が大きく、地域や品質により大きく異なるため、購入時には最新の市場価格を確認されたい。
6.3 製品開発の方向性
カヌカはちみつを活用した製品開発は、主に以下の方向性で進められている:
機能性食品:
抗酸化作用と抗炎症作用を強調したサプリメントや特定保健用食品としての開発。
スキンケア製品:
抗炎症作用と皮膚マイクロバイオーム調整作用を活かした、アトピー性皮膚炎や敏感肌向けのスキンケア製品の開発。ニュージーランドのいくつかの化粧品ブランドでは、カヌカはちみつを配合した保湿クリームや軟膏が販売されている。
呼吸器系の健康サポート:
カヌカ植物の精油成分に由来する呼吸器系への効果を活かした製品。カヌカはちみつのど飴や、カヌカはちみつシロップなどが開発されている。
医療グレード製品:
まだ初期段階ではあるが、カヌカはちみつの抗炎症特性を活かした医療グレードの創傷被覆材や皮膚炎治療製品の開発研究も進められている。
6.4 研究と開発の課題
カヌカはちみつのさらなる研究と開発には、いくつかの課題が存在する:
標準化の必要性:
マヌカはちみつのUMFやMGO値に相当する、カヌカはちみつの活性を示す標準化された指標がまだ確立されていない。総フェノール含量や特定のフラボノイド(ピノセンブリンなど)の含有量が候補として考えられているが、国際的に認知された基準はまだない。
特異的マーカーの同定:
カヌカはちみつの真正性を確保するための特異的化学マーカーの同定と検証方法の確立が求められている。これは、マヌカはちみつとの混合や偽和を防ぐためにも重要である。
臨床エビデンスの蓄積:
カヌカはちみつの医療応用には、さらなる臨床試験によるエビデンスの蓄積が必要である。特に、皮膚疾患や呼吸器系疾患に対する効果については、少数の予備的研究しか実施されていない。
持続可能な生産体制:
カヌカ植物は成長が遅く、森林伐採や土地利用変化によって生息地が減少している。持続可能な採蜜のためには、カヌカ林の保全と再生が課題となる。
7. カヌカはちみつの未来:付加価値創出への道筋
カヌカはちみつの潜在的価値を最大化し、「マヌカの影」から脱却するためには、どのような道筋が考えられるだろうか。
7.1 差別化戦略:独自性の強調
マヌカはちみつとの直接的な競争ではなく、カヌカはちみつの独自の特性を強調した差別化戦略が重要である。具体的には以下のような方向性が考えられる:
官能特性の価値化:
カヌカはちみつの繊細な風味プロファイルを食文化の文脈で価値化する。例えば、特定の料理や飲料とのペアリング提案や、料理人とのコラボレーションなどが考えられる。
機能性の特化:
マヌカの抗菌活性ではなく、カヌカの抗炎症作用や抗酸化作用、皮膚マイクロバイオーム調整作用など、独自の機能性に焦点を当てた製品開発を進める。
文化的・生態学的物語:
カヌカ植物の生態学的重要性や、マオリ文化における伝統的利用など、文化的・生態学的な物語性を付加価値として活用する。
7.2 科学的基盤の強化
カヌカはちみつの価値を確立するためには、さらなる科学的研究が不可欠である:
作用メカニズムの解明:
カヌカはちみつの抗炎症作用や抗酸化作用のより詳細な分子メカニズムの解明が必要である。特に、特定のフラボノイド成分と生理活性の関連の解明が重要となる。
臨床研究の拡充:
皮膚疾患、呼吸器疾患、胃腸疾患などに対するカヌカはちみつの効果を検証する臨床研究の実施が求められる。特に、アトピー性皮膚炎や敏感肌へのアプローチは有望分野である。
標準化と品質保証:
カヌカはちみつの活性を示す標準化された指標の確立と、それに基づく品質保証システムの構築が必要である。ピノセンブリン含有量や総フェノール含量、抗炎症活性などが候補として考えられる。
7.3 持続可能性と生物多様性保全
カヌカはちみつの長期的な価値創出には、持続可能性の視点が不可欠である:
カヌカ林の保全と再生:
カヌカ植物は森林再生の看護樹種としての役割があり、その保全は生物多様性保全と炭素固定の観点からも重要である。カヌカはちみつの生産と生態系保全を結びつけた取り組みが求められる。
原産地保護制度の確立:
ニュージーランド固有のカヌカはちみつの価値を保護するための原産地表示保護制度(GI: Geographical Indication)の確立も検討すべき課題である。
先住民族の知識と権利の尊重:
マオリの伝統的知識をカヌカはちみつの価値創出に活用する際には、先住民族の知的財産権を尊重し、利益共有の仕組みを構築することが重要である。
7.4 新たな応用分野の開拓
カヌカはちみつの潜在的価値を最大化するためには、従来の枠組みを超えた新たな応用分野の開拓も重要である:
機能性素材としての抽出物:
カヌカはちみつから特定の機能性成分(フラボノイド類など)を抽出・精製し、機能性食品や化粧品、医薬品の原料として活用する方向性も考えられる。
環境修復への応用:
カヌカ植物の環境適応能力と窒素固定能力を活かした、鉱山跡地や荒廃地の修復プログラムとカヌカはちみつ生産を組み合わせた取り組みも検討に値する。
発酵飲料への応用:
カヌカはちみつの特徴的風味を活かした発酵飲料(ミード、蜂蜜酒)の開発も、付加価値創出の一つの方向性である。一部の醸造所では、すでにカヌカはちみつを用いた特産品開発が始まっている。
結論:影から光へ—カヌカはちみつの再評価
本稿では、マヌカの影に隠れがちであったカヌカはちみつの科学的特性と潜在的価値について探究してきた。カヌカはちみつは、マヌカとは異なる化学組成と生理活性を持ち、特に抗炎症作用、抗酸化作用、皮膚マイクロバイオーム調整作用などが注目される。その繊細な風味プロファイルも、食品としての付加価値を高める重要な特性である。
『市場ポジショニングの再考という視点で理解すると』、カヌカはちみつはマヌカはちみつの「劣った代替品」ではなく、独自の特性と価値を持つ特産品として再評価されるべきである。そのためには、さらなる科学的研究の蓄積、標準化された品質指標の確立、差別化された商品開発、そして持続可能性を考慮した生産体制の構築が求められる。
ニュージーランドの生物多様性の産物であるカヌカはちみつは、その潜在的価値がまだ十分に認識されていない「隠された宝石」と言えるだろう。しかし、適切な研究と開発により、マヌカの影から光へと移行し、独自の市場ポジションを確立する可能性を秘めている。
『生態学的価値と商業的価値の統合という観点から』、カヌカはちみつは単なる商品を超えて、ニュージーランドの自然遺産保護と持続可能な産業発展のシンボルとなる可能性を持っている。その実現には、科学者、生産者、政策立案者、そして消費者の協力による包括的なアプローチが不可欠である。
注:本稿で紹介された研究データや分析結果は、現在も継続的に更新されている分野であり、最新の研究動向については専門文献の確認が推奨される。
参考文献
Allen, K. L., Molan, P. C., & Reid, G. M. (1991). A survey of the antibacterial activity of some New Zealand honeys. Journal of Pharmacy and Pharmacology, 43(12), 817-822.
Alvarez-Suarez, J. M., Gasparrini, M., Forbes-Hernández, T. Y., Mazzoni, L., & Giampieri, F. (2014). The composition and biological activity of honey: A focus on Manuka honey. Foods, 3(3), 420-432.
Alvarez-Suarez, J. M., Giampieri, F., Cordero, M., Gasparrini, M., Forbes-Hernández, T. Y., Mazzoni, L., … & Battino, M. (2016). Activation of AMPK/Nrf2 signalling by Manuka honey protects human dermal fibroblasts against oxidative damage by improving antioxidant response and mitochondrial function promoting wound healing. Journal of Functional Foods, 25, 38-49.
Chan, C. W., Deadman, B. J., Manley-Harris, M., Wilkins, A. L., Alber, D. G., & Harry, E. (2013). Analysis of the flavonoid component of bioactive New Zealand Mānuka (Leptospermum scoparium) honey and the isolation, characterisation and synthesis of an unusual pyrrole. Food Chemistry, 141(3), 1772-1781.
Chepulis, L. M., Francis, E., & Chin, N. L. Q. (2013). The effect of honey compared to sucrose, mixed sugars, and a sugar-free diet on weight gain in young rats. Journal of Food Science, 78(8), H1221-H1229.
de Lange, P. J. (2014). A revision of the New Zealand Kunzea ericoides (Myrtaceae) complex. PhytoKeys, 40, 1-185.
Fingleton, J., Corin, A., Sheahan, D., Cave, N., Woodall, M., Marlow, G., … & Beasley, R. (2014). Pilot study investigating the feasibility of a randomised controlled trial of inhaled Manuka honey for the treatment of bronchiectasis. BMJ Open Respiratory Research, 1(1), e000024.
Hawkins, J., de Vere, N., Griffith, A., Ford, C. R., Allainguillaume, J., Hegarty, M. J., … & Adams-Groom, B. (2015). Using DNA metabarcoding to identify the floral composition of honey: A new tool for investigating honey bee foraging preferences. PLoS One, 10(8), e0134735.
Leong, A. G., Herst, P. M., & Harper, J. L. (2012). Indigenous New Zealand honeys exhibit multiple anti-inflammatory activities. Innate Immunity, 18(3), 459-466.
Lin, S. M., Molan, P. C., & Cursons, R. T. (2011). The controlled in vitro susceptibility of gastrointestinal pathogens to the antibacterial effect of Manuka honey. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, 30(4), 569-574.
Lindsay, B., Chin, D., Conlon, C., Rumbaugh, K., Smyth, A., Redinbo, M., … & Reid, G. (2018). Antimicrobial and immunomodulatory properties of Kanuka honey. Microbiology Open, 7(5), e00573.
Lu, J., Carter, D. A., Turnbull, L., Rosendale, D., Hedderley, D., Stephens, J., … & Harry, E. J. (2013). The effect of New Zealand Kanuka, Manuka and Clover honeys on bacterial growth dynamics and cellular morphology varies according to the species. PLoS One, 8(2), e55898.
Moar, N. T. (1985). Pollen analysis of New Zealand honey. New Zealand Journal of Agricultural Research, 28(1), 39-70.
Perry, N. B., Brennan, N. J., Van Klink, J. W., Harris, W., Douglas, M. H., McGimpsey, J. A., … & Anderson, R. E. (1997). Essential oils from New Zealand Manuka and Kanuka: Chemotaxonomy of Kunzea. Phytochemistry, 44(8), 1485-1494.
Stephens, J. M., Schlothauer, R. C., Morris, B. D., Yang, D., Fearnley, L., Greenwood, D. R., & Loomes, K. M. (2010). Phenolic compounds and methylglyoxal in some New Zealand Manuka and Kanuka honeys. Food Chemistry, 120(1), 78-86.
Thompson, J. (1983). Redefinitions and nomenclatural changes within the Leptospermum suballiance of Myrtaceae. Telopea, 2(4), 379-383.
Tomblin, V., Ferguson, L. R., Han, D. Y., Murray, P., & Schlothauer, R. (2014). Potential pathway of anti-inflammatory effect by New Zealand honeys. International Journal of General Medicine, 7, 149-158.
Vanhanen, L. P., Emmett, B., & Savage, G. P. (2011). Comparison of some sensory and chemical properties of Manuka and Kanuka honeys with references to their anti-microbial characteristics. Food Technology and Biotechnology, 49(2), 187-192.
Wardle, P. (1991). Vegetation of New Zealand. Cambridge University Press.