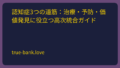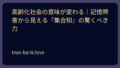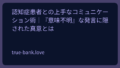第2部:科学哲学からみた形態共鳴—パラダイムシフトの可能性
イントロダクション:科学革命の境界で
科学の本質とは何か。どのような知識が「科学的」と呼ばれるのか。そして科学の境界はどこにあるのか。
ルパート・シェルドレイクの形態共鳴理論は、これらの問いに私たちを直面させる。前回概説した形態共鳴理論の基本概念—形態形成場、習慣としての自然法則、非局所的な情報伝達—は、現代科学の主流パラダイムに根本的な挑戦を投げかけている。この理論は単なる生物学的仮説を超え、科学の方法論や世界観そのものを問い直す試みでもある。
科学史家トーマス・クーンが『科学革命の構造』(1962)で示したように、科学は時に劇的な「パラダイムシフト」を経験する。地動説への転換、ダーウィンの進化論、アインシュタインの相対性理論などは、それまでの科学的世界観を根本から変革した。シェルドレイクの形態共鳴理論は、そのような科学革命の先駆けとなる可能性を秘めているのだろうか、それとも科学の境界を越えた思弁的仮説に過ぎないのだろうか。
本稿では、科学哲学の視点から形態共鳴理論を検討し、その科学的地位と革新的可能性について考察する。デカルト的二元論から量子力学的全体論へと移行しつつある科学史の文脈において、形態共鳴理論がどのように位置づけられるのか。また、ポパーの反証可能性やラカトシュの研究プログラム論など、現代科学哲学の基準から見たときに、この理論はどのように評価されるのか。さらに、生命科学における還元主義と全体論の対立、因果律の理解、実在の本質といった哲学的問題について、形態共鳴理論がどのような新たな視座を提供するのかを探っていく。
1. 科学パラダイムの歴史的変遷と形態共鳴理論
機械論的世界観の台頭と限界
現代科学の基盤となったデカルト・ニュートン的パラダイムは、17世紀の科学革命期に確立された。デカルトの心身二元論(精神と物質の分離)とニュートンの機械論的宇宙観は、世界を「巨大な時計仕掛け」として捉え、自然現象を物質の運動として還元的に説明しようとするアプローチを生み出した。
「世界は部分に分解でき、その部分の性質と運動法則から全体を理解できる」という前提は、古典物理学の驚異的な成功をもたらした。このパラダイムのもとで、天体の運動から熱力学、電磁気学に至るまで、自然界の多くの現象が数学的に記述可能となった。
しかし、哲学者アルフレッド・ノース・ホワイトヘッドが指摘したように、この機械論的世界観には「具体性の誤謬」(fallacy of misplaced concreteness)という根本的な問題がある(Whitehead, 1925)。すなわち、抽象的モデルと実在そのものを取り違え、生きた現実の複雑さを単純化しすぎるという誤りである。
特に生命現象の領域では、機械論的還元主義の限界が次第に明らかになってきた。生物学者ポール・ワイスは早くから「部分の総和以上の全体」としての生命システムの特性に注目し、「有機体論」(organicism)の立場を提唱していた(Weiss, 1939)。
シェルドレイクの形態共鳴理論は、まさにこの機械論的パラダイムの限界を指摘し、生命と意識の理解には新たな概念枠組みが必要だと主張している。彼は『科学の幻想』(2012)の中で次のように述べている:
「機械論的世界観は自然を理解する上で強力な道具だったが、それは科学的手法そのものというよりも、特定の歴史的時期に発展した一つの世界観に過ぎない。この世界観は、生命や意識を扱う際に根本的な限界に直面している」(Sheldrake, 2012)。
20世紀の科学革命:量子力学から複雑系へ
20世紀の科学は、それまでの機械論的パラダイムを根本から揺るがす発見の連続だった。量子力学は微視的世界の非決定論的性質と観測者の役割を明らかにし、アインシュタインの相対性理論は時間と空間の絶対性を否定した。さらに、ゲーデルの不完全性定理は数学的知識の限界を示し、ハイゼンベルクの不確定性原理は測定の根本的な制約を明らかにした。
物理学者デイヴィッド・ボームが提唱した「包摂秩序」(implicate order)の概念は、量子力学の解釈に新たな視点をもたらした。ボームによれば、私たちが認識する「展開秩序」(explicate order)の背後には、全てが相互に絡み合った「包摂秩序」が存在し、粒子の見かけ上の個別性は表層的な現象に過ぎない(Bohm, 1980)。
この視点はシェルドレイクの形態場概念と深い親和性を持っている。実際、シェルドレイクとボームは対話を重ね、「科学と霊性の再結合」(Science, Order, and Creativity, 1987)でその思想的共鳴を示している。両者は、現実を「関係性」と「全体性」の観点から捉え直す必要性を強調している。
さらに、20世紀後半から発展した複雑系科学、自己組織化理論、カオス理論などは、還元主義的アプローチでは捉えきれない創発的特性(emergent properties)に注目し、「全体は部分の総和以上」という有機体論的視点を科学的に基礎づけた。イリヤ・プリゴジンの「散逸構造」理論は、エネルギーを消費しながら自発的に秩序を形成する非平衡システムの性質を明らかにし、生命の自己組織化プロセスの理解に新たな概念的枠組みを提供した(Prigogine & Stengers, 1984)。
このような科学の発展は、還元主義から全体論への、線形的思考から非線形的思考への、実体中心から関係中心への大きなパラダイムシフトを示唆している。シェルドレイクの形態共鳴理論は、この新たなパラダイムを先取りする試みとして理解することもできる。
シェルドレイクのパラダイム批判:十の教義
シェルドレイクは『科学の幻想』(原題:Science Set Free, 2012)において、現代科学の根底にある「十の教義」(ten dogmas)を批判的に検討している。これらは明示的に述べられることは少ないが、科学的実践の前提となっている暗黙の信念だという:
- 宇宙は機械的な存在である
- 物質は意識を持たない
- 自然法則は不変である
- 保存される総エネルギー量は一定である
- 自然に目的性はない
- 生物の遺伝的継承は物質的である
- 記憶は脳内に物質的に保存される
- 心は脳内活動に過ぎない
- テレパシーのような超心理学的現象は錯覚である
- 機械論的医療は唯一の有効なアプローチである
シェルドレイクは、これらの「教義」が仮説から不問の前提へと変質し、科学的探究を制限していると主張する。科学者ルネ・トムも同様の懸念を表明し、「科学的唯物論は科学の方法論ではなく、一つの形而上学的信念体系になっている」と指摘している(Thom, 1989)。
形態共鳴理論は、特に「自然法則の不変性」「物質的な遺伝的継承」「脳内の記憶保存」といった教義に挑戦し、より柔軟で開かれた科学的世界観の可能性を探っている。ここには、科学と形而上学の境界、事実と価値の関係、観察と理論の相互依存性といった科学哲学の根本問題が関わっている。
2. クーンのパラダイム論から見た形態共鳴理論
通常科学とパラダイムの概念
トーマス・クーンの『科学革命の構造』(1962)は、科学の発展についての理解を根本から変えた。クーンは科学史の分析から、科学が単線的に累積されるのではなく、「通常科学」の時期と「科学革命」の時期が交互に現れることを指摘した。
「パラダイム」とは、ある時代の科学者集団が共有する理論、方法論、価値観、世界観の総体である。通常科学の時期には、科学者たちは既存のパラダイムの枠内で「パズル解き」に従事し、パラダイムの基本的前提を疑うことはない。
しかし、パラダイムでは説明できない「変則事例」(anomalies)が増加すると、科学者コミュニティに危機意識が生まれる。この危機の時期に、既存パラダイムに代わる新たな理論的枠組みが提案され、やがて「科学革命」によってパラダイムの転換が起こる。
クーンの視点から見ると、現代生物学の主流パラダイムである「分子生物学的・遺伝子中心的アプローチ」は、多くの成功を収めながらも、複数の変則事例に直面している。例えば:
- DNAだけでは説明できない形態形成の複雑さ
- クローンの個体差を説明する遺伝子外要因
- エピジェネティックな情報の世代間伝達
- 「失われた遺伝率」(missing heritability)問題
これらの変則事例は必ずしも現行パラダイムを否定するものではないが、科学者マイケル・デントンが指摘するように「遺伝子中心的パラダイムの説明力には明確な限界がある」(Denton, 2016)。
シェルドレイクの形態共鳴理論は、これらの変則事例に対する代替的説明を提供しようとする試みと見ることができる。しかし、クーンの指摘通り、新しいパラダイムが旧パラダイムに取って代わるためには、単に変則事例を説明できるだけでなく、旧パラダイムの説明力を保持しつつ、より広範な現象を統一的に説明できることが必要とされる。
形態共鳴理論と「パラダイム不整合性」
クーンの重要な洞察の一つに「パラダイム間の通約不可能性」(incommensurability)がある。異なるパラダイムに属する科学者は、同じ言葉で異なる概念を指し、同じ現象を異なる枠組みで解釈するため、真の意味での対話が難しくなる。
形態共鳴理論と主流生物学のパラダイム間にも、このような概念的断絶が見られる。例えば「記憶」という概念について、主流の神経科学では「ニューロンのネットワークにおけるシナプス結合の強化」という物理的プロセスとして理解されるのに対し、シェルドレイクは「形態場における非局所的な情報の蓄積」として捉える。このような根本的概念の相違は、両者の対話を困難にしている。
科学哲学者ハンス・ラデヴィはこれを「パラダイム不整合性」(paradigm incongruity)と呼び、「革新的理論が主流パラダイムから拒絶される主要因は、しばしば論理的矛盾よりも概念体系の不整合性にある」と指摘している(Radder, 1997)。
さらに、クーンが強調したように、パラダイムは単なる理論以上のものであり、科学者共同体の制度的・社会的構造や、研究資金の配分、教育システム、出版慣行など多くの要素と絡み合っている。このため、パラダイムの転換は純粋に論理的・証拠的な問題ではなく、社会的・心理的・制度的要因が複雑に絡み合う過程となる。
科学社会学者ブルーノ・ラトゥールの「アクターネットワーク理論」は、科学的知識の構築過程における人間的・非人間的アクターの複雑なネットワークを分析している(Latour, 1987)。この視点からは、形態共鳴理論がパラダイムシフトを引き起こすためには、理論の論理的整合性や証拠だけでなく、研究者ネットワーク、実験装置、研究施設、出版物、資金源など多様なアクターを動員する能力も問われることになる。
パラダイムシフトの条件と形態共鳴理論の可能性
形態共鳴理論がパラダイムシフトを引き起こす可能性について、クーンの視点から考察してみよう。クーンによれば、新パラダイムが旧パラダイムに取って代わるためには、以下の条件を満たす必要がある:
- 旧パラダイムが説明できない変則事例を説明できること
- 旧パラダイムの核心的成功を説明できること
- 新たな研究領域を開拓する可能性を示すこと
- 美的基準(単純性、一貫性、包括性など)を満たすこと
- 若い世代や新しい分野の研究者に訴求力を持つこと
形態共鳴理論は、第1の条件については部分的に満たしていると言える。前述のように、遺伝子中心的アプローチが十分に説明できない現象に対する代替的説明を提供している。
第2の条件については課題が残る。形態共鳴理論は、分子生物学の核心的成功(遺伝情報の分子的基盤、タンパク質合成のメカニズム、遺伝子発現の調節など)をどのように包含するのか、明確に示せていない。シェルドレイク自身も「形態共鳴理論は分子生物学に取って代わるものではなく、それを補完するものである」と述べている(Sheldrake, 2009)。
第3の条件については、形態共鳴理論は確かに新たな研究領域を示唆している。「共同的記憶」「種の学習」「人間と動物のテレパシー」などの現象は、従来の科学的枠組みでは周縁的とされてきたが、形態共鳴理論ではこれらが中心的研究対象となる。
第4と第5の条件については評価が分かれる。形態共鳴理論の単純性と包括性は魅力的だが、既存の科学的知識体系との整合性に課題がある。また、理論に対する評価は世代や研究分野によって大きく異なり、若手研究者の間でも賛否両論がある。
科学哲学者イアン・ハッキングは「科学革命は稀な現象だが、パラダイムの修正や拡張はより頻繁に起こる」と指摘している(Hacking, 2012)。この視点からは、形態共鳴理論が完全なパラダイムシフトを引き起こすよりも、既存パラダイムの修正や拡張に影響を与える可能性が高いかもしれない。
実際、システム生物学や統合生物学といった新しいアプローチは、還元主義的方法と全体論的視点の統合を目指しており、形態共鳴理論のいくつかの洞察と部分的に共鳴している。ノーベル賞受賞者のシドニー・ブレナーは「すべての生命現象を分子レベルに還元するのではなく、異なる階層を適切に関連づける理論的枠組みが必要だ」と主張している(Brenner, 2010)。
3. 科学哲学の視点からの形態共鳴理論の科学性評価
ポパーの反証可能性基準と形態共鳴理論
カール・ポパーの科学哲学における中心的概念は「反証可能性」(falsifiability)である。科学的理論と非科学的理論を区別する基準として、ポパーは「理論が経験的観察によって反証(否定)される可能性があるか」を重視した(Popper, 1959)。この基準によれば、いかなる観察結果によっても反証されない理論は科学的ではない。
形態共鳴理論の反証可能性については、評価が分かれる。シェルドレイク自身は理論の反証可能性を強調し、『七つの実験』(1994)では形態共鳴の存在を検証するための具体的な実験プロトコルを提案している。例えば:
- 新しい結晶化合物の形成が、時間の経過とともに世界中で容易になるか
- ラットが新しい迷路学習を行うとき、同種の別個体の学習速度が向上するか
- 人々がランダムに選ばれた画像を当てる実験で、繰り返し使用された画像は正答率が上がるか
これらはポパー的に言えば「反証可能な予測」であり、経験的観察によって形態共鳴理論を検証する可能性を示している。
しかし、批判者たちはこの理論の「免疫戦略」を指摘する。哲学者マリオ・ブンゲは「形態共鳴理論が実験結果と一致しない場合、理論の擁護者は『実験条件が不適切だった』『形態場の影響が小さすぎて検出できなかった』といった説明を後付けで導入し、理論を保護している」と批判している(Bunge, 2012)。
科学哲学者アドルフ・グリュンバウムも同様の懸念を表明し、「形態共鳴理論が予測する効果のサイズについての事前の規定がなく、どのような結果も理論に適合させることができる」と指摘している(Grünbaum, 1984)。
ポパー自身は後年、単純な反証主義を超えて「研究プログラム」の概念を発展させ、理論の「疑似科学性」は単一の基準ではなく、複数の要素からなる「家族的類似性」(family resemblance)によって判断されるべきだと考えるようになった(Popper, 1983)。
ラカトシュの研究プログラム論と形態共鳴理論
イムレ・ラカトシュはポパーの反証主義を発展させ、「科学的研究プログラム」の概念を提唱した。研究プログラムは「堅固な核」(hard core)と「防御帯」(protective belt)からなり、科学者は通常、核を保護しつつ防御帯を修正して異常事例に対応する(Lakatos, 1970)。
研究プログラムの進歩性は、新たな事実の予測と発見を導くかどうかで判断される。「進歩的」なプログラムは新しい予測と発見を生み出し、「退行的」なプログラムは既知の事実の事後的説明に終始する。
ラカトシュの枠組みから形態共鳴理論を評価すると、その科学的地位はやや曖昧になる。理論の「堅固な核」は明確(形態場の存在、形態共鳴のメカニズム、習慣としての自然法則など)だが、この核が新たな予測と発見を十分に生み出しているかどうかは議論の余地がある。
シェルドレイクの支持者は、彼の実験(特にテレパシーに関する研究)が従来の理論では予測できない現象を発見したと主張する。しかし批判者は、これらの実験結果の解釈や再現性に疑問を呈し、真に「進歩的」な研究プログラムの条件を満たしていないと考える。
科学哲学者ニコラス・マクスウェルは「科学的研究プログラムの評価には時間が必要であり、現時点で形態共鳴理論の可能性を完全に否定することはできない」と指摘している(Maxwell, 2004)。科学史を振り返れば、当初は周縁的だった研究プログラム(大陸移動説、冥王代の生命起源説など)が、数十年の時を経て主流になった例は少なくない。
ファイヤアーベントの方法論的多元主義
科学哲学者ポール・ファイヤアーベントは『方法への挑戦』(1975)において「科学に普遍的な方法は存在しない」と主張し、科学の発展には方法論的多元主義と一見奇抜に見える理論の存在が不可欠だと論じた。彼の有名な標語「何でもあり」(anything goes)は、科学的探究において多様なアプローチが許容されるべきだという主張を表している。
ファイヤアーベントによれば、科学史上の重要な進歩の多くは、当時の「科学的方法」の基準に従わない革新的思考から生まれた。ガリレオの望遠鏡観測、アインシュタインのゲダンケン実験、ウェゲナーの大陸移動説など、革新的理論は初期段階では「非科学的」と見なされることが多い。
このような視点からは、形態共鳴理論のような「境界科学」も科学の発展において重要な役割を果たす可能性がある。仮に理論そのものが最終的に否定されたとしても、そのアプローチが提起する問題や概念が主流科学に影響を与え、新たな研究方向を示唆することがある。
科学哲学者ハッサン・サンケイは「形態共鳴理論の最大の貢献は、それが正しいかどうかよりも、生命と意識の理解に関する新たな問いを提起し、代替的な思考実験を可能にした点にある」と評価している(Sankey, 2008)。
実際、シェルドレイクの問題提起の一部は、主流科学における新たな研究方向と共鳴している。例えば「記憶の保存と想起のメカニズム」「生物システムの自己組織化」「情報の非局所的伝達」といったテーマは、現代の神経科学、システム生物学、量子生物学などで活発に研究されている。
この観点からは、形態共鳴理論の科学性を単純に肯定/否定するのではなく、それが科学的対話と探究にどのように貢献しうるかを評価することが重要になる。
4. 境界科学の認識論的地位
境界科学と疑似科学の区別
「境界科学」(fringe science)とは、確立された科学的コンセンサスの周縁にあり、主流科学よりも投機的だが、科学の方法論を部分的に用いる研究領域を指す。一方、「疑似科学」(pseudoscience)は科学を装いながら、科学の基本的方法論(証拠に基づく推論、理論の改訂、批判的検討など)を欠く活動である。
境界科学と疑似科学の区別は単純ではなく、複数の基準が関わる。科学哲学者マイケル・シャーマーは以下の要素を考慮することを提案している(Shermer, 2013):
- 理論は証拠の変化に応じて修正されるか
- 提唱者は批判に対して理性的に応答するか
- 理論は確立された科学的知識と最小限の整合性があるか
- 理論は検証可能な予測を生み出すか
- 研究コミュニティは研究の質を管理しているか
これらの基準は連続的なスペクトラムを形成し、特定の理論がどこに位置するかは時に判断が難しい。形態共鳴理論の場合、これらの基準に関して評価が分かれる。
シェルドレイク自身は科学の方法論を重視し、『七つの実験』(1994)では「市民科学者」による実験検証を奨励している。また、批判に対しても詳細な反論を展開し、論争に積極的に参加している。この点では疑似科学の典型からは区別される。
他方、理論の根幹的要素(形態場の非物質性など)が確立された科学的知識と部分的に矛盾することや、実験結果の再現性に関する論争は、境界科学としての性格を示している。
科学社会学者トーマス・ギエリンは「境界作業」(boundary-work)の概念を提唱し、「科学と非科学の境界は固定的ではなく、科学者コミュニティの社会的実践によって常に再交渉されている」と指摘している(Gieryn, 1999)。この視点からは、形態共鳴理論の科学的地位も絶対的なものではなく、科学者コミュニティとの相互作用の中で変化していく可能性がある。
歴史的に境界から主流になった科学理論
科学史を振り返ると、初期には境界科学と見なされ、激しい批判を受けながらも、後に主流科学に受け入れられた理論は少なくない。代表的な例として:
- 大陸移動説: アルフレッド・ウェゲナーが1912年に提唱した大陸移動説は、当時の地質学者から「ファンタジー」「空想的」と批判された。しかし1960年代に海洋底拡大の証拠が発見され、プレートテクトニクス理論として主流化した。
- 陰石の地球外起源説: 18世紀末まで、多くの科学者は「空から石が落ちてくる」という報告を迷信として退けていた。しかし物理学者エルンスト・クラドニの研究と複数の目撃証言により、隕石の地球外起源が次第に受け入れられた。
- プリオン説: タンパク質のみで構成される感染因子「プリオン」の存在は、当初「生物学の中心教義に反する」として懐疑的に見られたが、スタンレー・プルシナーの研究により実証され、1997年にノーベル賞が授与された。
- 共生進化説: リン・マーギュリスが提唱した「真核細胞はかつて独立していた細菌の共生によって進化した」という理論は、1970年代には「荒唐無稽」と批判されたが、現在では細胞内小器官の起源を説明する標準理論となっている。
科学哲学者トーマス・ニッケルズは「境界科学が主流化するためには、強固な証拠の蓄積だけでなく、既存理論を補完または拡張する形で受容されるか、既存パラダイムに重大な危機が生じる必要がある」と指摘している(Nickles, 2019)。
これらの歴史的事例からの教訓は、現時点での科学的評価が最終的なものではなく、形態共鳴理論についても将来的な再評価の可能性は排除できないということだ。ただし、境界から主流になった理論は、批判に応じて修正を重ね、予測力を高め、経験的証拠を蓄積するプロセスを経ている点に注意が必要である。
形態共鳴理論の境界科学としての評価
形態共鳴理論を境界科学として見たとき、その特徴は以下のように整理できる:
境界科学としての積極的評価:
- 従来説明が難しかった現象(形態形成の詳細メカニズム、行動の跨種的伝播など)に対する代替的説明を提供している
- 実験的検証が可能な予測を生み出している
- 一部の実験結果は理論と一致すると主張されている
- 科学者コミュニティの一部に支持者がおり、査読付き論文も発表されている
- 量子物理学や複雑系科学の概念と部分的に共鳴している
境界科学としての課題:
- 提案される「形態場」の物理的基盤が不明確である
- 実験結果の再現性に関する論争が解決していない
- 理論の修正過程がしばしば事後的で、反証を避ける防御的なものになっている
- 主流科学の成功例をどのように包含するかが明確でない
- 科学者コミュニティの多数派からは依然として懐疑的に見られている
科学哲学者スティーブン・ブロードは「境界科学は主流科学と疑似科学の間の中間領域として見るべきではなく、革新的で挑戦的なアイデアが生まれる『創造的辺境』として理解すべきだ」と主張している(Braude, 2020)。
この視点からは、形態共鳴理論の価値はそれが「正しい」か「間違い」かという二分法ではなく、それが提起する問題設定や概念的革新、そして実験的探究がもたらす知見にあると言える。仮に理論の詳細は修正されるとしても、シェルドレイクが提起した問い—「生命はどのようにしてその形を獲得するのか」「情報はどのように保存され伝達されるのか」「自然法則はどのように確立されたのか」—自体は科学的に重要な問いであり続ける。
科学史家トーマス・ハンキンスは「新理論の誕生は予測や検証だけでなく、問題を定式化する新しい方法、現象を観察する新しい視点、そして以前は不可視だった現象を可視化する新しい方法によっても促進される」と指摘している(Hankins, 1985)。この点において、形態共鳴理論は科学的想像力を刺激し、新たな研究の可能性を切り開く役割を果たすかもしれない。
5. 生命科学における還元主義 vs 全体論
還元主義的アプローチの成功と限界
生命科学における還元主義的アプローチは、生命現象を分子レベルの相互作用に還元して理解しようとする。この戦略は20世紀の分子生物学において目覚ましい成功を収めた。DNAの二重らせん構造の解明、遺伝暗号の解読、ゲノム配列決定など、生命の基盤的メカニズムの理解が大きく進展した。
しかし、生物学者スチュアート・カウフマンが指摘するように、「還元主義的方法は強力だが、それだけでは生命システムの挙動を十分に説明できない」(Kauffman, 1995)。特に以下のような領域で限界が見られる:
- 発生過程の調整: 胚発生における細胞の位置情報や器官形成の調整機構の完全な理解には至っていない。
- 創発的特性: 複雑なシステムに現れる創発的特性(意識、自己組織化など)は、単純な要素還元では説明困難である。
- システム全体の統合: 複雑な代謝ネットワークや生理機能の統合的調整など、システム全体としての挙動の理解には限界がある。
- 進化のパターン: 長期的な進化のパターンや複雑性の増大など、マクロスケールの現象の説明には還元主義だけでは不十分である。
生物学者デニス・ノーブルは『生命の音楽』(The Music of Life, 2006)で、「生命は複数のスケールにまたがる重層的なシステムであり、どのレベルも他のレベルに還元できない因果的役割を持つ」と主張している。これは「ダウンワード・コーザリティ」(下向き因果)と呼ばれ、全体が部分の振る舞いに影響を与える現象を指す。
シェルドレイクの形態場の概念はまさにこの「下向き因果」を説明する試みと見ることができる。形態場は分子的相互作用を方向づけ、全体としての形態パターンを実現するという因果的役割を担っている。
全体論的視点の必要性
生命科学における全体論的アプローチは、システム全体としての特性や階層間の相互作用を重視する。この視点は、19世紀の「有機体論」(organicism)に起源を持ち、近年はシステム生物学や統合生物学として復活している。
全体論の代表的な主張は以下のようなものだ:
- 全体は部分の総和以上: 生命システムは構成要素の単なる集合ではなく、それらの相互作用から創発する特性を持つ。
- 階層的組織化: 生命は分子から細胞、組織、器官、個体、生態系へと至る階層的システムであり、各レベルは固有の法則性を持つ。
- 文脈依存性: 生物学的現象の理解には、構成要素だけでなく、それが置かれた文脈(環境、歴史、他の要素との関係)が重要である。
- 循環的因果関係: 生命システムでは、A→B→C→Aという循環的・非線形的な因果関係が一般的である。
生物学者ルートヴィヒ・フォン・ベルタランフィは『一般システム理論』(1968)で「生物学的還元主義は、生命の本質的特徴である組織化と全体性を見失わせる」と警告した。また、神経科学者ジェラルド・エーデルマンは『神経ダーウィニズム』(1987)で「脳の機能理解には、分子レベルから行動レベルまでを統合する多層的アプローチが不可欠」と主張している。
シェルドレイクの形態共鳴理論は、このような全体論的視点を極端な形で展開したものと見ることができる。彼の「形態形成場」は、生命システムの全体性や非局所的な情報伝達を説明するための概念装置である。
形態共鳴理論の提供する統合的視点の可能性
形態共鳴理論は、還元主義と全体論を統合する可能性を秘めているだろうか?
シェルドレイク自身は、形態共鳴理論が還元主義的アプローチを否定するのではなく、補完するものだと主張している:
「分子生物学の発見は重要であり、遺伝子がタンパク質の構造を指定することは疑いない。形態共鳴理論が問うのは、それだけで形態形成や行動の複雑なパターンを説明できるのかということだ」(Sheldrake, 2009)。
理論生物学者ブライアン・グッドウィンは、シェルドレイクの理論を「質的生物学」(qualitative biology)の一部として評価し、「量的・還元的アプローチと質的・全体的アプローチの統合が生物学の未来である」と主張している(Goodwin, 1994)。
形態共鳴理論が提供しうる統合的視点としては、以下のような側面がある:
- 多層的因果性: 分子レベルのメカニズムと、より高次の形態パターンの両方を説明する枠組み
- 情報と物質の関係: 情報(形態場のパターン)と物質(分子構造)の相互作用モデル
- 時間と記憶: 生物学的時間の非線形性と、種の「記憶」としての進化過程の理解
- 個と全体の関係: 個体発生と系統発生、個体と種全体の相互関係の説明
しかし、この統合的可能性を実現するためには、形態共鳴理論がより明確な実験的証拠を提示し、既存の生物学的知見と整合的に接続される必要がある。現状では、理論の基本概念(形態場、共鳴メカニズム)が既存の生物学的・物理学的概念と十分に接続されておらず、「概念的断絶」が統合を妨げている。
システム生物学者デニス・ブレイはより実用的な立場から「現在の生物学に必要なのは、抽象的な形而上学ではなく、分子から細胞、組織、個体へと至る多層的モデルの構築である」と主張している(Bray, 2009)。この視点からは、形態共鳴理論の価値は、それが提起する問いや視点が、より精緻なシステムモデルの構築にどう貢献できるかにかかっている。
6. 因果関係の理解:線形 vs 非線形
線形的因果関係の限界
古典的な科学的思考は、しばしば線形的な因果関係を前提としてきた。すなわち、原因Aが結果Bを生み、その大きさは比例関係にあるという考え方である。この思考法は「原因と結果の単純な対応関係」「加法性(原因の合計が結果の合計に等しい)」「可逆性(過程を逆転できる)」などの特徴を持つ。
しかし、特に生命システムや複雑系においては、この線形的因果モデルの限界が明らかになっている。複雑系研究者メリーン・ミッチェルは以下の非線形的現象を指摘している(Mitchell, 2009):
- 臨界点と相転移: わずかな量的変化が質的な転換をもたらす現象(例:細胞分化のスイッチング)
- フィードバックループ: 結果が原因に影響を与え、自己強化や自己抑制が生じる
- 創発的特性: 構成要素の単純な相互作用から、予測困難な高次パターンが生じる
- カオス的振る舞い: 初期条件のわずかな差異が、長期的に大きな変化をもたらす(バタフライ効果)
哲学者ナンシー・カートライトは『自然の法則はどこにあるのか』(1999)で、「自然科学の法則が適用されるのは、高度に理想化された条件下のみであり、複雑な実在の全体を捉えるには至らない」と主張している。
シェルドレイクの形態共鳴理論は、この線形的因果関係の限界を鋭く指摘し、非線形的・非局所的な因果関係のモデルを提案している。「過去のパターンが現在のパターン形成に影響を与える」という形態共鳴の概念は、時間と空間を超えた非線形的因果関係を想定している。
複雑系科学の非線形的アプローチ
複雑系科学は1980年代以降、物理学、生物学、社会科学などの分野で発展し、非線形的現象の理解に新たなアプローチをもたらした。サンタフェ研究所の創設者マレー・ゲルマンは複雑系を「適応的学習システム」と定義し、その特徴として自己組織化、創発、非線形相互作用、ヒエラルキー構造などを挙げている(Gell-Mann, 1994)。
複雑系科学の主要な概念的ツールには以下のようなものがある:
- 自己組織化: 外部からの詳細な指示なしに、構成要素の相互作用から秩序あるパターンが自発的に生じる現象
- 創発: システムの構成要素からは予測できない新たな特性や機能が高次レベルに現れる現象
- アトラクター: システムが長期的に収束する状態や振る舞いのパターン
- フラクタル: 自己相似的な構造を持ち、異なるスケールで類似したパターンを示す現象
- 相転移: システムの状態が質的に変化する臨界点現象
これらの概念は、シェルドレイクの形態共鳴理論と部分的に共鳴している。例えば、形態場による形態形成は一種の自己組織化現象と見ることができ、形態共鳴によるパターンの伝達はアトラクターの概念と関連づけられる。
複雑系理論家スチュアート・カウフマンの「可能性の隣接領域」(adjacent possible)の概念は、シェルドレイクの「習慣としての自然法則」と呼応する側面がある。両者とも、自然の法則や可能性が歴史的プロセスを通じて発展するという視点を共有している(Kauffman, 2000)。
形態共鳴理論の提案する因果関係の新たな理解
形態共鳴理論は、従来の因果関係の理解に対して以下のような新たな視点を提案している:
- 形態場による全体的調整: 局所的な分子相互作用だけでなく、形態場が全体的パターンを調整するという二重の因果性
- 時間を超えた因果関係: 過去の類似パターンが現在のパターン形成に影響を与えるという非線形的な時間関係
- 非局所的な情報伝達: 空間的に離れた類似システム間での情報共有という非局所的な因果性
- 習慣としての因果関係: 自然法則が固定されたルールではなく、習慣として発展するという動的な因果概念
この視点は、量子物理学における非局所性や量子もつれの概念と部分的に共鳴する。量子物理学者ヘンリー・スタップの「量子力学の参加的解釈」では、観測者と観測対象の間の相互作用が実在を共同創造するという考え方が提示されている(Stapp, 2007)。また、物理学者デイヴィッド・ボームの「包摂秩序」の概念も、形態共鳴理論と共通点を持っている。
しかし、科学哲学者ジェームズ・ラディマンは「形態共鳴理論の因果概念は魅力的だが、従来の物理学と整合的に接続されていない」と指摘している(Ladyman, 2012)。この「接続問題」は、理論の科学的受容における大きな障壁となっている。
現代の科学哲学では、因果関係の理解にも変化が見られる。「メカニスティック説明」(mechanistic explanation)のアプローチでは、単純な線形的因果ではなく、多様な構成要素がどのように相互作用して特定の現象を生み出すかを理解しようとする(Machamer et al., 2000)。
この新たな因果概念の発展は、還元主義と全体論の間の第三の道を示唆している。システム神経科学者テレンス・ディーコンは『インコンプリート・ネイチャー』(2012)で「創発的なプロセスは、部分から全体への単純な創発でも、全体から部分への単純な制約でもなく、異なる階層間の動的な相互作用から生じる」と主張している。
形態共鳴理論が提案する因果概念も、このような複雑系的・創発的因果性の一種と見ることができるかもしれない。ただし、その理論的・実証的基盤をより堅固にするためには、形態場と物理的プロセスの間の関係をより明確に説明する必要がある。
7. 実在の本質:実体論 vs 関係論
実体中心の存在論からプロセス・関係中心の存在論へ
西洋哲学の主流は長らく「実体」(substance)を中心とする存在論を採用してきた。アリストテレスからデカルトに至る伝統では、世界は本質的な性質を持つ離散的な実体から構成されると考えられてきた。この視点は近代科学にも引き継がれ、原子論的物質観や遺伝子還元主義などに反映されている。
しかし20世紀以降、この実体中心の存在論に代わる「関係論的」「プロセス中心」の存在論が発展してきた。哲学者アルフレッド・ノース・ホワイトヘッドの「過程哲学」は、静的な実体ではなく動的な「出来事」や「生成」を実在の基本単位と見なす(Whitehead, 1929)。
このような存在論的転換は、量子物理学の発展とも深く関連している。量子力学では粒子は独立した実体ではなく、場の振動や相互作用のパターンとして理解される。物理学者カルロ・ロヴェッリは「関係的量子力学」を提唱し、「量子系の特性は他の系との相互作用の中でのみ定義される」と主張している(Rovelli, 1996)。
生物学においても、「関係的生物学」のアプローチが発展している。理論生物学者ロバート・ローゼンは、生命を「関係のネットワーク」として理解し、その本質的特徴は構成要素ではなく「関係パターン」にあると主張した(Rosen, 1991)。また、進化生物学者リチャード・ルウォンティンは『遺伝子、有機体、環境』(1985)で、生物を遺伝子によって規定された実体としてではなく、遺伝子・有機体・環境の動的相互作用プロセスとして理解する視点を提示している。
シェルドレイクの形態共鳴理論もまた、この関係論的・プロセス的存在論の流れに位置づけられる。彼の「形態場」の概念は、実体というよりも関係性のパターンとして理解されるものであり、生物をその物質的構成要素に還元するのではなく、過去からの「習慣」の蓄積として捉える視点を提示している。
形態場の関係論的性質
シェルドレイクの形態場は、従来の物理学における「場」の概念と関連しつつも、独自の特性を持つ。彼はそれを以下のように説明している:
「形態場は物理的な場(電磁場など)と類似しているが、特定の種やシステムに固有の場であり、その形態と行動を組織化する役割を果たす。それは物質に還元されず、関係性のパターンとして理解される必要がある」(Sheldrake, 1988)。
形態場の関係論的性質は以下の点に表れている:
- 非局所性: 形態場は特定の空間領域に局在せず、類似したパターンを持つ系の間を「共鳴」によって繋ぐ
- 時間的連続性: 過去の類似パターンと現在のパターンの間に関係性を創出する
- 全体性: 個々の構成要素ではなく、系の全体的パターンを組織化する
- 文脈依存性: 同じ要素でも、置かれた文脈(関係性のネットワーク)によって異なる振る舞いを示す
このような関係論的視点は、量子物理学者デイヴィッド・ボームの「包摂秩序」の概念と共通点がある。ボームは宇宙を「明示的秩序」(物質世界として現れる側面)と「包摂的秩序」(すべてが相互連関した全体性)の二重構造として捉えた(Bohm, 1980)。
科学哲学者キャリン・バラッドはさらに徹底した関係論的存在論を提唱し、「行為体的実在論」(agential realism)において「実体は特定の関係的実践を通じて具体化される」と主張している(Barad, 2007)。この視点からは、形態場も特定の関係的実践を通じて具体化される可能性として理解できる。
情報としての実在という視点
もう一つの重要な存在論的転換は、「情報」を実在の根本的側面と見なす視点の発展である。物理学者ジョン・アーチボルド・ウィーラーは「イット・フロム・ビット」(it from bit)というフレーズで、情報が物質の基盤にあるという考えを表現した(Wheeler, 1990)。
情報理論の創始者クロード・シャノンは情報を「不確実性の減少」として定義したが、現代の情報概念はより広範で、「パターンの伝達と保存」「意味のある差異」「秩序の組織化」などの側面を含んでいる。
生物学者ハワード・パッティは「生命の本質は物質ではなく情報である」と主張し、生命を「物質的システムに具現化された情報プロセス」として理解する「生命情報学」(biosemiotics)のアプローチを発展させた(Pattee, 1969)。
この情報中心の視点は、シェルドレイクの形態共鳴理論と共鳴する。形態場は物質的実体ではなく「情報のパターン」として理解することができ、形態共鳴による情報の非局所的伝達は「情報としての実在」という視点と整合的である。
情報物理学者セス・ロイドは『プログラムされた宇宙』(2006)で、「宇宙は根本的には量子情報処理システムである」という視点を提示している。また、理論物理学者デイヴィッド・ドイッチュも『実在の構造』(2011)で、「情報が実在の最も基本的な構成要素である」と主張している。
これらの現代的視点は、シェルドレイクの形態共鳴理論が提示する「情報としての形態場」という考え方と部分的に共鳴する。ただし、シェルドレイクの理論が現代物理学の枠組みと完全に整合的かどうかは、依然として議論の対象である。
科学哲学者マイケル・シルバースタインは「形態共鳴理論は魅力的な概念的枠組みを提供するが、その情報概念を現代物理学や情報理論と整合的に接続するためには、より精緻な理論的展開が必要である」と指摘している(Silberstein, 2015)。
結論:科学的知識の境界と拡張可能性
形態共鳴理論をめぐる科学哲学的考察は、科学的知識の本質、境界、発展可能性について深い問いを投げかける。科学哲学者カール・ポパーは「大胆な仮説と厳格な反証」という科学の進歩モデルを提示したが、形態共鳴理論はまさにこの「大胆な仮説」としての性格を持っている。
理論が提起する革新的視点—形態場による全体的調整、習慣としての自然法則、非局所的情報伝達—は、現代科学の主流パラダイムに根本的な挑戦を投げかけている。しかし同時に、この理論は科学哲学における重要な論点—還元主義と全体論の統合、非線形的因果性の理解、関係論的存在論の発展—と深く関わっている。
形態共鳴理論が「科学的」かどうかという問いに単純な答えはない。この理論は現代の科学基準に照らせば「境界科学」に位置づけられるが、科学の歴史を振り返れば、かつて境界にあった理論が後に主流となった例も少なくない。
より建設的な問いは「この理論が科学的知識の拡張にどう貢献しうるか」ということだろう。形態共鳴理論の価値は、それが「正しい」か「間違い」かという二分法ではなく、それが提起する問題設定、概念的革新、実験的探究がもたらす知見にある。
科学哲学者トーマス・クーンが指摘したように、パラダイムの転換には単なる証拠の蓄積以上のものが必要となる。新たな世界観、新たな問い、新たな観察方法が求められる。形態共鳴理論がこれらを提供できるかどうかは、今後の理論的発展と実験的検証にかかっている。
科学史家スティーブン・ブルッシュは「革新的な科学理論の発展には、大胆な思弁と厳格な検証のバランス、そして既存知識との創造的な対話が不可欠である」と指摘している(Brush, 2015)。形態共鳴理論がこの創造的対話に参加し、科学の境界を拡張する可能性を秘めていることは否定できない。
最終的には、「この理論は科学か」という問いよりも、「この理論は自然の理解を深めるか」という問いの方が重要かもしれない。科学哲学者リチャード・ロティが述べたように、「科学の目的は世界の『真の姿』を映し出すことではなく、より良い生活と自然との関係を築くための概念的道具を提供することにある」(Rorty, 1991)。
次回の記事では、形態共鳴理論と現代物理学の接点に焦点を当て、量子力学、場の理論、複雑系物理学などの観点から理論の科学的基盤を検討する。シェルドレイクの「非物質的形態場」という概念が、現代物理学の枠組みでどのように解釈され、検証されうるのかを探っていく。
参考文献
Barad, K. (2007). Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning. Durham: Duke University Press.
Bohm, D. (1980). Wholeness and the Implicate Order. London: Routledge.
Bohm, D., & Hiley, B. J. (1993). The Undivided Universe: An Ontological Interpretation of Quantum Theory. London: Routledge.
Bohm, D., & Peat, F. D. (1987). Science, Order, and Creativity. New York: Bantam Books.
Braude, S. E. (2020). Dangerous Pursuits: Fringe Science and the Creative Edge. Journal of Scientific Exploration, 34(2), 215-240.
Bray, D. (2009). Wetware: A Computer in Every Living Cell. New Haven: Yale University Press.
Brenner, S. (2010). Sequences and consequences. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 365(1537), 207-212.
Brush, S. G. (2015). Making 20th Century Science: How Theories Became Knowledge. Oxford: Oxford University Press.
Bunge, M. (2012). Evaluating Philosophies. Dordrecht: Springer.
Cartwright, N. (1999). The Dappled World: A Study of the Boundaries of Science. Cambridge: Cambridge University Press.
Deacon, T. W. (2012). Incomplete Nature: How Mind Emerged from Matter. New York: W. W. Norton & Company.
Denton, M. (2016). Evolution: Still a Theory in Crisis. Seattle: Discovery Institute Press.
Deutsch, D. (2011). The Beginning of Infinity: Explanations That Transform the World. London: Allen Lane.
Edelman, G. M. (1987). Neural Darwinism: The Theory of Neuronal Group Selection. New York: Basic Books.
Feyerabend, P. (1975). Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge. London: New Left Books.
Gell-Mann, M. (1994). The Quark and the Jaguar: Adventures in the Simple and the Complex. New York: W. H. Freeman.
Gieryn, T. F. (1999). Cultural Boundaries of Science: Credibility on the Line. Chicago: University of Chicago Press.
Goodwin, B. C. (1994). How the Leopard Changed Its Spots: The Evolution of Complexity. New York: Charles Scribner’s Sons.
Grünbaum, A. (1984). The Foundations of Psychoanalysis: A Philosophical Critique. Berkeley: University of California Press.
Hacking, I. (2012). “Introductory Essay” in T. S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions: 50th Anniversary Edition. Chicago: University of Chicago Press.
Hankins, T. L. (1985). Science and the Enlightenment. Cambridge: Cambridge University Press.
Josephson, B. D., & Pallikari-Viras, F. (1991). Biological utilization of quantum nonlocality. Foundations of Physics, 21(2), 197-207.
Kauffman, S. A. (1995). At Home in the Universe: The Search for the Laws of Self-Organization and Complexity. New York: Oxford University Press.
Kauffman, S. A. (2000). Investigations. Oxford: Oxford University Press.
Kuhn, T. S. (1962). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press.
Ladyman, J. (2012). Science, metaphysics and method. Philosophical Studies, 160(1), 31-51.
Lakatos, I. (1970). “Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes” in I. Lakatos & A. Musgrave (eds.), Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge: Cambridge University Press.
Latour, B. (1987). Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers through Society. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Lewontin, R. C. (1985). The Organism as the Subject and Object of Evolution. In R. Levins & R. Lewontin, The Dialectical Biologist. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Lloyd, S. (2006). Programming the Universe: A Quantum Computer Scientist Takes on the Cosmos. New York: Knopf.
Machamer, P., Darden, L., & Craver, C. F. (2000). Thinking about mechanisms. Philosophy of Science, 67(1), 1-25.
Maxwell, N. (2004). Is Science Neurotic? London: Imperial College Press.
Mitchell, M. (2009). Complexity: A Guided Tour. Oxford: Oxford University Press.
Nickles, T. (2019). “Scientific Revolutions” in The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.).
Noble, D. (2006). The Music of Life: Biology Beyond Genes. Oxford: Oxford University Press.
Pattee, H. H. (1969). How does a molecule become a message? Developmental Biology Supplement, 3, 1-16.
Popper, K. (1959). The Logic of Scientific Discovery. London: Hutchinson.
Popper, K. (1983). Realism and the Aim of Science. London: Routledge.
Prigogine, I., & Stengers, I. (1984). Order Out of Chaos: Man’s New Dialogue with Nature. New York: Bantam Books.
Radder, H. (1997). Philosophy and History of Science: Beyond the Kuhnian Paradigm. Studies in History and Philosophy of Science, 28(4), 633-655.
Rorty, R. (1991). Objectivity, Relativism, and Truth: Philosophical Papers, Volume 1. Cambridge: Cambridge University Press.
Rosen, R. (1991). Life Itself: A Comprehensive Inquiry into the Nature, Origin, and Fabrication of Life. New York: Columbia University Press.
Rovelli, C. (1996). Relational quantum mechanics. International Journal of Theoretical Physics, 35(8), 1637-1678.
Sankey, H. (2008). Scientific Realism and the Rationality of Science. London: Routledge.
Sheldrake, R. (1988). The Presence of the Past: Morphic Resonance and the Habits of Nature. New York: Times Books.
Sheldrake, R. (1994). Seven Experiments That Could Change the World: A Do-It-Yourself Guide to Revolutionary Science. London: Fourth Estate.
Sheldrake, R. (2009). Morphic Resonance: The Nature of Formative Causation. Rochester, VT: Park Street Press.
Sheldrake, R. (2012). Science Set Free: 10 Paths to New Discovery. New York: Deepak Chopra Books.
Shermer, M. (2013). Science and Pseudoscience: The Difference in Practice and the Difference It Makes. In M. Pigliucci & M. Boudry (eds.), Philosophy of Pseudoscience: Reconsidering the Demarcation Problem. Chicago: University of Chicago Press.
Silberstein, M. (2015). Extending neutral monism to the hard problem. Journal of Consciousness Studies, 22(3-4), 181-194.
Stapp, H. P. (2007). Mindful Universe: Quantum Mechanics and the Participating Observer. Berlin: Springer.
Thom, R. (1989). Structural Stability and Morphogenesis: An Outline of a General Theory of Models. Reading, MA: Addison-Wesley.
von Bertalanffy, L. (1968). General System Theory: Foundations, Development, Applications. New York: George Braziller.
Weiss, P. A. (1939). Principles of Development. New York: Holt.
Wheeler, J. A. (1990). Information, physics, quantum: The search for links. In W. Zurek (ed.), Complexity, Entropy, and the Physics of Information. Redwood City, CA: Addison-Wesley.
Whitehead, A. N. (1925). Science and the Modern World. New York: Macmillan.
Whitehead, A. N. (1929). Process and Reality: An Essay in Cosmology. New York: Macmillan.