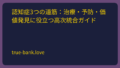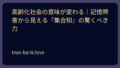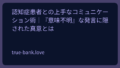第3部:積分思考がもたらす累積効果の解明 – 瞬間を超えた経験の総体化
瞬間から全体へ – 積分という視座転換
微分が「今この瞬間の変化」に焦点を当てるなら、積分はそれとは逆に「時間を通じた積み重ね」に光を当てる。瞬間から全体へ、点から面へ、変化から蓄積へ—これが積分の本質だ。
心理学において、私たちの経験は決して瞬間的な状態の連なりではない。むしろ、過去の瞬間が積み重なり、融合し、複雑に絡み合った総体として存在している。記憶、学習、感情、アイデンティティ—これらはすべて「経験の積分」によって形成される。
積分とは、無限に小さな量の連続的な総和を求める数学的操作だ。関数f(x)の定積分∫[a→b]f(x)dxは、区間[a,b]におけるf(x)の「面積」を表す。この「面積」という概念は、心理現象においては「経験の総量」「蓄積された効果」「履歴の影響」など、様々な意味を持ちうる。
興味深いのは、同じ関数でも、その積分と微分は全く異なる情報を提供する点だ。微分が「局所的な変化の特性」を明らかにするのに対し、積分は「全体的な累積の特性」を示す。この相補的な視点こそが、微積分の力であり、心理現象の理解に新たな次元をもたらす。
心理学者William Jamesは「意識の流れ」という概念を提唱したが、これは積分的視点の先駆けと言える。彼の言葉を借りれば、「意識は離散的な状態の連なりではなく、連続的に流れる川のようなもの」だ。この流れの全体を捉えるには、積分という数学的言語が必要となる。
さらに、異なる経路に沿った積分値が異なるという「経路依存性」の概念は、心理学的にも重要な意味を持つ。同じ最終状態に至る異なる経験経路は、異なる心理的結果をもたらす。これは「過程の質」が「結果の本質」を決定するという深い洞察を数学的に表現している。
面積としての総体験 – 積分の数学的本質と心理学的意味
積分の基本概念をより正確に理解するために、その数学的定義と心理学的解釈を深掘りしよう。
定積分∫[a→b]f(x)dxは、以下のように定義される:
∫[a→b]f(x)dx = lim[n→∞] Σ[i=1→n] f(x_i)Δx
ここで区間[a,b]をn個の小区間に分割し、各小区間の関数値と幅の積を合計、そしてnを無限大に近づける操作を行う。これは「無限小の経験の連続的総和」と解釈できる。
心理学的には、これは「離散的な経験の点が、連続的な経験の流れへと融合する過程」を表現している。例えば学習過程の積分は、個々の学習エピソードが融合して形成される「知識の連続体」を表す。
積分の興味深い性質の一つは、原始関数(不定積分)F(x)=∫f(x)dxとその導関数の関係だ:
F'(x) = f(x)
つまり、原始関数の変化率は元の関数に等しい。心理学的に解釈すれば、「経験の蓄積速度」は「現在の経験強度」に等しいということだ。これは直観的にも理解しやすい—強い経験はより速く蓄積され、弱い経験はより緩やかに蓄積される。
積分と微分の間には「基本定理」という重要な関係がある:
∫[a→b]f(x)dx = F(b) - F(a)
これは「区間[a,b]での積分値」が「終点での蓄積量」から「始点での蓄積量」を引いた値に等しいことを示す。心理学的には、「ある期間の経験の総体」は「最終状態」と「初期状態」の差として理解できるということだ。
しかし、心理現象の多くは「経路依存的」である。つまり、同じ始点aと終点bを持つ異なる経路Cが、異なる積分値をもたらす:
∫_C f(x,y)ds ≠ ∫_C' f(x,y)ds (C≠C')
これは「経験の質は、単に始点と終点だけでなく、その間の経路全体によって決定される」ことを数学的に表現している。
例えば、同じ学習目標に到達する二人の学習者を考えよう。一人は順調に学習を進め、もう一人は試行錯誤を繰り返した。最終的な知識レベルは同じでも、二人の「学習経験の積分値」は大きく異なる。この差異が、知識の「深さ」や「転移可能性」に影響を与える可能性がある。
近年の「経験サンプリング法」(Experience Sampling Method)による研究は、まさにこの積分的視点を実証的に探求している。Csikszentmihalyi & Larson (2014)は、断続的な経験サンプルから連続的な「経験の流れ」を再構成し、その積分的特性を分析する方法論を発展させた。
ダニング=クルーガー効果の積分 – 学習軌跡の総体
ダニング=クルーガー効果を積分的視点から再解釈すると、能力開発の全過程における自己認識の「総体験量」という新たな概念が浮かび上がる。
第2部で検討した自己評価関数f(x)の定積分:
∫[x₁→x₂]f(x)dx
は、能力がx₁からx₂へ向上する過程での自己評価の「総量」を表す。この積分値は単なる数学的抽象ではなく、学習の質的特性と密接に関連している。
特に興味深いのは、「誤差関数」e(x) = f(x) – xの積分だ:
E = ∫[x₁→x₂]e(x)dx = ∫[x₁→x₂](f(x) - x)dx
この値Eは「能力開発過程全体を通じての自己評価誤差の総和」を表し、「学習過程の主観的歪み」の指標と解釈できる。Eが大きい正の値をとる場合、学習者は過程全体を通じて自己を過大評価する傾向があり、Eが負の値をとる場合は自己過小評価の傾向があることを示す。
Ehrlinger et al. (2008)の研究によれば、このE値は学習成果の予測因子となりうる。彼らは、E > 0(持続的過大評価)の学習者はフィードバック受容度と学習率が低い傾向を示し、E < 0(持続的過小評価)の学習者はより慎重だが挑戦回避傾向が高いことを示した。最も効果的な学習は、E ≈ 0、つまり過大評価と過小評価が学習過程全体でバランスする場合に生じる。
さらに、誤差関数の符号が切り替わる「無知の山」の前後で積分を分割することで、より詳細な分析が可能になる:
E_early = ∫[x₁→x*]e(x)dx (x* = peak of Mount Stupid)
E_late = ∫[x*→x₂]e(x)dx
Kruger & Dunning (1999)のデータの再分析によれば、E_earlyとE_lateの比率が学習の「メタ認知的質」と関連する。E_early >> |E_late|の場合(初期の過大評価が後期の過小評価を大きく上回る)、学習者は「認知的調整」に失敗する傾向がある。一方、E_early ≈ |E_late|の場合(初期の過大評価と後期の過小評価がバランスする)、学習は「認知的柔軟性」を特徴とする。
この積分的視点は、ダニング=クルーガー効果を「点としての誤認」ではなく「学習軌跡全体の特性」として捉え直す道を開く。重要なのは特定時点での自己評価の正確さではなく、学習過程全体を通じての自己評価のバランスなのだ。
Mitric & Mascie-Taylor (2015)は、この考えをさらに発展させ、「適応的自己評価軌跡」(adaptive self-assessment trajectory)という概念を提案している。これは、学習初期の適度な自己過大評価(E_early > 0)が動機づけとして機能し、学習後期の適度な自己過小評価(E_late < 0)が継続的改善を促進するという理想的パターンを表す。彼らの縦断研究によれば、この軌跡に近い学習者は、単に「正確な自己評価」を持つ学習者よりも、長期的には優れた成果を示す傾向がある。
ジャネーの法則と履歴効果 – 心的疲労の時間的積分
ジャネーの心的エネルギー消費の法則を積分的視点から検討すると、時間を通じた「心的仕事量」の総体が見えてくる。これは単なる「瞬間的状態」ではなく、時間的文脈に依存した非線形的な主観的経験だ。
ジャネーの基本関数:
f(t) = E₀ × (1 - e^(-kt)) / t
の定積分:
W = ∫[t₁→t₂]f(t)dt
は、時間区間[t₁,t₂]における総心的仕事量を表す。この積分値Wは、単なる「エネルギー消費の総量」ではなく、主観的に経験される「疲労感」や「達成感」と深く関連する。
興味深いのは、同じ積分値Wであっても、負荷の時間的パターンによって主観的経験が大きく異なる点だ。例えば、負荷が徐々に増加するパターン(ランプ関数)と、急激に増加後一定となるパターン(ステップ関数)では、積分値が同じでも後者の方が主観的疲労感が大きい。これは積分過程の「履歴効果」を示している。
Hockey (2011)は、この現象を「努力の履歴積分」(effort history integral)として定式化した:
H = ∫[0→T]w(t)·f(t)dt
ここでw(t)は時間依存的な重み関数であり、直近の経験ほど大きな重みを持つ(通常、指数関数的に減衰する記憶痕跡を反映)。この履歴積分Hは、同じ「面積」でも、その「形状」によって値が異なる。これは主観的疲労が単なる状態の加算ではなく、時間的文脈に依存した非線形積分であることを示している。
Geurts & Sonnentag (2006)の「努力-回復モデル」を積分的に再解釈すると、システム状態の時間発展を表す微分方程式:
dE/dt = -αE(t) + βR(t) - γL(t)
dR/dt = δ(E₀ - E(t)) - εR(t)
の解は、初期条件と入力関数L(t)(外部負荷)の積分によって決定される:
E(t) = E(0)e^(-αt) + ∫[0→t]e^(-α(t-s))(βR(s) - γL(s))ds
この解は、「現在の心的状態」が「過去の負荷と回復の履歴全体」の積分によって決定されることを数学的に表現している。特定時点の状態だけでなく、そこに至る過程全体が重要なのだ。
Zijlstra et al. (2014)は、この積分的視点を「疲労の蓄積関数」(fatigue accumulation function)として発展させた。彼らの実験では、被験者に異なる負荷パターンを課し、主観的疲労と生理指標を測定した。その結果、「負荷と回復の経路に沿った積分値」が、単純な「総負荷量」より疲労予測の精度が高いことが示された。特に、回復期間の戦略的配置が積分値に劇的な影響を与えることが明らかになった。
さらに興味深いのは、同じ心的仕事量でも、「意味のある仕事」と認識されるか「無駄な労力」と感じるかによって、主観的経験が劇的に変わる点だ。これは単なる「重み付け」では説明できない非線形性を示唆している。
Deci & Ryan (2008)の自己決定理論に基づく研究では、内発的動機づけによる活動と外発的動機づけによる活動では、同じエネルギー消費量でも「活力消耗の積分値」が異なることが示されている。数学的には、これは積分重み関数w(t)が活動の意味づけによって修飾されることを意味する。
一般的な見方では、心的エネルギーの消費は単純に「燃料の消費」のようなものとされるが、積分的視点が示唆するのは、むしろそれが「意味の生成過程」であるという可能性だ。エネルギー消費の時間的パターンがその主観的意味を創発的に生み出しているのかもしれない。
ヤーキーズ=ドッドソンの法則の積分 – 持続可能なパフォーマンスの条件
ヤーキーズ=ドッドソンの法則の積分的解釈は、特定の覚醒区間におけるパフォーマンスの「累積効果」を示し、持続的活動の最適戦略を示唆する。
基本的な二次関数表現:
P(A) = -k(A - A_opt)² + P_max
の定積分:
PT = ∫[A₁→A₂]P(A)dA
は、覚醒レベルがA₁からA₂へ変化する間の「総パフォーマンス」を表す。これは単発的なピークパフォーマンスではなく、持続的な活動効率を評価する指標となる。
しかし実際の関心は、時間を通じたパフォーマンスの蓄積だろう。覚醒レベルが時間とともに変化する関数A(t)を考えると、総パフォーマンスは:
PT = ∫[t₁→t₂]P(A(t))dt
となる。これは「時間を通じたパフォーマンスの累積」を表し、単発的な最高パフォーマンスと持続的な総合パフォーマンスの違いを浮き彫りにする。
Matthews & Davies (2001)の研究では、この積分的視点から「サスティナブル・パフォーマンス・カーブ」(sustainable performance curve)という概念が提案されている。彼らは、短期的には最適より高い覚醒レベルA > A_optがパフォーマンスを低下させるが、長期的持続性を考慮した場合はむしろA < A_optの「控えめな覚醒」が総合パフォーマンスを最大化する可能性を示した。
数学的に表現すると、時間区間[0,T]での総パフォーマンスを最大化する最適覚醒プロファイルA*(t)は、次の変分問題の解として与えられる:
A*(t) = argmax ∫[0→T]P(A(t))dt subject to ∫[0→T]C(A(t))dt ≤ E_max
ここでC(A)は覚醒レベルAの維持コスト関数、E_maxは利用可能な総エネルギーを表す。この最適化問題の解は一般に、A*(t) < A_optとなる。つまり、持続的活動では「控えめな覚醒」が最適なのだ。
Hockey (2013)の資源管理モデルに基づく実験では、被験者に低・中・高の覚醒レベルでの作業を課し、短期(30分)と長期(3時間)のパフォーマンスを比較した。短期では中〜高覚醒が優位だったが、長期では低〜中覚醒が総合パフォーマンスで勝った。これは積分的評価の重要性を示している。
さらに複雑なのは、覚醒レベルの変動パターンだ。同じ平均覚醒レベルでも、変動パターンによって積分値が異なる。例えば:
PT_constant = ∫[0→T]P(A_mean)dt
PT_variable = ∫[0→T]P(A_mean + δ(t))dt
ここでδ(t)は平均ゼロの変動関数を表す。ヤーキーズ=ドッドソンの曲線が上に凸(P”(A) < 0)であるため、ジェンセンの不等式より:
PT_variable < PT_constant (P''(A) < 0の場合)
つまり、覚醒レベルの変動は積分パフォーマンスを低下させる。這い数学的洞察は、「一定の適度な覚醒」が「変動する覚醒」より効率的であることを示している。
しかし、現実の課題では状況が逆転することもある。例えば創造的問題解決では、覚醒レベルの意図的変動が有効な場合がある。Poincaré-Hadamardの創造的プロセスモデルでは、「緊張」と「緩和」の周期的交替が創造性を高めると考えられている。これを数学的に表現すると:
C = ∫[0→T]Q(A(t),dA/dt)dt
ここでCは創造的成果、Q(A,dA/dt)は覚醒レベルとその変化率に依存する創造性関数である。このモデルでは、dA/dt ≠ 0、つまり覚醒レベルの変動自体が創造的過程に寄与する。
この視点は、Fredrickson & Losada (2005)の「拡張—構築理論」(broaden-and-build theory)とも共鳴する。彼らのモデルでは、ポジティブ情動(低〜中覚醒)が「思考—行動レパートリーの拡張」をもたらし、ネガティブ情動(中〜高覚醒)が「特定行動の構築」に寄与すると考える。最適な創造的パフォーマンスは、この両者の動的バランスによって実現される:
C = ∫[0→T]B(t)·P(A(t))dt
ここでB(t)は思考—行動レパートリーの広さを表す。Fredrickson & Losadaによれば、最適な創造性は「ポジティブ—ネガティブ情動の比率」が特定の臨界値(約3:1)で実現されるという。
経路依存性と経験積分 – 過程が結果を決める数学
心理現象の多くは「経路依存的」だ。つまり、同じ始点と終点を持つ異なる経路が、異なる心理的結果をもたらす。この「過程の質が結果を決定する」という直観を、数学的に表現するのが経路積分の概念だ。
多次元空間における経路Cに沿った積分:
I = ∫_C f(x,y,...)ds
は、その経路全体の特性を捉える。心理学的には、これは「経験の質的総体」を表現している。
例えば、学習曲線の経路積分は「学習経験の質的特性」を反映する。同じ知識レベルに到達する二人の学習者が、異なる学習経路C₁とC₂を辿ったとする:
I₁ = ∫_C₁ L(k,dk/dt,...)ds
I₂ = ∫_C₂ L(k,dk/dt,...)ds
ここでkは知識レベル、L(k,dk/dt,…)は学習経験の質を表す関数である。I₁ ≠ I₂の場合、二人の「学習経験の質」は異なる。これは同じ「知識量」でも、その獲得過程によって知識の「深さ」「柔軟性」「転移可能性」が異なることを数学的に表現している。
Bjork & Bjork (2011)の「望ましい困難」(desirable difficulties)理論は、この経路依存性を実証的に裏付けている。彼らの研究によれば、学習過程で適度な困難を経験する経路C₁は、同じ最終知識レベルに到達する容易な経路C₂よりも、長期的には優れた知識定着と転移を示す。
I_retention = ∫_C L(k,dk/dt) × R(dk/dt)ds
ここでR(dk/dt)は知識獲得率に依存する記憶強化関数であり、「適度な困難」(小さいdk/dt)が高い記憶強化をもたらすと考えられる。
同様に、心理療法の経路依存性も重要だ。同じ症状改善を達成する異なる治療経路が、異なる「治療経験の質」をもたらす:
I_therapy = ∫_C T(s,ds/dt,...)dt
ここでsは症状レベル、T(s,ds/dt,…)は治療経験の質を表す関数である。Hayes et al. (2007)のプロセス重視療法研究では、症状改善の「速度」よりも「経路の質」(特に自己理解と受容の深化)が、長期的な再発防止に重要であることが示されている。
こうした経路依存性は、保存場と非保存場の区別にも関係する。保存場では、経路に依存せず積分値は始点と終点のみによって決まる:
∫_C₁ f(x,y)ds = ∫_C₂ f(x,y)ds (C₁とC₂が同じ始点と終点を持つ場合)
しかし心理現象の多くは非保存場を形成しており、経路そのものが積分値を左右する。
Vallacher & Nowak (1997)の動力学的社会心理学モデルでは、自己概念の形成を多次元状態空間における経路積分として表現している。このモデルによれば、同じ客観的経験(例:成功体験)でも、それが解釈される「意味づけ空間の経路」によって、自己概念への影響が大きく異なる。
ΔS = ∫_C M(e,c)ds
ここでΔSは自己概念の変化、eは経験、cは文脈、M(e,c)は意味づけ関数である。この積分は「経験が自己概念に与える影響」が、単に経験の「内容」だけでなく、その「解釈経路」にも依存することを表現している。
多重積分と心理的状態空間 – 経験の多次元的積分
心理的経験の累積効果を正確に表現するには、単純な一次元積分ではなく、多重積分の概念が必要になる。例えば、ある期間[t₁,t₂]における様々な状況Dと異なる強度Iでの情動体験の総量E_totalは:
E_total = ∫∫∫ E(t,D,I) dt dD dI
このような多重積分は、時間・状況・強度の三次元空間における「情動体験の体積」を表現している。
Barrett (2017)はこの考えをさらに発展させ、感情経験を「概念化された感情」と「身体的覚醒」の多次元空間における軌跡として捉え、この軌跡に沿った積分が主観的感情経験を形成すると論じている:
E_subjective = ∫_C L(c,p,a,s) ds
ここでcは概念化、pは知覚、aは覚醒、sは社会的文脈を表す多次元空間上の点、Lはこの空間での経験の強度関数である。この多次元積分は、感情が単一の「種類」や「強度」ではなく、多次元空間での「経路」として存在することを表現している。
Russell (2003)の「核心的影響」(core affect)理論も同様に、感情経験を快—不快と覚醒—鎮静の二次元空間での軌跡として捉える。この空間での経路積分:
A = ∫_C V(p,a) ds
は「感情経験の総体」を表し、瞬間的な感情状態の単なる集合ではなく、それらの統合的体験を表現している。
興味深いことに、Verduyn et al. (2015)の研究によれば、客観的に同じ「面積」(持続時間×強度)を持つ感情体験でも、その「形状」(強度の時間的推移パターン)によって主観的評価が大きく異なる。特に、強度が徐々に低下する「なだらか」なパターンは、急激に低下する「断崖」的パターンより、主観的には「長く」「強く」評価される傾向がある。
E_subjective = ∫[0→T] I(t) × w(dI/dt) dt
ここでI(t)は客観的強度、w(dI/dt)は強度変化率に依存する重み関数で、dI/dt < 0の絶対値が小さいほど(緩やかな低下)w(dI/dt)は大きくなる。
この多次元積分的視点は、「経験サンプリング法」(Experience Sampling Method)の理論的基盤ともなっている。Csikszentmihalyi & Larson (2014)は、離散的サンプリングデータから連続的な「経験空間」を再構成する方法論を発展させ、その積分的特性を分析している。
E_reconstructed = ∫∫∫ K(t-t_i, D-D_i, I-I_i) dt dD dI
ここでK(…)はカーネル関数、(t_i, D_i, I_i)はサンプリングポイントを表す。この再構成された経験空間の特性分析から、個人の「心理的ウェルビーイング」や「生活の質」の新たな理解が生まれている。
多重積分の概念は、「自伝的記憶」の理解にも応用される。Conway & Pleydell-Pearce (2000)の「自己記憶システム」(Self-Memory System)モデルでは、自伝的記憶は単なる「出来事の集合」ではなく、多次元空間での「統合的経験」として存在する:
M = ∫∫∫ S(e,c,s) de dc ds
ここでeは出来事、cは文脈、sは自己関連性を表す次元である。この多次元積分が「自己物語」の連続性と一貫性を生み出し、断片的な記憶を統合的な自己アイデンティティへと変換する。
結論:総体としての心 – 積分が明かす経験の全体性
心理法則を積分的視点から再検討することで、私たちは「瞬間」から「全体」へ、「状態」から「過程」へ、「点」から「面」へと視点を拡張した。この視点転換は、心理現象の時間的広がりと経路依存性を数学的に捉える道を開く。
ダニング=クルーガー効果の積分的解釈からは、学習過程全体を通じての自己評価のバランスが重要であることが示された。「学習軌跡の積分特性」としての誤差総量Eは、単なる「点としての誤認」よりも学習の質を良く反映する。最も効果的な学習は、初期の適度な過大評価と後期の適度な過小評価がバランスする「適応的自己評価軌跡」によって特徴づけられる。
ジャネーの法則の積分分析は、心的エネルギー消費の「履歴効果」を明らかにした。同じ総負荷量でも、その「時間的パターン」によって主観的疲労感が大きく異なる。「負荷と回復の経路に沿った積分値」が、単純な「総負荷量」より疲労予測の精度が高い。特に、回復期間の戦略的配置が積分値に劇的な影響を与える。
ヤーキーズ=ドッドソンの法則の積分的視点からは、短期的ピークパフォーマンスと長期的持続パフォーマンスの違いが浮かび上がった。持続的活動の最適覚醒レベルは、瞬間的ピークに必要なレベルより低い。さらに、覚醒レベルの変動パターンも積分値に影響し、目的によっては「一定の適度な覚醒」より「意図的な覚醒変動」が有効な場合もある。
経路積分の概念は、「過程の質が結果を決定する」という心理学的直観を数学的に表現する。同じ「終点」に至る異なる「経路」は、異なる「経験の質的総体」をもたらす。これは学習、治療、感情経験など、多くの心理現象に当てはまる。
多重積分の導入により、経験の多次元的積分という視点が開かれた。感情、記憶、アイデンティティなどは、多次元状態空間での「統合的経験」として存在し、その特性は単純な一次元評価では捉えきれない。
積分的視点が教えるのは、心とは「点の集合」ではなく「連続的な流れ」であり、「状態の連なり」ではなく「過程の総体」であるということだ。私たちの主観的経験は、無数の瞬間が融合し、絡み合い、統合された「経験の海」として存在している。その海の特性を理解するには、積分という数学的言語が不可欠なのだ。
次回の第4部では、心理法則を多変数関数として捉え直し、二次元平面から多次元空間への拡張を試みる。文脈依存性、個人差、相互作用効果など、従来の単純モデルでは捉えきれなかった複雑性に光を当てていく。
参考文献
Barrett, L. F. (2017). How emotions are made: The secret life of the brain. Houghton Mifflin Harcourt.
Bjork, R. A., & Bjork, E. L. (2011). Making things hard on yourself, but in a good way: Creating desirable difficulties to enhance learning. In M. A. Gernsbacher et al. (Eds.), Psychology and the real world: Essays illustrating fundamental contributions to society (pp. 56-64). Worth Publishers.
Conway, M. A., & Pleydell-Pearce, C. W. (2000). The construction of autobiographical memories in the self-memory system. Psychological Review, 107(2), 261-288.
Csikszentmihalyi, M., & Larson, R. (2014). Validity and reliability of the experience-sampling method. In M. Csikszentmihalyi (Ed.), Flow and the foundations of positive psychology (pp. 35-54). Springer.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008). Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development, and health. Canadian Psychology, 49(3), 182-185.
Ehrlinger, J., Johnson, K., Banner, M., Dunning, D., & Kruger, J. (2008). Why the unskilled are unaware: Further explorations of (absent) self-insight among the incompetent. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 105(1), 98-121.
Fredrickson, B. L., & Losada, M. F. (2005). Positive affect and the complex dynamics of human flourishing. American Psychologist, 60(7), 678-686.
Geurts, S. A., & Sonnentag, S. (2006). Recovery as an explanatory mechanism in the relation between acute stress reactions and chronic health impairment. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 32(6), 482-492.
Hayes, A. M., Laurenceau, J. P., Feldman, G., Strauss, J. L., & Cardaciotto, L. (2007). Change is not always linear: The study of nonlinear and discontinuous patterns of change in psychotherapy. Clinical Psychology Review, 27(6), 715-723.
Hockey, R. (2013). The psychology of fatigue: Work, effort and control. Cambridge University Press.
Hockey, G. R. J. (2011). A motivational control theory of cognitive fatigue. In P. L. Ackerman (Ed.), Cognitive fatigue: Multidisciplinary perspectives on current research and future applications (pp. 167-187). American Psychological Association.
Kruger, J., & Dunning, D. (1999). Unskilled and unaware of it: How difficulties in recognizing one’s own incompetence lead to inflated self-assessments. Journal of Personality and Social Psychology, 77(6), 1121-1134.
Matthews, G., & Davies, D. R. (2001). Individual differences in energetic arousal and sustained attention: A dual-task study. Personality and Individual Differences, 31(4), 575-589.
Mitric, G., & Mascie-Taylor, D. (2015). On the nature of adaptive self-assessment: A longitudinal investigation. Learning and Instruction, 40, 1-14.
Russell, J. A. (2003). Core affect and the psychological construction of emotion. Psychological Review, 110(1), 145-172.
Vallacher, R. R., & Nowak, A. (1997). The emergence of dynamical social psychology. Psychological Inquiry, 8(2), 73-99.
Verduyn, P., Van Mechelen, I., & Tuerlinckx, F. (2015). The relation between event processing and the duration of emotional experience. Emotion, 15(3), 259-273.
Zijlstra, F. R., Cropley, M., & Rydstedt, L. W. (2014). From recovery to regulation: An attempt to reconceptualize ‘recovery from work’. Stress and Health, 30(3), 244-252.