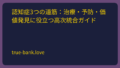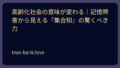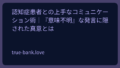※Click here to see this article written in English.

同じ人間という存在同士を注意深く観察すると、そこには「入れ物」としての人間と「実体」としての人間という2種類の様相が入り混じって同じ大地に立っているということがわかってくる。そして私が実体として正確に記述できるとき、この機能自体は合理的仕組みのように感じられ美しく、同時に個の存在として厄介で不愉快な面を感じてしまう。そしてこの感覚はおそらく欠陥であり、同時に欠陥が内包していながらなぜか機能していることはこれまたおそらく完全であり合理的であるに違いない。
私が入れ物であるときは、そもそも実体が機能している世界にはいない。いや、より正確に言うならば、大地は実体が機能する場であるがゆえに入れ物の存在環境は実体の場であるが、入れ物当人からすれば他(た)の実体が先導するその実体環境は、実体環境だと忘れてしまうか認識できないために、同じ環境対象を共有しているにも拘わらず入れ物の限定世界になる。
実体としての人間は、本質的に「個」であり、その存在様態は健全という言葉によって特徴づけられる。一方、入れ物としての人間は、ある種の空虚さを内包した物質的存在として現れるが、その主体は必ずしも不足感や欠陥を感じるとは限らない。
実体においては、その人から発せられる言葉のすべてがその人自身の本質から紡ぎ出され、その疑問や直感のすべてが自然の合理性と調和している。これに対して入れ物は、他者からの介入と浸食を受けた、あるいはより正確には、それを許容してしまった結果として、もはや「その人自身」とは言えない存在へと変質している。
自分自身をよく観察してみてほしい。
感覚的な話をすれば、普段自分だと思っている人格、つまり、今この文章をいつも通りに読んでいるモードAの自分以外に、感覚を切り離して客観的にモードAに評価を下せるモードBの人格を捉えられる。さらに頭部に意識や注意を払うと、何かが集中している部分がおそらくモードAでは前方に、モードBではそれよりやや後方に感じるはずである。
通常活動時において、AもBも前方集中が主体なのは同じだが、仮説だが、Bの活動の有無及び大小が入れ物と実体の違いを生む。
入れ物と実体の二重性は、時間の固有性という観点からさらに深い示唆を与える。各人が持つ時間振幅は大きく異なっており、そのため、一見同じ現実世界に立つ人々の間にも、まったく異質な存在様態が同時に共存している。しかし興味深いことに、この異質性は必ずしも分断を意味するものではない。なぜなら、異なる時間振幅を持つ者同士であっても、共有可能な接点を持ってしまうがゆえに相互の認識と接触が可能となるからである。
ここで注目すべきは、入れ物から実体への変容可能性である。個としての純度を高めるための「浄化」作業を通じて、入れ物は実体へと近づくことができる。この過程には、アクティブな自問自答の時間が不可欠となる。ただし、ここでいうアクティブとは、思考のトグルを意図的に制御することを意味する。
入れ物の性質が強い人との関わりは、必然的に自己の純度を低下させる。入れ物は他の入れ物から解放される鎖を自らさらに強固に締め、実体は入れ物への汚染切符を強制的につかまされる。特筆すべきは、現代社会において、この入れ物としての存在様態が極めて一般的となっており、その広がりは3σではなく、4σにも及ぶほど大きく悲観的なものであると例えてもいいだろう。
ゆえに、例え一時実体になったとしても、一度外に出たら基本的に瞬時に入れ物化する影響を大なり小なり受けることは避けられない。実体がこの変容を防ぐためには、確立された浄化作業を日常的なルーティンとして組み込む必要がある。そうすることで、実体としての存在様態を維持、あるいは再獲得することが可能となる。
唯一純粋な実体を長期に渡って維持する方法は、実体となってから意識的に孤立し、入れ物と接触する比率を冗談ではなく最低水準として12:1に抑え込むことが必要だと思われる。これは私の観察と実効による1つの導きだした答えである。この値は具体的には24時間×5日間の実体成分の精錬によって、12時間程度までなら入れ物と接触しても、実体の維持や入れ物からの影響をより負荷なく適度に修復できる1つの水準である。
この理論における重要な概念として、「臨界点」の存在を指摘しなければならない。これは単純な認識論的な限界を示すものであり、時間振幅をはじめとする複数のパラメーターによって規定される。臨界点の存在は、実体と入れ物の区別自体が相対化される高次の視点の存在を示唆する。
このように、人間存在の理解には重層的なアプローチが必要となる。実体と入れ物という二分法は、確かにある観察地点からは有効な理解の枠組みを提供する。しかし、より高次の視点からはその区別自体が相対化されるのである。このような重層的な理解こそが、人間存在の複雑性を適切に把握する鍵となる。
この考え方は、ある意味で1つの朗報ともいえる。この認識構造、すなわちフラクタル的な上位パターンの存在が前提にしてあり、また、パターン認識の実用的な分解能の理論を内包しているからである。つまり、この分解能の制限自体が「より上位のパターン追究において無限後退ではなく、実用的な臨界点で止まることを理論自体が想定している」ということである。
実体と入れ物の二重性を意識的に把握し、その間の移行を自覚的にコントロールする技法を確立することで、我々は従来にない存在様態を獲得する可能性を持ち、それは実体への回帰でも、入れ物としての受動性の肯定でもない。むしろ、両者の特質を統合した新たな存在の在り方を示唆している。
この可能性を具体化するためには、個人レベルでの実践が不可欠となる。それは日々の生活における意識的な浄化作業から始まり、徐々により深い次元での変容へと至る道筋を辿る。この過程において重要なのは、変容の各段階における適切な認識と、それに基づく実践的な対応である。
この変容過程が持つ集合的な意味における個人レベルでの実践は、必然的に周囲との関係性にも影響を及ぼす。実体としての存在様態を強化することは、同時に他者との真の意味での交流を可能にする。それは表層的なコミュニケーションの次元を超えて、より本質的な次元での共鳴を生み出す可能性を持つ。ただし、実体と入れ物の間の移行過程は常に不安定性を伴うため、時として深刻な心理的危機をもたらす可能性がある。これは不適応の問題ではなく、存在様態の根本的な変容に伴う必然的な過程として理解されなければならない。
実体は、自分自身の価値がわかっている。また、入れ物の価値の低さもわかっている。だから入れ物になる自分を避ける傾向にある。
これは差別ではなく、積極的分断である。つまり、分断した様相が差別であることを理解しつつ、本質が向上と改善になっており、自分自身が分断による孤立と、実体同士の共鳴の瞬間圧力の生み出す徳の価値の高さがより世界にとっての恵になると受け入れている。
その過程にある感謝は、入れ物の世界の言葉にはない概念であると理解している。