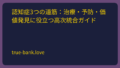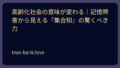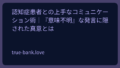相手の表面から感じられる差というのは、いかに本人が真の意味で努力してこなかったかの指標である。これは大小に関わらず当てはまるが、大きい場合は特に質が悪い。なぜなら、その頃には環境依存由来の能力的暴力が真実の自分を委縮させ、理性による合理的判断によって、自己の力で能力を向上させたと誤認させるからである。つまり、「本当にポテンシャルを発揮していると評価される人は、自分の『質』を変化させた回数が魅力の根源である」という事実を認めるのが怖いということを、この能力が高い愚者はア・プリオリに知っていたのである。
よって、もし恵まれた先天的能力や環境に後天的努力が加わった人に対して、この人には敵わないという心の声を自分で感じた場合、その表現が恐怖であるならば、それはたいてい嘘である。自分との対話で解決しないのであれば、初めて恐怖かどうかを検討すべきである。もちろん、嘘である理由は、真に恐怖すべき対象に対して失礼だからということでもある。真に能力的に恐怖を抱かせる者たちは、たいてい環境に潰されて日の目を見ない。つまり、ただ単に発見と遭遇が困難である。換言すれば、そういう対象は逆境の中で生まれやすく、その存在確率が他より高いとも言える。
我欲の主張は簒奪の台頭であるが、本質的に欠如が織り込まれた我欲という表現自体、すなわち、欠けた状態が真という欠陥それ自体が存在証明になる概念なのである。つまり我欲の命題において、奪いとり、戦うことに類する主張は、文字通り主調としてレーゾンデートルと同じなのである。
よって、我々の判断がいかに表面的であるかを浮き彫りにしなければ、真実を見誤る可能性が高いという結論に達する。自らの「質」を変化させた回数を魅力の根源とすることへの恐れは、自己変革の恐怖、すなわちコンフォートゾーンからの逸脱に対するものなのか、変革そのものが持つリスクの認識から来るものである。後者ならば、その恐れは賢明な警戒心として評価されるべきである。
また、真に恐怖を抱かせる「存在」が環境に潰されて日の目を見ないならば、普段接する恐怖の対象がどれほどの脅威を持つのだろうか。我々の恐怖が単なる自己の不安や不確実性から生じる幻想かもしれない。それならば、それは怠慢からくる当然の帰結であり、ただの幻肢痛である。この幻肢痛は、実体のない痛みでありながら、我々の心に確かに存在する。注意すべきは、この幻肢痛を抱いている者が才能ある挑戦者なのか、逃げ癖のある現実主義者なのかということである。
いくらでも判断の方法はあるが、もし今の自分が性質として「治療を望む」、すなわちどうしても今の役割の受け入れを拒むのであれば、自分との対話で解答が導出されるのは確定事項であることを認識するだけでよい。自己の内面との対話は、最も深い洞察を得るための唯一の手段であり、その対話の過程で初めて、我々は自らの真の姿と向き合うことができる。
世の本質を観る者は不遇の意味でラベルされた統合失調者であると私は断言すると同時に、上記の現実主義者こそ、世界を主語の対象とした文脈において、現在の世論的風潮でラベルされた統合失調者であると苦言を呈しておく。
今まで見てきたように、表面的な差異の評価には限界がある。言い換えれば、大多数には感じ取られず、観測もされないということであり、それは同時に他者に影響を与えず、自身の座標を動かすイベントを放棄し、壁を築くことでもある。真に重要なのは、我々が表面を越えて深層に存在する本質を見抜く力であり、その力を如何にして鍛えるかである。相手の自己洗脳がア・プリオリ的と誤認されて施されている以上、頼りになるのは相手の言葉ではなく、相手の漏れ出た成分を分析し、環境由来の能力を全て武装解除する外科手術をあなた自身で行い、その残滓を正しく評価することである。この手術は、他者の真の姿を暴き、厚い皮の幻影に負けない鋭い眼を養う過程でもあり、我々の洞察力を鍛えるための絶好の実践でもある。
この力は反骨心と反比例する。この力は維持しなくてもいい人も多いだろう。しかし自分自身の事情として維持を望むのであれば、消失の前に自分に合った格納方法の探索も同時並行で進めておくべきである。この優秀な力を用いれば、日の目を浴びない眠った脅威が―今までの論が覆ることになるが―少し高い頻度で見つかるようになってくるだろう。