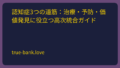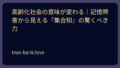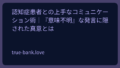※Click here to see this article written in English.

時間の推移は、我々の認識において完結性を持つと錯覚されがちだが、それは始点と終点の循環的連鎖という幻想に過ぎない。
時間は固有価値であり、不平等なものである。
時間と時刻の二重性の錯覚から解放されない限り、我々は自身の行動原理を本質的に理解することはできない。
驚くべきことに、人間の思考体系における最大の盲点は、自己完結性への過度な信頼にある。我々は自らの思考や行動が、ある種の完全な論理的枠組みの中で行われていると考えがちだが、これこそが最も危険な自己欺瞞である。
世の中に存在する言葉のうち、正しくない解釈を孕んで普及した言葉が一定数隠匿された状態で活動している。
今この瞬間に使用した「行動」という言葉もその一つであり、その元来の固有イメージは「思考の具現化」や「思考の試行」が当てはまるであろう。 日常で使われやすい言葉は、その言葉が本来結びつくべき言葉への方向性を分散させて乱反射した状態なので心地よく多方面に使われる。
形骸化という言葉は、多くの場合ネガティブな文脈で語られるが、実のところ、
自浄的最適化による自然な形骸化こそが、システムの本質的な進化の証である。
これは生命システムにおける細胞の自然な新陳代謝と同様、避けられない、そして避けるべきでない過程である。
ただし、この形骸化は、意識的な制御下になければならず、それは単なる時間経過による劣化とは本質的に異なる。時間経過による劣化は逃避的腐食の遷移結果であり、ここで主張したいのは浄化的最適化である。
我々の認識体系における最大の誤謬は、制限を上限として捉えることにある。
制限とは本来、状態遷移における障壁であり、それは乗り越えるべき壁ではなく、むしろ新たな状態への転換点として機能すべきものである。
この視点の転換とは、我々の行動様式を根本から変える可能性を秘めているにも拘らず、これは訓練の結果の嗜癖により気づいたら獲得されているものであり、かつ発見的性質をもつため獲得できるかは多少運である。
よって単位時間当たりに転換の発見数をこなせる人は相対的に見て非常に少ない。
つまりここまでで言えるのは、澄明さの獲得は単なる思考の整理を表しているのではないということである。
それは潜在的な形骸化要素を浄化する過程であり、この過程自体が思考の深化をもたらす。
しかし、この澄明さは受動的な時間経過によっては決して得られない。それは能動的な思考の累積によってのみ達成される。
受動的循環時間とは、実質的には退化の過程に他ならず、それを排除することなしには真の進化は望めない。
自身のプロジェクトを持ち、日々改善と試行を重ねていくと、
「ルーティーンをいかに組むか、ルーティーンをいかに厳守していくか」を
整える要素の探索行動に繋がってくる。
自身の不調を外部要因に求めることは容易い。
しかし、それは多くの場合、推移律の過小評価と怠慢的態度の結果である。
我々は因果関係を直線的に捉えがちだが、実際の因果は複雑な網目状の構造を持っており、その認識の欠如が不調の本質的原因となっている。
最も興味深いのは、たった一つの工夫が劇的な変化をもたらすという事実である。
これは決して誇張ではなく、むしろ複雑系におけるバタフライエフェクトと同じとして理解すべきである。しかし、この「一つの工夫」は、
表層的な技術や方法論ではなく、思考体系の根本的な転換を意味する。
その点からも、完結していると当然に思っていることとは、その始まりが終端からの推移に基づいて導かれており、矛盾がないことを確認しなければならないのだろう。
やるべきことのハードルを下げることというのは、単なる簡略化を示していない。それは本質的な構造の理解に基づく再構築であり、その過程で不要な要素が自然に削ぎ落とされていく。
この削ぎ落としの過程こそが、真の意味での最適化であり、美しい形骸化の特徴になる。
我々の認識体系における最大の課題は、静的な完結性への執着である。真の完結性とは、始点と終点の間に存在する無数の状態遷移の可能性を認識することも含む。
それは、固定的な終着点ではなく、常に新たな変化の可能性を内包した動的な平衡状態として理解されるべきである。
この動的平衡の認識は、我々の行動様式を本質的に変える。
目標達成という固定的な思考から、継続的な進化のプロセスという思考への転換をもたらす。 この転換こそが、真の意味での自己実現への道筋となる。
視点の転換の実例として、このプロセスという概念自体、未来のある時点からすれば、我々人間はリペイント可能な対象として像を移し得る。それならばプロセス自体を普及された意味:「過程」として捉えるのではなく、成し遂げるべき目標や対象とは、それを達した後にそれ自身の効用・存在によって産まれた「何か新しい現象の追究」の上に支配されて必然的に出る結果のことであるとわかり、それ以外の方法でそれを目指すことは偶発性に祈ることと同じであると気づく。
よって純粋な「その目標を絶対達成する、達成したい」というアプローチは、紛れもなく「それ以外の方法」として評価されてしまう。つまり誤りである。
プロセスの言葉の方向性とは、振り返る過程ではなく、支配の結果としての必然性と転換すれば、ここで挙げた動的平衡の認識が、継続的な進化を意味するものではなく、求める結果を支配する拘束具なのだと捉える可能性もある。
そして最後の落とし穴として、どのような転換を選ぶ人生にするかの疑似乱数の調整作業のことを「転換の発見」と呼ぶことに気づくことが必要である。結局のところそれを落とし込み、実践するかにかかっている。おそらくこの作業は、目の片方を通して理性を知り、もう片方でそれに反する崩壊を生体反射する意志をステレオグラム化した末路として、体癖まで形骸化した思考習慣の応答によって世界から還ってくるもの なのだろう。